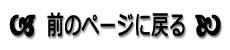●追跡行の果てに
【登場人物】
・ライル・クロイツァー
・アステール
・ウィク・イグナイター
・メイ・アサーシャ
・デュリン
・シル
・マグリア・A=ドラグ
・ボルブ・ボルドリック・ボロボレイト
・ドクトル・ハニィマシュー
・ニレル・ナタン
・シェック
・エイミィ・イッシュ(NPC)
・アルフレド(NPC)
・エクス(NPC)
日が高い。
真昼間の街は喧騒が絶えず、往来が激しい。市場の広がっている場所などはよく周囲を見て歩かないと危ないほどだ。ボルブ・ボルドリック・ボロボレイトの装飾店などはガチャガチャと武具を提げた者たちで店の外まで人だかりができているほどだ。
しかしライル・クロイツァーはこともなげに周囲の人だかりを避けて、高い目線で辺りを見渡す。黒地に金の流麗な装飾の施された鎧の擦れる音を極限まで落とした落ち着きのある動き。
人を探しているのだ。
いつもの訓練と業務を終えて待機時間になったので、宿舎に戻って一休みしようとしていたのに上官から呼び出されたのだ。そして人探しを頼まれた。ライルの隊が全員駆り出され、少しの間でいいから探すのに協力してくれと言われては断れない。相手が上官で、なおかつ見つかるまで探せと強要されたわけでもない。
「休養も大事だと思いますがね」
それでも同じの隊の連中の手前無条件に引き受けるとは言えなかった。訓練と業務をこなした後の疲弊した身体を無理やり起こして上官の手伝いをするのだから、ある程度の譲歩を引き出さなければ示しがつかない。
向こうもそれを分かっていたのか予め用意していたように金を握らせてくれた。おそらくは人探しを頼んだ相手から貰ったものだろう。一部が流れてきただけでも上々だ。ライルがクロイツァー家の人間でなければ、こう上手くは行かなかったに違いない。
そうしてライルは人探しをしている。
散り散りに隊を分け、各自で探すように伝えた。ライルは暗にサボっても問題ない、と言ったわけだ。
それは探す相手がアステールという男だからだ。
王立樹法研究院の若き天才だが、放蕩な少年としても有名だ。夜間はカフェ・ド・エクスで遊んでいるというのはもっぱらの噂であり、女好きのする顔ということもあって評判は多い。悪いとか良いとか以前に、ひたすらよく聞くのだ。
それもあってあまりライルも心配することなく、探していた。いざとなれば彼は自分の樹法でどうにかしてしまえるだろうし、捜索も面子による建前というところが大きいはずだ。
そうやって市場を見るのか人を探すのか曖昧な風に歩いていると、真正面から苛立ちを隠していない女が出てきた。ライルのことが見えていないようで、ドタドタと歩く姿にぎょっとした通行人が道を避けているから辛うじて人にぶつかっていない。
しかしライルは他の通行人たちに合わせて避けようとはしなかった。
あまりにも危なかっしいからだ。
自分にぶつかれば、他のもっと危ない連中にぶつかる前に自分の行為がいかに危険か気づくだろう。
ライルはわざと市場を見ているフリをして避けずにいた。
「んっ!」
案の定、女――ウィク・イグナイターはぶつかった。ばっと音を立てるくらいの勢いで顔をあげて、ライルの姿を見つける。すばやく視線を全身に移し、どんな身分なのか察したようだ。
ライルは一応剣を提げていた自分の姿に相手が気づいたのだと悟った。
「大丈夫ですか?」
ウィクが銀の長い髪の毛をぱっと揺らして頭を下げる。
「え、ええ。ごめんなさい。少し周りが見えてなくて」
少しではないだろう、と言いかけたのを翻してライルはにこりと笑った。業務的な笑みは騎士になる前に家で身につけた所作だ。
「俺だから良かったが子どもだったら危なかった。今後は気をつけたほうが良い」
「ええ。そうするわ」
と言ってウィクは再び駆け出そうとした。
ライルは彼女が少しも反省していないことに気づいたが、声の上ずりや口調、足踏みするような焦りを見て違和感を覚えた。
「ちょっと待ってくれ」
声をかけるが既に遠くへ行こうとしている。思わずライルは手を掴んで、止めた。
「な、なんですか?」
依然焦りが浮いている。騎士に呼び止められたから、ということではなさそうだ。恐怖で強張っているわけではなく、なにか不穏を嗅ぎ取っているように見える。
「なにかあったのかな? 言ってくれると嬉しい」
今度こそウィクの顔に明確な怯えが混じった。これは騎士に対する恐怖というよりは、秘密を誰かに知られたくないという類の怯えだ。騎士として見過ごすことはできなかった。
**
「なるほど」
二人が会ってから少し経った。ひとまず落ち着いたところで話をしようと提案したライルはウィクをカフェへ連れていき、話を聞いた。
コーヒーを出した店員――アルフレドなどはライルの顔を伺って女連れであることについて詳しく聞きたそうな顔をしていたが、努めて無視した。カウンターのほうでは常連客の一人であるドクトル・ハニィマシューとオーナーのエクスがライルを見て物珍しそうにしている。それも気にしないようにライルは注意深く意識の外へ追いやり、今はひとまずウィクの話を聞くことに専念した。
「とにかくまずいんです」
そう、彼女の隠し事はかなり危険だった。それこそ迷子なんて目じゃないくらいに。
「じゃあその爆薬はなるべく安全に回収したいね」
ウィクは錬金術師だという。爆発物関係のものを作るのが得意で今日もそのたぐいの商品を抱えて街を歩いていたらしい。
しかしそこで問題が発生した。
爆薬を小人種の女に盗られたというのだ。
女は何やらよく分からない話をした後にパッとゴーレムを使ってウィクの手にあった爆薬を盗んでしまったという。そしてウィクは完全にその女を見失ってしまい、下手に爆発でもしようものなら建物の一つや二つなら簡単に壊れて、街で大きな被害が起きて、自分も責任を問われるのではないかと怯えている。
ライルは自分の目に狂いはなかったと安堵しつつも、その状況に少なからず危機感を覚えていた。
今この都市にはどこにいるかも分からないアステールが放浪しているのだ。
もしうっかりアステールがその小人種と鉢合わせでもしようものなら、とんでもないことになる。
それどころかウィクのよく分からない女、という評が間違えていたらもっと問題だ。計画的犯行で、よく分からない女ではなく、とびきり怪しい女だったら本当に取り返しがつかない。
「ウィクさんは黙っておいてほしいだろうけど、これは手に余るよ。流石に黙っている訳にはいかない」
「そうですよね」
項垂れているウィクはライルの奢りである飲み物に口をつける様子もない。
ライルは少し待っているように伝えてから、すぐに最寄りの詰め所に事態を伝えて、カフェに戻る。
まだ彼女が待っているかは五分五分というところだったが、幸いまだ待っていた。
「待っていてくれてありがとう」
「流石に逃げるわけには行かないでしょう。それに本当なら私もついていくべきでした」
屹然とした態度には、さきほどまでの焦りが見られない。もしかするとこちらのほうが本来の彼女に近いのかもしれなかった。
二人はカフェを出て外を歩きながら、話を続けた。
「ウィクさんを連れて行かなかった理由は簡単だ。君が拘束されていたら、話が聞けない」
「なるほど。捜索を手伝えということですね」
ウィクは話のわかる人だな、とライルは判断した。
ここでライルが何らかの脅しをする気かと推測されていたら、話がこじれて面倒だった。踵を返して詰め所へ彼女を置いていっただろう。しかし物分りの良い彼女ならついて来てもらったほうが手っ取り早い。
「最後に小人種の女が向かった先は分かる?」
「えっと、向こうの通りで見てあっちだから……」
港の方ですね、とウィクは遠くを指さした。
ちょうど歩いている方だ。
二人は頷いてそちらへ足早に向かった。
**
港は軍港と別れているため、ほとんどが商船だ。
大きなクレーンが樹法で動いて、湾岸に留められた船から荷を運び出している。喧騒は市場の比ではなく、絶え間なく聞こえる怒声は慣れていない者にとっては怖いくらいだ。
しかし片側が海として開いていることもあって、そこまで音が籠もる場所ではなかった。
何十もの船が港へ停まっている。それの数十倍にもなる人が声をあげて働いている。骨惜しみしない頑強な船乗りたちは、互いに声を掛け合いながら荷を下ろしたり船の位置を指示したりと、めいめいに働いていた。
その脇にある、港の倍は大きい市場が開かれ、新鮮な魚介類が卸されていた。そこでしか食べられない料理も並んでいるのか、船乗りたちの隙間におおよそ港には似つかわしくない出で立ちの者もいる。
「港に逃げたなら店の並ぶところにいるだろう。どんな格好か教えて欲しい」
少し悩むようにウィクは顎に手を当て、しばらく黙りこくった。
ようやく顔をあげたとき、ウィクはライルがあらぬ方向を向いていることに気づく。
「どうしました?」
「いや、なにか騒がしいようだ」
そう言ってライルが顔を向けている方向は、海だ。大きなクレーンや市場の影になっていて見えないところへ人が集まっているのが確認できた。
そしてライルの横で同じように海を見ている少女――エイミィ・イッシュがいた。
「ああ、あれは多分海獣ですね」
「なんです、それ」
ウィクは同年代に近いエイミィに初対面ながらあっさり気を許したのか、心なしか態度が柔らかい。
エイミィはもっと遠くを見ているかのように目を眇め、海風になびく髪の毛を押さえて呟いた。
「多分何か危険な獣が出てます。攻撃ができるタイプの樹法使いさんたちが対処してるんでしょうね」
他人事のように話す彼女に、これ以上そこへ近づく意志は感じられなかった。
しかし二人は違った。
「俺はあっちへ行く。ウィクさんはここで少し待っていてくれ。今はあっちのほうが先だ」
「私も行きます」
そう言ってウィクはポケットから小瓶をいくつか取り出す。小指に挟んだ小瓶のなかに、粘度の高い半透明の液体が密封されている。
「私も戦えるので」
「それはいつも持ってるのか?」
「まあ、念のために」
どんなことを想定しているんだ、という言葉をライルは飲み込んだ。あまり事情に踏み込みすぎても相手にとっては不快かもしれない。
二人して市場を出て港へ出ると、喧騒が一層激しくなっていた。小舟で飛び出す四、五人の集団が何隻もおり、飛び交う言葉には緊迫感が宿っている。
「数珠触腕が出たぞ! 戦える者は全員出ろーっ!」
一際激しい気迫で声を荒げる壮年の男は腕まくりした腕をぶんぶん回して船乗りたちを急き立てた。大勢が小舟に乗って海へ出ていく。ライルとウィクも乗って良いかと聞くと「馬鹿野郎! 今そんなこと聞いてる暇ぁねえだろうが!」と怒鳴られてしまい、さっさと乗り込むことにした。彼にとっては怒っている自覚もないだろう。それくらい罵声が自然のなかに息づいている。一瞬の判断が死を招きかねない場所でぐずぐずすることなどできないのだ。
「あれか」
ライルは小舟を漕ぐ若い男に確認を取り、うなずくのを見てから再び視線を海獣に戻す。
静かな波間を割るようにして現れた巨体が船を揺らした。
小さな家ほどの大きさの、赤黒く濁った頭部が海から出ている。まぶたのない目が四方を観察し、周りに散らばった船を容赦なく攻撃してきた。
名前の通り触腕だ。
大きな円状の粒にざらついた鉤爪のようなものがついている。それが触腕に満遍なく散っており、一振りするごとに小舟がばらばらに砕け散って乗員が海へ放り出された。彼らを他の船が救出しながら、海獣の隙を伺う。
しかし目の位置など飾りに過ぎないのか、どこから攻撃しようと近づいてもまたたく間に触腕が振り下ろされ、そのたびごとに怪我人が増えていく始末だった。見た目は大きなタコなのに、巨体に見合わないほど俊敏な動きをするせいで攻撃一つとっても破壊力が過剰だった。
「離れろーっ! 樹法が飛ぶぞ!」
一隻の舟から声が上がると共に、まばゆい光が昼間の空に浮かび、轟音と共に海から蒸気が上がる。うねるような火が宙へ浮かんで海獣の頭部目掛けて飛んだのだ。近くにいるだけで熱が感じられるほどの高温はあっという間に海水を蒸発させ、辺り一面が水蒸気まみれになる。
「風がいる! 誰か使えるやついないかーっ!」
蒸気で互いの姿も見えない中、声を張り上げた誰かに応じて、不自然なまでに大きな風が吹き現れた。これもまた樹法によるものだ。船乗りたちは自ら風を起こせる樹法使いたちを重用している。だからこそこんな時に応じられる者も当然いた。
しかし蒸気で吹かれて現れた光景は、みなが望んだものではなかった。
赤黒い頭部が海を持ち上げるようにして再び現れ、平然と触腕を振りかざす。
攻撃のタイミングを読まれ、海中に逃げられたのだ。
傲然と振り回す触腕にぶつかった小舟がばらばらに砕けていき、乗員が海へ投げ出される。しかし一人のイヌ科獣人種――メイ・アサーシャはただで海へ放り出されるほど甘くはなかった。
砕けた小舟から跳んだメイは数珠触腕の頭部へ拳を振り下ろした。
「せっかく着いたばっかりなのにこのヤローっ!」
握りしめた拳を身体全体で押し込むようにして頭部へ振り下ろしていく。彼女より大きな図体だからこそ、点の攻撃になってぬめりで光沢を放つ頭部を貫通するかと思われた一撃だった。
感嘆の声が船乗りたちからあがる。
しかし数珠触腕も港まで来るだけの実力がある。野生の勘でどぶりと海中へ逃げ、あえなく拳は振り下ろしどころを見失って身体ごと海に沈んだ。わーわーと悲鳴を上げるメイに幾人もの船乗りたちが助けをよこし、どうにか助かった。
ウィクの乗る舟も彼女を助けに向かい、多くの舟と鉢合わせた。
そこで偶然見知った顔を見つける。
爆薬を盗んだ小人種だ。
なぜか船乗りの背中に立っており、やいのやいのと騒ぎながら手持ちのゴーレムでメイを助けていた。
「デュリンね、あれ食べてみたい!」
「ちょ、危ない! あたしを助けるのか殺すのかはっきりして!」
メイは足を掴みながら引っ張り上げてくるゴーレムに対して悲鳴のような叫び声をなげつけるが、デュリンは気にする様子がない。
やだやだ絶対やだー! と喚く姿はウィクの見た小人種のまんまである。見間違いな訳がない。
それによく見ると彼女のゴーレムが、なにやら物騒な箱を持っていた。
爆薬だ。
血相を変えたウィクが船上で手を振りあげる。
「ちょっと、危ないから渡してちょうだい!」
普段声を張り上げることのないデュリンだったが流石に命が関わるとなると別だ。船乗りとデュリンよりも前に立つゴーレムが、メイを引き上げた後に単独で前へ出る。ゴーレムマスターであるデュリンの命に従い、数珠触腕を捕らえようとしているのだ。
しかし数珠触腕はそんな周りのことなど関係なしに攻撃を再開する。
のっそりと海中から頭を出して、舟に向かって触腕を振り回した。
その影響で大きな波が生まれ、小舟たちはぐらぐらと揺れた。船乗りの頭を掴むデュリンも体勢を崩して舟に滑り落ちた。一瞬動きが鈍ったゴーレムが船上で足を滑らせ、持っている箱を取り落とす。
振り切った触腕が見事にその箱へ直撃し、轟音とともに炸裂した。
城の柱くらいはありそうな大きな触腕が半ばからちぎれ飛び、爆発の影響で海に莫大な水柱が噴き上がる。辺りの小舟たちは転覆を防ぐので手一杯になる。
「あ、完全に配分はぴったりだったのね」
ウィクは一人冷静に爆発を見ているが、頭から水を被ってびしょ濡れだ。
次第に黒煙が辺りに広がり、デュリンたちの乗る舟は完全にひっくり返った。
数珠触腕も全体を蠢動させつつ痛みにのたうち回り、海へ潜ろうと動いた。
そこへさらに光が差し込む。
先程よりもずっと収斂された炎だ。まるで蝋燭の火をそのまま伸長したような鋭い明かりが宙を貫いて、数珠触腕の頭部へ突き刺さる。海の上へ出ていたいくつもの触腕がバラバラに痙攣し、しばらくするとぐったりと浮かんできた。
火の根が向く方には、銀の髪をかきあげる細身の男が立っている。
アステールだった。
**
海獣が退治された後も港の喧騒はやまなかった。むしろ海で騒いでいた連中が港に戻ってくることでより大きくなったと見ても良い。怪我人の治療に周囲にいた船乗りたちが駆けつけ、軍港から呼ばれた医者たちもおっとり刀で駆けつけていた。街の外れからたまたま来ていた少女――シルも手当てに参加していた。薬売りのような立場からすればこういうところで恩を売るのは顧客が増える可能性もあるので、願ったり叶ったりだ。
要請を受けて駆けつけた治癒術師もちらほら混じっていた。ニレル・ナタンなどは筆頭だ。あちこちで怪我人を治しながら、そのたびに感謝の言葉が飛び交う。
船乗りたちは悲しみに溺れるわけでもなく、恨み骨髄に徹するわけでもなく、騒がしさのなかで日常に戻っていた。
彼らは海と戦うものたちだ。危ない海域を通過することもあれば、海賊に遭遇することもある。そんな生活を営む船乗りたちには、こうした危険すらも過ぎ去ってしまえば過去のものとして流すのが通例だった。
海水でびしょ濡れになった人々は港の喧騒から少し離れた場所で樹法使いによる風を受けて乾かしたりしていた。メイとウィクも盛大に濡れてしまっていたので船乗りたちに混じって服の端を掴んで絞ったり髪を撫でつけている。メイはぶるぶると身体を振るって水を払いたい欲を抑えつつ、貸し出してもらったタオルで顔を拭いていた。
デュリンは全身濡れたままあちこちを走り回るので早々にウィクに捕まっていた。爆薬を盗んだ件を官憲も混じって注意されていたが、果たしてデュリンが反省するのかは怪しいところだった。
倒された数珠触腕は大きなタコとして早速捌かれており、船乗りたちに振る舞われている。
ちょうど港に来て市場を覗いていた料理人たちが手を貸し、その場で料理にされている。
「火薬の匂いがキツいから揚げて食うほうが美味いかなー」
料理人の一人、シェックは大きな触腕に調味料を揉み込んでいた。周りの船乗りたちは火薬の臭いなんか気にせず細く切られた生の触腕を噛んでいる。塩を振ってあるからそれだけでも食べられるらしかった。
「アレみたいに大きくなれるからいっぱい食べるんだよ」
港の騒ぎを聞きつけてやってきた子どもたちにもシェックは料理を差し出す。手づかみでガツガツ食べる子どもたちにとってはちょっとしたおやつ代わりだった。
最後に数珠触腕へ一撃を加えたアステールは早々に軍に捕まり、船乗りたちから引き離れていたがそれでも歓声が時折投げかけられていた。
腕を掴んでこれ以上逃げないよう押さえるライルは、女相手には手を振って笑顔を振りまくアステールに辟易としつつも表情には出さない。
「なんでこんなところに居たんです?」
「まあ、人を助けるには理由なんていらないじゃないか」
飄々とした態度を崩さないアステールはライルに引きずられるようにして港を後にする。
しかしそれを遮る影が現れた。
「誰だい?」
アステールが先んじて声をかける。そのせいでライルがどけるタイミングを失って、立ち止まった。
目の前の女はすらりとした長身で、アステールを見下ろしている。
興味深そうに目を見開いて、金色の瞳を二人へ向けた。
「私はマグリア。これ、キミが欲しそうにしてたからあげるよ。どうぞ」
そう言ってマグリアはアステールに紙包みを手渡した。
ぽかんとした表情を浮かべるアステールが、包みを開く。
揚げたタコが入っていた。
「俺はとくに欲しがってないよ? だけどキミみたいな美人からのプレゼントだ、ありがたく受け取ろうかな」
そうしてアステールはウインクを返した。
しかし傍目から見ていたライルには、そのアステールの態度が少し強張っているように感じた。
「え? でもさっきからちらちら露店を見てたでしょ? 女の子を見るフリしてたのは、少し面白かったよ」
そう言ってマグリアはピースサインを作って、自分の目の下をトントンと叩いた。
「は? 俺はそんなために出ていったわけじゃ――」
「まるごと一匹食べると背が伸びるってうわさでも聞いたのかな」
「はっ!? お、俺がそんなことのためにわざわざここまで来るわけないじゃないか!」
マグリアが確信をついた、というような笑みを浮かべる。
「じゃあ身長を気にしているのは当たってたんだ。私を見る目に少し違和感があるなとは思ってたんだよ。まさか髪の毛じゃなくて頭頂部を見てただなんてね」
面白かったよ、とマグリアは言って手をひらひらと振って二人の前から姿を消した。
「おい、待て! 話はまだ終わっちゃいないぞ!」
駆け出そうとするアステールをライルが引き止める。
「もう帰りましょう。それでも食べながら」
ライルは業務的な笑みで本心を隠し、笑い転げそうになるのを押さえてアステールを引っ張って帰った。
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp