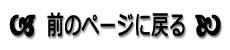●人食い刀事件
地滑りで現れた新しい発掘場所で古代人の樹石を発見した考古学者アーベン。
しかしそれは、恐るべき樹法具だった……。
【登場人物】
・ブロックマルツ
・メノウ
・アーベン
・ルイーズ
・スイ・フィラロイト
・ミルシュカ
・ルシェン
・トビア・サンチェス
・ニレル・ナタン
・アザミ
・ルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオ
・ボルブ・ボルドリック・ボロボレイト
・フクマル
・ライラ
・ドクトル・ハニィマシュー
・ヴェックマン
・ムツラ
・ユピテル
樹法具、樹石。
これらは偉大で貴重な品物である。
“反逆者”エルディールが源樹を破壊したのち、これらの品物はほとんど作られていない。つまり現存する物の多くは、千五百年程度よりも古いものなのだ。
ノードス戦争時代に作られた樹法具のほとんどは戦争中に失われたか、あるいはその後の年月で散逸している。おまけに残っているものも、使い方や使うための樹文の失伝していると来ている。使えているものも、本来はひょっとしたら違う使い方だったかもしれないものを、解る範囲で使っているに過ぎない。
例えばソーン市内にある西側管理の粉ひき小屋には水車も風車もついていない。
これは日光を当てると回転するという車輪の樹法具を粉ひき車に転用しているからで、これのおかげで西のパン屋はいつでも挽きたての小麦粉を使うことができる。夜以外は。
この車輪が本来粉ひきに使うものなのかどうかは、王立樹法研究所のトビア・サンチェスをもってなお、全くわかっていない。
だから“現存する樹法具”で、“正しい用途”が分かっている樹法具は極めて貴重で高価なものと言える。
「結局」
と、少年の域を出たばかり、といった若いにきびの男は得意げに言った。
「今、俺……私たち人種が使っている火薬や冶金、帆船やらなにやら一切合切は、“反逆者”の尻ぬぐいなわけです。“反逆者”が源樹を壊しさえしなければ、俺たち人種はもっと便利で豊かな暮らしをしていたはずなんですから」
受け売りだな。
裏町組合の親分衆の一人である獣人種のブロックマルツは、すぐに見抜いていた。
まぁせいぜい気分よくウタってみるといい。何が出てくるか楽しみだぜ。
応接室は小ぎれいに片付いている。成功した商人、くらいの雰囲気だろうか。
煉瓦を積んで作られた壁のあちこちには額に収められた絵画が飾られていて、その多くは静物画。
暖炉に火は入っておらず、マントルピースには銀製の燭台と水差し、お揃いの銀杯が揃って乗っている。
赤い見事なカーペットはエードローエのもので、窓のあまり大きくないこの部屋を明るく見せていた。
小さな窓の外では、子供たちが遊ぶ声がする。
フェルト張りの大きなソファに座ったブロックマルツは、彫刻の施された猫足風テーブルを挟んで座る若い男を面白そうに眺めた。
舌に油でも垂らしたかのように良く喋る。
その恰好はブロックマルツとは正反対だ。
おそらく貸衣装のしゃれた上着はからし色のスボンと合っておらず、首に巻いたネッカチーフが浮いている。
体型はひょろひょろで、いかにも衣装に着られているふうだ。
恰幅が良く、特注の高価な服をわざと少し崩して着こなし、尻尾を揺らしながら葉巻をくゆらせるブロックマルツとは、いかにも格が違う。
しかし若い新人詐欺師は、それに全く気付いていない様子で、ブロックマルツにはそれがおかしくてしかたない。
この男がやってきたのは、ブロックマルツの表のシノギを見ての事だろう。彼は孤児院経営をしたり商売をしたりと、表向きは温厚な商人の部分を持っているからだ。
「“偉大な樹法具”に興味はありませんか」
と、若い詐欺師は彼に持ちかけた。
「実はある樹法研究家が破産しまして、彼は財産の樹法具を手放したがっているんです。できるだけ早く。それで」
「ウチが小金持ちだから話を持って来てみた、と」
「そうです、そうです! もちろんあなたなら樹法具を正当な価格で売り抜ける商才もお持ちでしょう?」
「ま、“ルート”はあるがね」
「商工会とかですか?」
「そんなところだ」
苦笑する。
お前ンとこの元締めだよ。
ソーンの盗賊たちを束ねる裏町組合では、組合員同士の“仕事”はご法度だ。
これを利用して、泥棒避けに裏町組合に会費を支払って加盟している商店も少なくない。いや、目端の利く商人なら、万一とはいえ盗賊にやられて全財産……あるいは命まで持っていかれる可能性を考えれば、年の稼ぎの一割くらいはポンと払う。警邏をしている市民兵に付け届けをするよりも確実だ。
だからこの若い詐欺師がロクに経験を積んでいないことも、もちろん分かる。
親分衆の一人であるブロックマルツのところに“仕事”をしに来るくらいなのだから。
ったく、ちゃんと教えておけよ。
ブロックマルツは、この詐欺師が誰の“子分”なのかも、すでに調べあげていた。
今、こいつが座っている事務所だって、見る者が見ればただの商人の部屋ではないことはわかるはずだ。
壁は頑丈。天井には天窓があるし、窓もあるが、どれも頑丈。閉じ込めることも、ここから逃げるときに閉ざして足止めするにも簡単。簗と同じだ。ここに入り込んだら、者でも物でもそうそう逃げ出せない。部屋は十分な広さがあり、これは中で荒事が行われる可能性を考慮している。盗賊、それこそこの詐欺師の“兄貴”であるメノウなら、こんな造りの部屋を見たなら即座に回れ右をして出ていくだろう。
「で、その樹法具はどういうものなんだい?」
ブロックマルツはつまり、詐欺師との最期の会話を楽しんでいるのだ。
「それは……素晴らしいものですよ」
考えてねェのかよ。
「今、持ってるのかね?」
「今は持っていません。まず半金……三千タレルほど……をお支払いいただいて、それをくだんの樹法研究家に持っていき、それから品物を持ってきますのでその時に残りの半金と、どういうものかの説明を。なに、あなたの役に立たなくても、投資先としては格好だと思いますよ……」
「そうかい」
猫爺はにいっと笑って、詐欺師はうまくいったことを確信して握手のために手を伸ばそうとした。ブロックマルツはそれに応じず、指から爪を出して、振った。
「俺にとっちゃ、メノウの手下のオメエの身柄の方が役に立つなァ」
次の間に控えていたブロックマルツの子分たちがばたばたと飛び出し、詐欺師を押さえつける。
詐欺師は驚いてきょろきょろと首を巡らせる。
「おいおい、ブルってんじゃねぇよ。おめェ、ここがどこだか知らないで来たんだろ? かわいそうになァ。おい、やめろ、あんまりだんびらちらつかせんな。ちびっちまったらどうする。この絨毯は本物だぜ。こいつの樹法具とは違ってな。あぁそうそう。やさしく地下にでも閉じ込めとけ。そいでな、これから手紙を一通書くから、それをあのちびンとこ持ってけ。決まってンだろ。メノウだよ。あいつには借りがあるからな。ここらで返してもらっておこう……」
猫の獣人種はにやにや笑いをたたえたまま、次の葉巻の先を切り飛ばした。
◆◇◆
双子都市ソーンは、プロタ・リズマ王国の中でも最も古い都市である。
建国時にはソーンは王都として栄えていて、新帝国歴890年代に現在の王都プロタ・リズマに遷都された。
それ以後、ソーンは各代の王太子が治める都市として続いている。
つまりこの都市には、千五百年からの歴史があるということだ。
「そしてそれは、千五百年以上前……レグ・シャアの帝国以前から人種が住んでいたということさ」
調毒士にして歴史研究者でもある探索者アーベンは、そう講釈を垂れながらスコップを振るった。
講義の相手は護衛に雇った野伏のルイーズだ。
戦士の心得もあるアーベンの戦いの腕前は彼女に劣るものではないが、発掘に集中できるのは有難い。なにより、独り言を言い続けずに済む。
「フーン」
と、あくまでルイーズの対応は芳しくなかったが。
晩夏の空に、赤いトンボが飛び始めている。
ルイーズはそれをぼんやり眺めながら、もうすぐある豊穣祭に心を遊ばせていた。
ちょっとした地震があり、ソーンから丸一日ほどの街外れで地滑りが発生したのが数日前。
ソーン周辺に古代人の足跡を探しているアーベンは、その地滑りに古い地層を見出しさらにいくつかの遺物を発見していた。
樹力の切れた光石のかけらは、古代に誰かがここにいた証拠だ。
光石は比較的ありふれているとはいえ、現在では貴重になった樹石の一種で、暗闇の中で自分で光ることができる石だ。
その光源としての寿命はさまざまで、現在も光続けているものもあれば、昼間光に当てておかないと夜間には光ってくれないものもある。
長いもの、強いものはそれなりに高価だが、実用品としては、鯨油や石油のランプのほうが安価なぶん便利な場合も多い。
いずれにせよ、古代人の痕跡を発見したアーベンは、こうして準備を整えて発掘にやってきたというわけだ。
「ここは泥炭地だったんだな。沼だったのかも。何か儀式をしていたかもしれない。源樹が健在で生活の多くが源樹とともに成り立っていた古代なら、その尊敬、崇拝もひとしおだろう」
「今のおいらたちが、源樹への信仰を忘れてるってこと? お祈りになら行ってるよ」
「崇め方は変わっているかもしれない。それを紐解く鍵になるかもしれないということだ」
「“かもしれない”ばっかりだね。それって」
ルイーズが首を傾げる。
「面白いの?」
アーベンは渋い顔を上げた。
「面白くないか?」
「あんたの泥だらけの顔を見るのは面白いよ」
「……いいものが出たら金になるぞ」
「へー」
アーベンは肩をすくめた。
ルイーズとの付き合いはこうしてたまに仕事を依頼するくらいだが、それでも長い方だ。いつも食うに困っているくせに、金にいまいち執着しないのが不思議だった。
とはいえ彼が気にするほどの事ではない。
アーベンはスコップを突き立て、足で力を込めた。
どうやら当たりを引いたらしい。
日が落ちるころには、アーベンはいくらかの成果を持って、一度家路についていた。
泥炭地に埋まっていた石板には何か文字が刻まれていて、さらにその地で生活していた人々が投棄したものと思しき生活用品の類を発掘できた。
翠色の石器は、おそらく包丁のように使っていたのではないだろうか。
樹力に溢れていたころ、彼らはほとんどの道具に樹力を併用できたため、金属の鋭い刃は必要ないことが多かった。源樹の根などから削り出した石器などで充分だったのだ。
「例外は伝説のレグ・シャアだな。彼は樹力を検知できなかったと言われている。だから鋼で武器を作った」
「これは何に使っていたの?」
「さて。それを考えるのが楽しいんじゃないか。この泥炭地はゴミ捨て場だったのかもしれない。生活用品が出土した。あるいは墓かも。その石器は石の箱に入っていた。貴重なものだったとしたら、副葬品だったのかもしれない。今でも金持ちが死ぬと棺に金や宝石を収めて埋めることはある。それが墓荒らしの稼ぎになるわけで、くだらん見栄だとは思うがね。だが気持ちはわからないでもないだろう?」
「そうだね。大切な人には素敵なものに囲まれて源樹に行ってほしいってのは、わかるよ」
ルイーズにうなずいて、アーベンは翠色に透き通ったナイフくらいの石器を松明の灯りに透かす。美しい。この美しさを古代人も美しいと感じたなら、ここはゴミ捨て場ではなく墓場だった可能性が高いだろう。しかし古代人が世界をどう見ていたかは、もはや空想するしかない。
「実に興味深いだろう?」
そしてそれをこそ、アーベンは楽しむのだ。
◆◇◆
「もう一枚羽織ってくればよかったなぁ」
休日の赤盾市場を歩くのは、樹石職人スイ・フィラロイトである。
作業用の麻のシャツの上に薄手のマントを羽織って出てきたのだが、晩夏のソーンには早くも秋が訪れようとしていた。
市場には秋の食材が並ぶ。
じゃがいも、かぼちゃ、玉ねぎ、大豆や小豆、りんご、柿。それにチーズやバター。
食材だけではなく、その場のものを使ったような屋台なども盛況だ。
しかしスイは、うまそうな匂いを投げる獣人種カイルの屋台を素通りする。
彼が物色するのは、骨董市などだ。
彼は樹石職人として普段から樹石や宝石に触れている。
どちらも原石のままではそれほど人目を引かないことも多く、そういったものが目の利かない誰かのところにわたると、驚くほどの貴石がこれまた驚くほどの安値で並んでいたりもするのだ。
彼はこれを“発掘”と呼んで、日ごとの楽しみにしていた。
先日買い手がついた光石もそういうルートで手に入れたものだ。古い光石はセメントに塗り込まれたようになっていて、その光をおそらく二千年ほども隠し続けていたのだが、スイの目はそれを見逃さなかった。
ひとしきり奥ゆかしい光を愛でた後、知り合いの人形師が目の部品に使いたいということで彼女に売却することにし、あわせて球体に磨き出し終わったのが先日。
仕事の一段落ついたスイは、巣立っていく石に変わる新たな石を求めて、“発掘”に繰り出した、というわけだ。
もちろん古物商や骨董商に季節は関係ない。
しかし人通りが多くなればそういった季節を問わないものの出入りも多くなるのは常識で、スイはここ数日、何度も赤盾市場を訪れている。
「あれ」
スイはそのうち一件の店頭で足を止めた。
「この山、昨日ありましたっけ?」
「どれだい?」
「これ、この」
「あぁ……」
そこにはまだ値札のついていない、おそらく考古学的に価値(残念ながらスイは石以外は門外漢だ)があるのであろう品物が積まれた小さな山があった。
彼は崩さないように注意しながら、まずはそれを眺める。
「昨日の夕方くらいにボウズが持ってきたんだ。お遣いだって」
「ボウズ?」
「帳面みりゃ名前わかるけどな。スラスラ名前書いてったから、ありゃあどこかの樹法使いか錬金術師あたりの徒弟だろうよ」
名前みるかい? という店主に、スイは首を振って、逆にこの山を崩してもいいですか? と尋ねる。
「いいけど、先生の気に入るものがあるかなぁ。目方で買ったから何があるか分からんぜ。先生が目利きしてくれるんなら助かるね」
「そりゃいいや」
樹石職人は小躍りして、山を一つ一つ崩し始めた。
古い彫像は大きく欠けていて、美術品としての価値は厳しいだろう。だが原石として磨き直すのであれば気にならない。そもそもモチーフからしてなんだかわからないし。
青銅の鈴のようなものは完全な形を保っていたが、スイには価値はわからなかった。
「いてっ!」
山に手を突っ込んだ彼は、指先に熱いものを感じて手をひっこめた。
「どうした?」
「いや、何か……刃物かな」
改めて慎重に山を崩すと、そこから出てきたのは透き通った翠色の宝石だった。
しかもおそらくナイフだろう。打製石器然とした剥離させて作った刃は鋭く、ガラスの破片のよう。
スイはこれに指を触れてしまったのだ。ぷくりと血の玉が現れ、ぽたりと落ちた。店主がびっくりして包帯代わりにボロ布を当てる。商品を汚されてはかなわない。
「うわぁ……」
だが、彼は指の痛みなどどうでもよかった。店主も思わずスイの手元を覗き込んで見ほれる。
「すごいや。これ、樹石ですよ」
「へェ?」
「こんな風に透き通ったのを見るのは珍しいですほら光に透かすと中に金属質の粒が見えるでしょう?これが樹石の特徴なんです翠は珍しいなこれナイフですかねこれで料理したらすごいだろうなぁ!向こうの景色がうっすら透けて見える…ゆらゆらして…綺麗だそう思いませんか?こんなすごいものがガラクタの山に残ってるなんて奇跡なんじゃないかしらんきっとそうですよ」
「お、おぅ……」
早口でまくしたてるスイ・フィラロイトに、店主は半歩後ずさった。
「これ、買います。いくらですか?」
「そうだなぁ……」
店主は腕を組む。
そもそも「全部ガラクタだってさ」と言うから目方で買い取ったのだ。樹石が入っていたとなれば話が違う。あの子供に渡した銀貨では少なすぎるだろう。連絡を取るべきだろうか。あとで駆け込んで来られても困るし……。しかしながら目の前の樹石職人に「売れない」と言ったら……きっと面倒なことになるだろう。
「200タレルくらいでどうだい」
「タレント合金貨でいいですか。帰って取ってきます。17枚で。おつりはいいです」
「うぇ」
吹っ掛けてあきらめてもらうつもりだった店主に、スイは即座に答えた。
ちょうど人形職人ミルシュカに頼まれていた光石の前渡し金がある。大家に家賃の支払いをせかされているが、おそらくあと二ヶ月くらいは引っ張れるだろう。すぐに食うに困ることはない。
「わかった。わかったよ」
店主はさっさと匙を投げた。食い下がるほどではないし、そもそもお互い合意で買い取ったのだ。後で文句を言われたら、このおかしな樹石職人と直接交渉してもらえばいい。
その後数刻の後に、樹石職人スイ・フィラロイトは翠の石器を手にホクホクと家路についたのだった。
◆◇◆
「……みっともないわよ。それ」
人形の目玉につかう光石を受け取りに来た小人種の職人ミルシュカは、店主のスイ・フィラロイトに眉をひそめた。
「え?」
「え? じゃあなくて。その指」
「あぁ……」
スイは苦笑して口にくわえていた人差し指を離す。
「血が止まらなくって」
「血? じゃあ包帯を巻くとか、傷薬を使うとかなさったら?」
「それはやってみたんですよ」
スイはぽたりと落ちる血を手拭いで拭って、また癖になったかのように指をくわえる。
彼の宝石店はそれほど大きくはない。
自宅兼用で、カウンターにして使っている大きな長テーブルには高価な板ガラスがはめ込まれていて、たいそう立派に見える。中にはいくつかの、美しいが比較的価値の低い宝石が展示されていて、壁の棚にはまだカットしていない石が所狭しと並んでいた。
店頭はスイの作業場を兼ねていて、作業机の上には鮫皮のやすりや鹿皮の磨き皮、瓶に入った磨き粉に金やすりなどが並んでいた。
今、ミルシュカの手にあるぼうっと光る二つの球体も、ここで磨かれたものだ。
宝石の飾り棚以外は簡素で、棚木も決していいものではない。ぼろと言ってもいい。店主の力の入れ場所がよくわかる店内である。
「いつからなの?」
「三日くらい前ですね。それより見てくださいよこの樹石のナイフ! きれいだと思いませんか? こうやってランタンに透かすと綺麗でしょう? その光石と一緒に置いてあったんですけど、夜暗くなってからだとなお屈折が美しくて……」
「それは素敵だけれど!」
ミルシュカはいらいらと言う。
「三日も血が止まらないってそんなの変」
「さすがに僕も気になって、薬売りの人にいい薬をもらったりしたんです。知ってます? ルシェンさん」
「あの気味の悪い魔獣を連れてる人でしょう?」
「それ、本人の前では言わないであげてくださいね。それで、傷に兎に角よく効くっていう多肉草の剥いたのをもらってしばらく貼ってたんです」
「効いた?」
「ぜんぜん。朝起きたら布団が血まみれで。まぁ、指のかすり傷だからそんなに湧き水みたいに出るわけじゃあないですけれど……。それにそれを貼ってると利き手の人差し指なんで作業ができなくて」
「なにそれ?!」
スイ・フィラロイトは、彼の翠の石器に夢中になった。
日がな一日眺めるし、どの角度が美しいのか、この石器は誰が作ったのか、そんなことを四六時中考えていた。
だから、この石器を見つけた時についた指先の怪我が一向に治らないのも、あまり気にしてはいなかった。
ルシェンに処方してもらった薬も結局半日で外してしまったし、今も片眼鏡を光らせて、隙あらば石器を眺めようとそわそわしている。
年古る偉大なるゴーレムマスターでもあるミルシュカは、彼の様子があまりに奇妙に感じた。
「その石器、見せて頂いてもよろしい?」
「えぇえぇ、もちろんですとも。見るだけですよ。とりあえずこれは売らないことにしてるんです」
「大丈夫。見るだけよ」
ミルシュカはシルクの手袋をひっかけないよう注意しながら、きらきらした石のナイフを受け取った。
彼女もまた樹石職人であるので目利きはできる。
たしかにその石器は樹石の特徴を備えていた。ひょっとしたらそれ以上かも、と、ミルシュカは疑う。つまり、樹法具ではないか、と思うのだ。
であれば、それは慎重に扱われるべきだ。用途の分からないそれは危険な代物だから。
「ねぇ、ひょっとしてスイ様の指の傷って」
「えぇ。これで切ったんです。すごいでしょう。千年以上も鋭いままなんて!」
顔をしかめるミルシュカ。少なくとも、今のスイ・フィラロイトに慎重さは期待できまい。
さりとて何かやらかしてからでは遅い。
「ちょっとそれを持って一緒に来てくれない? その、ええと、わたくしもその石についてよく知りたいの」
「ややっ。ミルシュカさんもこの石のよさが分かりますか! でも売りませんよ!」
「落ち着いて」
ミルシュカは終始しゃべり続けるスイを引きずるように連れて、双子都市ソーンの街に繰り出したのだった。
◆◇◆
「これは古代の樹法具だなァ」
王立樹法研究院の一室、彼の研究室の机に置かれた翠の石器を頑丈な石綿の手袋でつついた研究員トビア・サンチェスは眼鏡をおでこに押し上げた。
「これをどこで?」
「東の地層だ。地震で地滑りが起きたあたり。泥炭層の中にあった」
研究者アーベンが後ろの方から背伸びするように声を上げる。
「狭い」
「普段はわししかいないもの」
部屋の大きさは概ね4ミル四方と、そもそも決して広くはない。窓は一つ。もともとは兵舎であった建物は頑丈な石造りで、なんならゴーレムが暴れても持ちこたえることができるだろう。
その狭いが堅牢な部屋の中は小さな机と椅子以外は、所せましと用途の分からないがらくたが積み上げられていて足の踏み場を探すのも一苦労。
鬼人種の学者アザミは珍しそうにその一つを取り上げて、トビアにじろりとにらまれた。
「そこらにあるのはまだ研究中の樹法具だ。一応、王女府の財産だからな。壊すと高くつくぞ」
くだんの石器を携えたスイ・フィラロイトを連れたミルシュカがまず向かったのは、シドリア大聖堂だった。
まずは彼の指先の傷を見てもらうのが先だと考えたからで、聖堂にいる小人種の治癒術士ニレル・ナタンを頼ったのだ。いつも症例を集めて研究している彼女ならいろいろな傷を見たことがあるだろう、と、ミルシュカは考えた。
「私で正解だよ」
ニレルは血を流し続けるスイの指を診察して答えた。
「こんな変な傷、カレに見せたら首を落とされかねないなのだね。ホラ、前に……死人が起きる事件があったから、警戒するのも仕方ないのだけど」
「そんな変な傷なんですの?」
「うん。普通、人種や動物種の血は傷を塞ぐ力を持っているのだよ。糊のようにね。そうじゃないと血を失い続けて死んでしまう。でもこの傷から流れる血にはその力が及んでいないようなのだね……失礼」
「いてっ!」
ニレルはスイの手の別の部分に鋭いナイフで小さな傷をつけた。そしてそれを観察する。
「このくらい、普通ならすぐにふさがるはずなのだね。治るのはその後でね……このメスは鋭いし……ほら、ふさがる」
「ははぁ」
「興味深いね。その石器で切った結果がこれというわけだね。なら、その傷を別の傷でえぐってしまえば大丈夫そうだ。このくらいの切り傷で良かったよ。もし手のひらにこれで穴でもあけていたら、手首を落とさなければならなかったかも」
「ええ?!」
さすがのスイも顔色を変える。
「この石はそんなすごい石だったんですね!」
「スイ様……」
「まぁ、すぐにすむよ。さ、手を出すのだよ」
結局痛い思いをして傷口を焼き切られたスイは口をとがらせながらもミルシュカに従って市場を訪れ、石器を持ち込んだ少年を見つけ出した。
言葉巧みにスイを誘導したのは、ミルシュカの年の功であろう。
少年は街外れの学者アーベンの使いで、彼が持ち込んだ“がらくた”にそれがたまたま紛れ込んでいたというのだ。
「知らないよ! おいらそこのを売って報酬にしろって言われたからそうしただけだよ! アーベンの管理が悪いんじゃないか!」
ミルシュカらが訪れた時、アーベンとルイーズの二人はちょうど発掘から帰ってきたところで、事情を聞いたアーベンが部屋(そこはひどくごちゃごちゃしていて、薬草も発掘品も日用品も入り乱れていた。あまり家に戻っていないのだろう)を探すと、確かにあの日地層で発掘した石器がない。
聞いてみると、やはりアーベンが報酬代わりにともっていかせた研究済みのがらくたの中に紛れていたらしい。
「しまったな」
と、アーベンは腕を組む。
「おいら悪くないよ!」
「わかってる。責めちゃいない」
「これは僕が正当な取引で手に入れたものですよ!」
「はいはい」
「ちなみに、いくらで買ったんだ?」
「200タレルです」
「そ、そうか……」
アーベンは石器と同時に出土した石板に描かれた文字を解読しようと考えているが、発掘が一段落するまでは、と、まだ本格的には手を付けていない。
解読すればこれが何かの手掛かりがあるかもしれないが、どうも帝国時代よりも古いものらしく、読み解くには時間がかかりそうだった。
その後、彼らは学者仲間に手掛かりを聞くも特に収穫もなくカフェ・ド・エクスで一息入れたのち、王立樹法研究院で樹法具を専攻しているトビア・サンチェスに行きついたのだった。
真っ先に行くであろう樹法研究院を後回しにしたのは、王女府の紐付きである研究院に行くと石器を取り上げられるのではないかとスイが渋ったからである。
ミルシュカは彼の執着に違和感を感じたが、もともとそうだったかも……とも思い、特には何も言わなかった。
「地層はどのくらい前のものかね」
「正確には……。ただ、一緒に出土した石板にあった文字が帝国時代のものではなかったから、もう少し前だと考えている」
「なるほど。それで、これで切った傷は治らなかったと」
「そうね」
「特に樹文もなく働く樹法具ってあるかな?」
ついてきていた鬼人種の学者アザミが口を挟んだ。彼女はアーベンの知り合いで、鉱石コレクターでもあるため、この石器におおいに興味を示したのだった。
「あるさ。子供がうっかり起動してしまって村一つなくなったことだってある」
「じゃあこれも?」
「それは解らん。単によく切れるナイフなのかもしれない」
「そうだね。外で鹿をさばくときにあるとすごく便利かも。血抜きをするのが楽そうだし」
「古代人にとって、樹法具はそのくらいありふれていたのかもしれんな」
「とんでもない! 鹿をさばくなら鋼のナイフがあるでしょう! これは貸せませんからね!」
「だめかね」
トビアがスイに聞く。
「できれば研究院の予算で買い取らせてほしいんじゃが。千タレルまでなら即金で……」
「ダメです!」
反駁するスイに、ミルシュカとアーベンは顔を見合わせた。
「普段からこうなのか?」
「ここまでじゃないとは思っていたけど、そんなに親しいわけじゃないし……。でも以前の……ほら、生き血を固めた血石があった事件を聞いたときも、欲しかった欲しかったって言ってたから、石絡みだと倫理観飛ぶのかも」
そこは親しみがわくけど、とは口には出さない。目的のために手段を選ばず前に進むのは人種の美点である、と、彼女は考えていた。
「まぁ、飽きるまで持たせておいてもいいかしらね。他に手はないでしょう。きっともっといいものを見つけたらそっちに興味が移りますわ」
「そう願いたいね。私も買い取って研究してみたいが、私じゃあそんな大金は出ないよ」
「おいらのせいだよね……」
「違う。気にするな。そう思ったら今度護衛代を負けてくれ。それで終わりにしよう」
「わかった!」
「じゃあ、僕はこれを持っていていいんですね?!」
目を輝かせるスイに、トビアは肩をすくめて石綿の手袋を彼に渡した。
「飽きたら譲ってくれ。なに、その石は千五百年以上もそのままだったんだ。いまさら一月や一年たったところで、そう困ったことにはならんじゃろうよ。その手袋はプレゼントだ。前渡しだと思ってくれればええよ」
樹石職人スイ・フィラロイトは渡された手袋をはいて石器を手に取り、うっとりとそれを眺めた。
◆◇◆
石造りの部屋は暗い。ソーンの地下にはこの都市が作られたころからの古い遺構がそのまま残っており、下水道を含めて、今ではすべてを把握している者のいない、犯罪者の巣窟となっていた。
その一室で、盗賊メノウは(いつものように)危機に陥っている。
裏町組合という盗賊組織を身一つで乗り切ってきた彼は、立ち回りにはそれなりに自信がある。親分衆の中には彼を疎むものもいるが、逆に彼に目をかけてくれる者もいるのだ。
腕っぷしが重視される犯罪社会において、彼ははしっこいが小柄であり、あいにくと暴力沙汰は苦手だったが、それでも彼はその危機に対する嗅覚と、危機に陥った際の如才ない身の処し方によって、今では裏町組合の“兄貴”の立場を固めていた。
“兄貴”。すなわち、裏社会に新規参入する若い無法者たちに裏社会の法を教え、組合にとって“稼げる”無法者にするのが彼の仕事だ。
これは未来の幹部が必ず通る地位であり、この小男の将来にとって決しておろそかには出来ない仕事であった。
と、言うのも、ここで教えた“子分”たちが、彼が幹部となった時の支持者となるのだ。子飼いの優秀な部下は多いほどいい。
しかしながら“子分”がヘマをした場合、“兄貴”も責任を問われる。これは大きなリスクであるが、飼いならし乗り越えるべき危機でもあった。
「間抜けが」
メノウは周囲に誰もいないことを確認してから悪態をついた。
彼の“子分”である若い男が捕まったのだ。
それが官憲ならまだいい。
“トリッカー”あたりに捕まったのであれば裏から手を回して出してやることもできる。たとえルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオが真面目で任務に熱心だったとしても、最後まで事件を担当することはできない。官憲にも裏町組合の息のかかった者はいるのだ。
だが、その若者は相手が悪かった。
「よりにもよって“猫爺”かよ」
ちいさなランプの灯りがジジ……と、音を立てる。ぼろい木のテーブルの上には羊皮紙が乗っていた。
メノウの“子分”である若い詐欺師が捕まったのは、同じ裏町組合の親分衆の一人、獣人種の“猫爺”ことブロックマルツだ。
もちろん組合員同士の“仕事”はご法度。掟破りは死に繋がる。彼の“兄貴”であるメノウの経歴も無事ではいられない。
だがブロックマルツは狡猾だった。
何も組合員同士の取引までもが禁じられているわけではない。
くだんの若者がブロックマルツに持ちかけた詐欺。つまり、架空の樹法具の売買。これが架空でなくなれば、これは何も問題ないのだ。
ブロックマルツはメノウにこう持ち掛けた。
――この若者の言うとおり、取引がしたいと思っている。
彼の言う樹法具は魅力的だし商材にもなる。ついては是非購入したいので、“偉大な樹法具”を持って来てほしい。
あいにく老齢の身でもあるし、話し相手にも飢えている。この若者の話は面白い。聞けば彼の後見人はキミだということなので、キミに持って来てほしい。
それまで彼は話し相手になってもらう。これは彼も了承済みなので心配いらない。
どんな樹法具かは知らないし、それが何であってもかまわない。素晴らしい樹法具を楽しみにしている――。
メノウの手持ちに素晴らしい樹法具などない。それを見越しての無理難題である。
端金で樹法具を買えるし、そうでなければメノウの首を取れる。
「くそっ!」
メノウは床に唾を吐いた。
これならまだその場で始末してくれた方がマシだった。
だがもしあの若造を見捨てる判断をしたなら、メノウは“子分を見捨てる男”となる。この評判は致命的だ。ブロックマルツはもちろんそれを喧伝するだろう。
メノウに選択肢はない。
あの若い詐欺師のついた嘘を、本当にしてやらねばならないのだ。
「樹法具か……」
持ってるやつから買うか、奪うか。
どちらかしかない。
◆◇◆
「おうい、スイさん、いますかね?」
武具装飾職人ボルブ・ボルドリック・ボロボレイトが、スイ・フィラロイトの宝石店を訪れたのは、その数日後のことであった。
職人街の会合に、スイが顔を出さないのはそう珍しい話ではないが、その場合、多くの場合彼は事前に断りを入れていたはずだったが、先日の会合にはまったく連絡はなかった。
常連の戦士が言うには、ここ数日開店すらしていないという。
「はてな」
と、思ったボルブは、少し太めの身体を揺らし、夕食の誘いでも、と、彼の店を訪れたのだった。
いかさま、スイの店には準備中の札が掛かったままだ。
夕暮れ。徐々に日の落ちる職人街の一角にスイの店を訪ねたボルブは、樫材の飾り気のないドアを叩いた。
「いないんですか?」
どうやら留守のようだ。さて、どこかに出かけたか……。
仕方ない。フクマルさんの食堂で一人で何か食べて帰ろうか、と思い足元に目を落としたボルブは、ドアの隙間から光が漏れているのを見つける。
なんだ居るんじゃないですか、と、ボルブは向き直ってもう一度ドアを叩く。
「スイさん、食事でもどうですか?」
返事はない。
ボルブは急に二つの不安を感じる。
一つは、自分が自分でも知らない間に何かやらかしたのではないか、ということ。
もう一つは、あの柔弱な樹石職人が何か事件にでも巻き込まれているのではないか、ということ。
そう、例えば今、部屋の中で強盗がスイを縛り上げ、宝石を物色しているのかもしれない。
ボルブが引き返して翌朝来てみると、そこには変わり果てた職人仲間の姿が……。
「いやいやいや」
ボルブは苦笑し、ドアノブに手をかけた。
回る。
機械式の錠前は高価だが、扱う品物も高価であるスイの店には、そこそこいいものが据え付けられている。開けられるとしたら、腕のいい盗賊だ。
ボルブは自分の空想にぎくりとする。
手先は器用だが身体は鈍重な彼は、苦労して音を忍んでドアノブを回し、ゆっくりと引いた。
「……はぁぁあ……」
覗き見た室内に、武具装飾職人はがっくりとうなだれ、次に笑い出した。
「なんだ、いたんじゃあないですか。もう、スイさんも人が悪いな……」
見ればスイ・フィラロイトはひとり、作業机にすわってランプの灯りで熱心に何かを手に取り眺めている。どうやら宝石のようだ。
ボルブはおかしくなってくすくすと笑いを漏らす。
まぁ、集中し過ぎて他がおろそかになってしまうことはボルブにも覚えのある話だ。
「……あれ? ボルブさん」
「なんだ今頃気付いたんですか。夕食でもどうですか?」
「え……今なんどきですか?」
みればもともと細身のスイが、なんだかやつれて見える。
「スイさん、ちゃんと食べてます? 昨夜眠りましたか? 目の下、クマすごいですよ……」
「いやぁ、それがこの石器見てくださいよこの中に浮かんでるきらきらした粒子なんですけどねこれ樹法具らしいんですよすごいでしょどうやって動かすのか気になっていろいろやってみてるんですけどねなかなか……」
「まったくもぅ」
ボルブは苦笑して、スイの石綿の手袋をはめた手を取った。
「一休みしましょう。休息しないと頭が回りません。樹法具は専門じゃないでしょう?」
そうして彼の手から翠の石器を取ろうと手を伸ばしたとき、スイは突然立ち上がって石器と後ろ手に隠した。
「わ! 渡しませんよ! これは僕のですから!」
「い、いや、とりませんよ……」
「食事はいいです。ほっといてください。もう少しで何か分かる気がするんです!」
「はぁ……」
ボルブはさすがに奇妙に感じる。
確かに彼の知るスイ・フィラロイトは石に関してはこだわりの強い男だったが、それは早口で説明してくれたり自慢したりする類のこだわりで、独り占めしようというような男ではない。むしろみせびらかしてこっちが感心したら喜ぶようなところがあった。
「ちょっと、大丈夫ですか? 解りましたから落ち着いて下さい」
「大丈夫ですぅ!」
取り付く島もない。
ボルブは友人を残し、退散するほかなかった。
「まだやってらしたの?」
そのことを、ちょうど夕食に出ようと職人街を歩いていた人形職人ミルシュカに話すと、彼女はその可愛らしい顔をしかめた。
ボルブは道に膝をつき、ミルシュカに話を聞く。
「スイ様の翠の石器でしょう? あれ、わたくしも困ってて。原石を買おうと思ってもお店がやってないんですもの」
「へぇ」
聞けばスイはほとんど偶然手に入れたあの未知の樹法具に心を奪われ、すっかりそれに夢中らしい。
「ライラさんのお店の本で読んだことがあるわ。心を乱す樹法具のおはなし。まるで自分の子供のようにその指輪を可愛がって、ついに本当の子供を殺してしまうの」
「おはなしでしょう、そんなの」
「おはなしにはいつも理由があるものよ。エルディカをさまよう王子。南の深海に宮殿を作る万の目と億の耳をもつ物言わぬ乙女。空を飛び国一つ平らげた妖刀。雲の上の天枝に住む巨人……」
「結構夢がある方だったんですね……失礼。ええと、それじゃスイさんはあの樹法具の影響で?」
「そういうこともあるんじゃないかって話」
ミルシュカはふい、と振り返り、所在なさげにアドの金物工房に並んでいるソーン式将棋の駒をつついた。お祭り前の増産だろうか。
「それに、自分がいまそうなってないとも言えないし」
「それじゃあ……その、スイさんの翠の石器の出所に聞いて見ましょうか」
ボルブはそう提案した。いずれにせよ、今日は深夜までスイ・フィラロイトと飲むつもりで出てきたのだ。このまま帰るのも所在ないし、友人のことも心配だ。できることがあるなら一応やっておこう。そう考えたのだ。
「出所っていうと……アーベン様?」
「そのひと。一緒に発掘したものも調べているんでしょうし、何かわかったりしているかも」
◆◇◆
そんな珍しい傷なら、ぜひ見てみたかったものだね。とは、友人の医師ドクトル・ハニイマシューの弁である。
翠の石器がスイの手に渡ったことを知ってから、それを発掘したアーベンは、学者アザミの持つ文献もあわせて、一緒に出土した石板の文字を調べにかかっていた。
現在、プロタ・リズマで使われている帝国公用語は長い時を経ていて変質しているため、初期帝国語を読み下すには十分な資料と知識がいる。
ましてこの石板にあるのはそれよりももっと古い。文法も細部が異なるし、単語もいくつか共通するものがあるだけだ。
鬼人種の錬金術師アザミのもつ記録は、語彙が鉱石に偏っているが、それが今は役に立っている。もしすべてを網羅した資料なら、単語を拾うのももっと大変だったろう。
なんとなく責任を感じるルイーズが、しかしつまらなそうに二人の学者が喧々諤々するのを眺めていた。
「あの石器は、箱に収まっていたんだよねぇ」
「そうだ。地滑りのせいか壊れていたが。石の箱に入っていた。それがこの石板で、石は普通の玄武岩だ」
「このあたりで玄武岩はあまり手に入らないから、きっと大切なものだったんだね」
「そう思う。棺だったのかもしれない。周りにあった生活用品や切れた光石も一緒に埋葬したと考えることもできる生活用品には傷が入っていた」
「棺にしては小さいよ?」
「子供用かも」
「子供の副葬品にナイフを入れるかな」
「それもそうだ……じゃあ、あの石器を収めるためだけに作ったのか? 財宝として?」
「見て。この文字。“飛ぶ”ってある。“礫”とも。礫ってのは石礫のことで、あの石器のこととも考えられないかなぁ」
「ふむ。こっちは否定語だな。“ナニナニしてはいけない”の命令だ。強い言葉だと思う。これは今とは文法が違うからこっちにかかって……“開く”あるいは“解き放つ”か」
「これは象形文字で“人”だと思うよぉ。前に北方の古墳で見た気がする。こっちには太陽の絵があるね」
ルイーズにはちんぷんかんぷんどころではなく、まるで子供のお店屋さんごっこのようにすら見える。やってる当人たちには別の何かが見えていて至って真剣なのだろうが、はたから見るには何をやってるのかさっぱりわからない。
とはいえそこに口を挟むほど、彼女も無粋ではない。
だからルイーズは二人の邪魔をしないように来客の対応をすることにした。
「あぁ、いらっしゃい。ってもおいらの家じゃあないんだけど……ええと、ミルシュカ…さんだったよね。この間、石器の時にいた。そちらは?」
「こんにちは。ボルブ・ボルドリック・ボロボレイトと申します。スイ・フィラロイト氏の友人です。こちらアーベンさんのお宅ですか?」
「あー……」
ルイーズは頭を掻いて、テーブルにどっさり資料を広げているアーベンを指さした。来客の方を見ようともしない。
「あの石器のことですよね。今、家主、ああなんです」
「どいつもこいつも」
「え?」
「いえ、なんでも……」
苦笑するボルブを制して、ミルシュカが背伸びをして言う。
「実は、スイ様の様子がおかしくて。あの樹法具のせいじゃないかって思いまして……きっと調べてらっしゃるんだろうなと思って来たのだけれど……」
「何か分かったかだよね」
「そう」
「だってさ」
ルイーズはアーベンらに声をかけた。
「何か分かった?」
沈黙。
「これだよ」
ルイーズは苦笑して、何か飲む? と二人に椅子を勧めようとしたところで、アーベンが声を上げた。
「不味いんじゃないか?」
「え? お茶が? 知らないよ。キミんちのお茶じゃん……」
「違う。見ろ」
アーベンは机の上に置いた重い石板を指差した。ボルブとミルシュカも(ミルシュカは椅子の上に立って)覗き込む。
「これはあの石器が入っていた箱だ。すでに壊れているが……それに古い文字が書かれていた。まずは“この箱を開けるな”。これはかなり強い言葉で書かれている。古代人があの翠の石器をどういう意図でつくったのかはわからないが……。あれは武器だったらしい。あの石器は石礫のように飛んで人を刺すよう作られたもののようだ」
「何それ怖い」
「ところが、それは古代人の制御を離れた……。原因はわからない。ゴーレムが生まれる前の話だが、ゴーレムの暴走に近いのかもしれない。とにかく、石器は夜な夜な勝手に飛び回り人を殺し、人種の血を求めた。かつてこの地に住んでいた古代人は、これをこの石の箱に収めて沼に沈めたんだ」
「ムー……。じゃあ一緒に沈んでた生活用品は?」
「推測が入るが、生贄を一緒に沈めたんじゃないだろうか。万一目覚めた時、血がそばにあれば石器は街を襲わないだろう、と。彼らのためのせめてもの贈り物だったのではないかと想像するな」
「たっぷりの血を求めるらしいんだよねぇ。多分だけど、血が止まらないのはあれが血を取り込むためにそういう機能を持ってるんじゃないかな。蚊が血を吸う時に血が固まらないように毒を入れるようなものかなぁ」
「じゃあどうして、今スイ様のところにある石器は暴れ出さないんですの?」
「それはわからない。長く放置されていたから休眠状態なのか……何か理由があるのか」
「壊せないんですか?」
「古代人は頑丈な石の箱にこれを閉じ込めるのが精いっぱいだったらしい。あるいは……今のあの樹石職人のように執着してしまって壊すことができなかったのか……。これをもし敵国の都に投げ込めば、そりゃあ便利だろうな」
アーベンは顔を上げ、一同をぐるりと見渡した。
「私は、とんでもないものを掘り出してしまったのかもしれない……」
「確かなの?」
ルイーズがおそるおそる尋ねる。
「まだ推測だ。未解読部分も残っているが……でも読み下せる限りでは、古代人はあの石器をこう呼んでいたようだ」
石板の中央の象形文字を指して、アーベンは言った。
「“人食い刀”と」
◆◇◆
早速情報の売り手が決まりそうで、情報屋ヴェックマンはホクホクと裏町の通りを歩いていた。
古い市街地である裏町の通りは狭い。かしいだ建物が通りに覆いかぶさるように並んでいて、所によってはつっかえ棒で建物を支えていたりもする。ヴェックマンは干してある洗濯物をくぐり、棒を跨いで歩いた。目的地は宵闇の華亭。裏町で営業する酒場のひとつだ。
「待たせましたかね」
建て付けの悪い扉は、開閉すると派手に音を立てる。忍び込むことなど不可能だ。とはいえ店は常に騒がしい。店の客たちは入ってきたヴェックマンを一瞥すると、またすぐにそれぞれの会話に戻った。
漂ってくる紫煙をふーっと吹き散らして、ヴェックマンは目的のテーブルにつくと帽子を取った。
テーブルにはすでに一人の小男が座って、足を投げ出している。
でかく見せているだけだな。と、ヴェックマンは心得ていた。彼とは知り合いでもあるのだ。
「メノウちゃんを待たせるとは、偉くなったじゃねぇの」
小がは不敵に笑って見せると、ヴェックマンは喉の奥で笑い、とんでもない、と答えた。待っていた小男……裏町組合の“兄貴”メノウが足を下ろす。
「仕事の話でしょう? まいど」
「確かな奴を頼むぜ」
「もちろん。隣の奥さんの下着の色から機密情報まで」
「そんなのはいらんよ。話してあったろ」
メノウはぐいっと顔を寄せて声を潜めた。
「ヘッヘ……。樹法具でしょ。手頃なのを知ってるんですよ。チョイと小耳に挟んでね。裏もとってあります。あんたがなんで樹法具を欲しがってるのかは……知らない事にもできますし、知ってることにもできますぜ」
ヴェックマンはそう言って左手を出す。
「わかったよ。抜け目ねぇな。ったく。あのバカにお前の十二分の一も抜け目なさがあったら、今頃こんなことにゃなってなかったろうに……」
メノウはヴェックマンの手に数枚のタレント合金貨を握らせた。
「お前は何も知らない」
「へっへ。わかってやすよ。お察しします……おっと、これはもう知らないんだった。へへ」
彼は受け取った合金貨を数えて上着の隠しに落とすと、もう一段声を潜めた。
「職人街の宝石店で、スイ・フィラロイトって奴の店があるんですがね。そいつが樹法具を手に入れたんですよ。先日ね」
「やべぇ奴じゃねぇだろうな」
「なに、ひょろっとした“うらなり”ですよ。あんただって殴り倒せる……これは失敬。しかも大した護衛もなく、金庫だって置いちゃいない、とてもじゃないけど樹法具の価値が分かってる様子もないんでさぁ。どうもただの宝石と勘違いしてるんじゃないかってくらいで。忍び込めれば難なく盗み出せるでしょうよ」
「どんな樹法具なんだ?」
「そいつはちょっと解らないですねぇ。起動前ってやつだ。よくある話で……。でも、あんたにゃその情報は必要ないでしょ?」
「……まぁな」
メノウは想像する。
ただの樹石職人からなら、樹法具を盗み出すのは簡単だ。
ほとんどの樹法具はきちんと管理されている。そうではなく、ただそこにあるだけなら、かっぱらって猫爺に渡すにはうってつけだろう。その樹石職人には災難だが。
時間はない。
メノウは立ち上がって、さらに一枚、コインをヴェックマンに投げた。
「チップで?」
「いや、違う。ムツラの奴を探してくれ。今夜は新月だ。今夜やる」
◆◇◆
「えぇええええ……」
やってきたアーベンらに、樹石職人スイ・フィラロイトは顔をしかめた。
「だから、それは危険なものなのよ。スイ様」
ミルシュカが人差し指を立てる。
カウンターの上には小さいが重い鉄の箱が乗っている。箱には機械式の頑丈な錠前がついていて、隅には大手工房であるノシュマンの工房のマークが刻まれていた。大急ぎで頑丈に作ってもらった特注品だ。
「なにも取り上げようというんじゃないんです」
ボルブが持ち前の根気強さでスイに語り掛けた。
「普段はこれに入れておきましょう。その石器について、もっとわかるまで」
「でも……」
「大切にしたいのはわかります。でも私は、あなたの身が心配なんです。ここのところ石ばかりで、ろくに食べても眠ってもいないでしょう? ずっとランタンの光で石をみるばかりだったじゃあないですか。友人がそうしていたら心配するのは当然です。スイさんだって、私がそうしていたら心配するでしょう?」
「そりゃあしますよ」
「ね? その箱にとりあえず入れて、虎の鰭亭でちょっといいものでも食べましょう。箱は重いし、錠前も頑丈です。そんじょそこらの盗賊には開けられやしませんよ」
「そんじょそこらじゃなかったら?」
「開きます」
「兎に角!」
ミルシュカがずいっと迫る。
「その石はしまって! わたくしの注文に応じて頂かないと! 光石の目玉、すこし大きさを調整して欲しいの」
「あれ? 大きすぎましたか?」
「注文通りよ。ただ今作ってる眼窩が思ったより小さくて……」
彼女は言葉で気を引きながら、ひょいと翠の石器を取り上げ、鉄の箱に収めた。
がこん、と蓋を閉じ、鍵をかける。アザミが膂力の刺青の力で箱を持ち上げ、テーブルの隅に据え付けた。
「あとで鎖を買ってきて床につなごう。箱ごと持っていかれないように。どうかな?」
「はぁ、ありがとうございます」
アーベンの言葉に、スイが素直にうなずく。
「お代は結構。だがもしよかったら、時々私やアザミさんにも石を見せてくれないかな。すこし……調べたい。慎重に」
「いいですよ。何なら今夜からでも!」
スイは目を輝かせた。
「僕も色々調べていたんです! 石の中に見えていたきらきらしたもの。ちょっと紅いんですよ。あれについてとか……」
「はいはい」
ルイーズが手を叩いて、スイの早口を中断させる。
「ほら、それは後! まずはご飯食べに行こう? アーベンさんのおごりでしょ?」
「私か……」
「他にいないじゃないか。一件落着したんだから、少し息抜きしよ……」
「あ、ご馳走様です。いやぁ、じつはあの石器を買ったら本当にお金がなくて……」
悪びれず言うスイに、思わず笑いが漏れた。
◆◇◆
その明け方のことだった。空が白む数時間前。人がいたなら最も眠りの深いころ。
「俺ぁここで見張ってる。頼むぞ」
黒い布で素早く覆面を作り顔を隠したメノウが路地に止まっていた大八車の影に身を隠すのを、獣人種の盗賊ムツラは肩をすくめて見送った。
しなやかな肢体を革の仕事着に包んだ彼女は、長身を少し伸ばして、これから忍び込む宝石店を観察する。
入り口は正面に一つと裏口が一つ。
窓は二つ。どちらもガラスははまっておらず、今は鎧戸が下りている。
壁は木に漆喰を貼ったもので、屋根は銅張りだ。
煙突が出ているがごく小さいもので、ムツラの頭とウェストはともかく胸と尻は通れそうにない。
メノウの依頼で、この宝石店から翠の宝石でできたナイフとやらを盗み出すよう依頼された彼女は、ついでに他のものも盗んでいいという条件で依頼に乗った。
一人働きは慣れている彼女だったが、通りを見張ってくれる者がいるのはありがたい。
もっといいのは引き込み(スパイとしてあらかじめ入り込んでいて、裏口を開けてくれる仲間の事。大店の丁稚や下働きを誑し込んで引き込みにすることもある)を使うことだが、今回はそこまでは期待できないし、ムツラは“仕事”の人数を増やすことには本来消極的だ。盗賊は裏切りをこそ恐れるべきなのだ。
だから仕事の仲間としてついてきたのがメノウ一人だったのを見て、彼女は彼を少し信用することにした。
「さて」
ムツラは音もなくその宝石店の周囲を回り扉と窓を調べた。
店と住居が一体となっているのだろう。情報によると、店頭のカウンターにあるというから、下手に住居側に手を付けない方がいい。
さっと入ってくだんの石器とやらをいただき、ついでに盗賊心をくすぐるようなきれいな宝石ちゃんがあればいただいていく。
彼女は大胆に、店舗側正面の扉に目を付けた。
窓は閂で、外から外すことは不可能ではないが音が出るかもしれない。粗暴犯ならそれでいいが、彼女には十分な錠前外しの腕前がある。
店舗側の扉には金属製の鍵がかかっている。
ムツラは腰の袋から“みみかき”と呼ばれる先の曲がった針金を数本と油さしを取り出し、解錠をはじめた。
ばねで押されているピンの数は八つ。これは難物だ。
千枚通しを入れて軽く回し、テンションをかける。それから“耳かき”を差し込んで慎重にピンをひとつづつ上げていく……。
まだか、とジェスチャアをするメノウを無視してムツラは気分よく針金を操作し、およそ十分ほどかけてこれを解錠した。
蝶番に油を刺しマントで扉を隠して、そっと中を覗く。
豹の特徴を持つ獣人種であるムツラの目には光は必要ないし、耳もおおかたの広人種よりも鋭い。
生まれながらの盗賊、などと言われるのは心外だが、実際今の生業がこうなのであまり大きなことは言えない。
さて、新月の曇天ではあるものの、用心深くマントで隙間から光が差し込まないよう注意しながら覗き込んだ室内には、数人が床に眠っている。宴会でもやったのだろうか? なら好都合だ。
一人が寝ているところに忍び込むのは難しいが、これが複数人が雑魚寝しているなら話は別。小さな音がしても、寝ている者は「誰かの音だろう」と自己完結してしまうからだ。
ムツラは猫足立ちのまま音もなく室内に滑り込むと、そっと扉を閉める。もしだれかがこの部屋を見ているなら、ムツラの目だけが、金色に輝いて見えるだろう。
「さて、お宝ちゃんは……」
見ればカウンターの脇に、やたらとごつい鉄の箱がある。
カウンターの一部は高価なガラス張りで、中には宝石や原石が。どれも丁寧にカットされていて、石としての価値は高くはないが美しい。これはいくつかいただいていこうかな、と、ムツラは考えた。得るのではなく、自分の美貌をさらに飾るために。
見える範囲には、くだんの翠の石器は見つからない。
「話が違うじゃない」
ムツラは闇の中で口を尖らせた。
たいした金庫もなく裸であるはずだ、と聞いていたのに。もちろんあの箱に入っているのがもっと違うものであることも考えられるが。
「ま、いっか」
ムツラはまず窓の閂を外して複数の退路を確保し、それからノシュマン工房製の錠前にとりかかった。
店頭で眠っていたのは、アーベンとスイ、それにルイーズの三人だった。
アーベンとアザミは食事のあと持ち込んだ資料で石板の解読を進めていたのだが、そのまま眠ってしまったのだ。この点、アーベンはスイを全く責められない。
アザミは家から追加の資料を持ってくる、と、明日の朝にまた来る予定。
ミルシュカとボルブはあきれて家に帰り、宿無しのルイーズは護衛と称して持って帰ってきた残りの揚げ物を薄めた葡萄酒でちびちびやっていたが、彼女も今は寝入っている。つまりムツラが住居部分を避けたことには何の意味もなかったのだが、これは結果論に過ぎない。
かちり、と小さな音を聞いた気がして、アーベンは寝返りを打った。
おおかたリーズが便所にでも起きたのだろう、と思ったのだ。寝るギリギリまで葡萄酒をやっていたのを覚えていたから。
ところがその後に女の驚く声が聞こえて、アーベンは飛び起きた。
「なにこれ!」
聞きなれない女の声で悲鳴が聞こえる。
「誰だ!」
アーベンが誰何の声を上げ、そばで寝ているルイーズを蹴飛ばす。そのアーベンの顔の脇を、何かが高速で飛びすぎ、彼は首をすくめた。
しかし周囲は闇だ。
探索者として闇には慣れているアーベンだったが、別に夜目が効くわけではない。
「くそっ!」
がしゃん、という何かが砕ける音が聞こえる。部屋の中を何かが飛び回っている。心当たりは、一つしかない。
「何、何、なんなの?!」
「誰だか知らんが動くな! いいか、絶対に怪我をするなよ! ええい、明かりを……」
アーベンは窓に飛びつくと鎧戸を上げる。かかっていた閂が外れているが、この際気にしない。星明りを入れようとしたのだ。
窓を開けると、差し込む星明かりが部屋を照らす。闇に慣れた目には眩しいほどだ。
ひゅっ、と空気を切り裂く音が聞こえ、鋭い翠の石礫がアーベンの視界を横切った。
「なにぃ?」
のそのそ起きるルイーズに、アベーンが鋭く叫ぶ。
「寝てろ!」
「起こしたくせにぃ!」
「じゃあ伏せてろ!」
翠の石器は、もはや“人食い刀”の姿を隠さなかった。
ぎらりと輝く石の刃は美しく、アーベンはスイが寝ていることを源樹に感謝した。
「お前も伏せろ!」と、鉄の箱を開けた盗賊女に叫ぶ。「死にたくなかったらな!」
アーベンは傍らにあった箒を手に取る。叩き落して足で踏んで捕まえる。もし可能なら。
一方、路地で店を見張っていたメノウも、店内で騒ぎが起きたことに気付いていた。
「ヘマやったか?」
発見され、騒ぎになった。メノウはそう考えて、まずは逃げることを考える。
だが、くだんの石器はただテーブルに乗っているはずだ。ムツラがそれをひっつかんで逃げてきた時に、もしメノウがいなかったら彼女はそれを自分のものにするだろう。
メノウは一瞬の逡巡の後、ムツラを助けるために店に向かって駆け出した。
なんにせよ、樹法具は確保しなければならない。
室内で何かを破壊する音がする。ムツラの声の他に男の声もするので、発見されたことは間違いない。
窓が殴られるように開いた。ムツラが飛び出してくることを考え、メノウは窓の脇に駆け寄る。
手鏡を出す余裕がなかったので、メノウは覆面をぐっとかぶって店内を覗こうと顔を出した。
「?!」
脇をかすめるように、何か翠のものが窓から外に飛び出した。
「な、なんだぁ?!」
メノウは驚いて尻もちをつく。と、窓から顔を出した男と目が合った。
「……」
「……お前、見覚えがあるな」
以前キノコの洞窟の件で会った、アーベンであった。
◆◇◆
「不味いことになったぞ」
スイの店は、まるで泥棒に荒らされたかのようなありさまだ。実際荒らしたのは泥棒ではなく、お宝のほうだったが。
その中で彼らは、比較的無事だったテーブルを囲んでいる。
スイは石が失われてしょんぼりとし、ルイーズはとにかく落ち着かせるべくお茶を淹れ、アーベンは立ったり座ったりを繰り返している。
メノウとムツラは捕まって監視されているが、別に縛られたり武装解除されたりはしていない。それどころではないのだ。
近所の少年を使いに出したアーベンは、アザミの持ってくる資料を待っている。
「なんだよ、あの石っころは」
メノウが、温かいお茶をすすって毒づいた。
「起動していない樹法具って聞いてたぞ」
「僕の石……」「“人食い刀”だ」
不満げなスイをよそに、アーベンが説明した。
「古代人が制御しきれなかった、人殺しの樹法具と考えている」
「ただの綺麗な石って話だったじゃない」
「知るか。メノウちゃんだってそう聞いてたよ。情報屋に言え。くそっ! とっちめてやる」
「ほんのちょっと前まではそうだったんだよ。ねぇ?」
「あぁ。実際、寝る前までは明かりをつけて調べていたんだ。その時はなんともなかった。なぜあれが暴れ出したのか、皆目見当もつかない」
「僕があれを手に入れてからもう一週間ですよ。その間何もなかったのに、なんで急に……」
アーベンは首をひねる。
スイがずっと人食い刀を眺めていたのは間違いない。それは樹法具の影響であることも考えられる話だ。
アーベンは再び石板に目を落とした。
「暗いな。明かりをくれ」
「はいはい」
ルイーズが窓を開ける。すでに朝になっていた。窓から頭を出したルイーズが、曇ってきたね、と言って振り返ると、アーベンがはっとなって立ち上がっていた。
「明かりだ」
「え? うん、ほら」
「違う。人食い刀の起動条件だ。そうだ。なぜ気付かなかったんだ。一緒に出土したのは切れた光石だった。スイはずっとランタンの灯りをともし続けていた。石板には太陽の象形文字があった」
「……だから?」
ルイーズはきょとんとする。スイは眼鏡を上げた。
「ひょっとして、暗闇? 箱に収めて暗くなったから……動き出したのでは?」
「暗くなったら活動が活発になるなら、昼の間は安全かもしれない。石板には人食い刀は夜な夜な勝手に飛び回り人を殺し、人種の血を求めた……とあった」
「じゃ、ひょっとして僕があの石器を大好きになっちゃってずっとランタンの灯りを当て続けてたのも?」
「古代人があの樹法具にかけた安全装置なのかもしれない」
「こだいじんはちょっとおかしい」
「そうだな」
顔をしかめるルイーズに、アーベンは思わず苦笑する。だから発掘は面白いんだ。
「じゃあよォ」
メノウが椅子を動かしてテーブルの石板を覗き込んだ。
「お前らの話を総合すると、あの石器の樹法具は昼の間は大人しいけど、夜になると飛び回って人を殺すってことか? 今夜?」
「……そうなるな。昼の間にソーンの街のどこかにある人食い刀を探さなくてはならない」
「それ無理でしょ?! ソーンって人口いま何人くらいだっけ?! 十万人くらい?」
「もうちょっといるだろ。豊穣祭を当て込んだ観光客も来はじめてるし……手がかりは? 例えばほら、その石っころがここですよってなにか印を残してるとか」
「……ないな。あるかもしれないが、そもそも飛び出したのを見るのが初めてだ」
石板になにか書いてあるかもしれないが、果たして解読が間に合うかどうか。
「つまり、今夜ソーンは血の海になるってこと?」
ムツラがおそるおそる言って。
そして誰もそれに反論できなかった。
昨晩の飲みすぎで倒れているであろうスイやアーベンを心配して朝食を持ってやってきたボルブとミルシュカは、店の惨状に絶句した。
「なぁにこれ! ミヤマザルでも暴れたの?」
「ノードスの鉤爪にかけて。もしそうならどんなによかったか!」
アザミと石板の解読を進めていたアーベンが、思わず天を仰いだ。解読は進めているが、人食い刀を追跡するすべは見つからないままだ。
話を聞いたボルブは真っ青になる。
「あ、あの、王女府に届けた方が……」
「したよ。した。石板の写しも渡したが、こっちで何もしないわけにはいかないだろう。もしあれが人を殺してみろ。どうなると思う」
「……どうなりますかね」
「私とスイはタダじゃ済まないだろうな」
「あぁ……」
「記録によると」
アザミが石板を指差しながら割り込む。彼女の表情は仮面でわかりにくいが、彼女にしては珍しく冷や汗を流している。それなりに責任を感じてはいるのだろう。
「人食い刀は、人種の血の多いところを襲ったとあるね」
「今人が多いところってどこだ?」
「夜にだろ? 集中してるなら、盛り場じゃないか? 裏町やら百合おばけ通りやら……」
「あとは兵舎。それから……オーリエル学院の寮とかも、一つのところに集中して多いと言えるかしら」
「昼の間にどこにあるかは分からないの?」
「あの小さい石器だぞ。子供がうっかり拾ってなければ、この街のどこにあるかなんてわからないだろうな」
「ねぇ、新聞に公告を打ったらどう? 拾った人がいるかもしれない。拾ったら明かりを絶やさないようにして持ってきてもらうとか……」
「それはいい考えだ、ルイーズ。ピリアネータ新聞に公告を打とう」
「高いんじゃないの?」
「どうせユピテルさんなら、いつも誌面を埋めるのに困ってるから大丈夫だと思いますよ」
「よし、今文章を作るから、それを持って赤盾市場まで走ってくれ」
血の海になるのを避けられるならなんでもするよ、と、アーベンはペンを取り、ミルシュカが持ってきたパンに手を伸ばした。焼き立てのパンはエミリーの店のもので、これが夜には血に染まるというのだけはなんとか避けなければならない。
一方、奇妙に巻き込まれた形になったメノウも、頭をフル回転させる。
彼の苦境は何ら変わっていない。
なんならそのナントカという樹法具がいっそ暴れてくれれば、どさくさに紛れて捕まっている“子分”を助け出すチャンスが生まれるかもしれない、と考えるくらいだ。ソーンが血の海になるのを避けたとして、樹法具はいずれにせよ彼の手には入らず、そうなれば猫爺に渡すものは何もなくなる。メノウはこんなところとっとと抜け出して別の樹法具を狙うべきだったが、なんとはなしにこの場所に残っている。
こういう経験は前にもあって、そういう時、盗賊メノウちゃんはだいたいいいアイデアを思いついてその場を切り抜ける逆転の一手を繰り出すことができたのだ。何か見落としてやいないか? 彼は考える。
別にソーンが血の海になってもいいが(そりゃあならないに越したことはない)、なんとか彼の目的とアーベンらの目的を両立させ、全員が納得できる案は……。
「血の海か……」
メノウは口の中でつぶやいて、それから全員を上目遣いに見まわしで、言った。
「メノウちゃんは門外漢だからなんとも言えないが、ひとつ思いついたぜ。いくつか条件があるが……。聞くかい……?」
◆◇◆
曇天の夕刻、獣人種の“親分”ブロックマルツは憮然とした。
「なんだ、こりゃあ」
彼の事務所のテーブルには、鈍く光る紅い石が大量に積み上げられている。
以前にソーンを騒がせた“紅飯綱事件”の副産物だ。ある女が、人種の血を抜き見事な宝石にするという樹法具を使って起こした事件で、“あたたかの家”という貧民救済のお助け所を隠れ蓑として浮浪者や孤児を大量に集め、その血を宝石としてソーンに流通させていた。番犬ガルム・ウォレスらの活躍で事件が解決された後、そのほとんどの石は回収され、軍事拠点に保管されていた。スイ・フィラロイトにとっても、そしてブロックマルツにとっても、知らない事件ではない。
ブロックマルツは不快げに体をゆすった。
「メノウよ。俺がこんなもんを見せられて喜ぶとでも思ったのかい?」
「思っちゃいないさ。約束通り、あんたに俺の“子分”が約束した樹法具を渡す。これはその……準備だ」
「準備ねぇ……じゃぁ、そいつらもか?」
「あぁ」
数日前の“子分”と同様に椅子に座るメノウの後ろには、アーベン、アザミ、ルイーズ、それにスイ・フィラロイトが、場違いな感じで立っていた。みんな手に短い棒を持ち、棒の先にはアーベンが練った特別なトリモチをつけている。アザミだけは両手に重そうな鉄の箱を抱えていた。持ち上げるのも一苦労だろうが、彼女は汗ひとつかいていない。
「そのトリモチを部屋の絨毯に付けるんじゃねぇぞ」
「もちろん」
メノウは堂々と言った。
「いいかい旦那。これからあんたに樹法具を見せる。ただそいつはちょっと……じゃじゃ馬でね。あんたはこいつらにきっと感謝することになるだろう。どんな樹法具でも構わない、って言ってたよな?」
「あぁ。あるなら」
「あるさ。それからあんたに、その樹法具を渡す。あんたが樹法具をどうするかは、あんたの自由だ。メノウちゃんはあのバカな“子分”を連れて退散する……。それでいいな?」
「いいさ」
ブロックマルツには自信がある。
メノウが何をしようが、ここは彼の事務所の中だ。次の間には荒事の得意な手下も控えている。
猫が獲物をなぶるように、ブロックマルツは小男のメノウをねめつけた。
やれるだけやってみりゃいいさ。
アーベンは、もはやこの作戦に乗るしかなかったのだが、部屋を見るなり案外悪い作戦ではないかも、という気がしていた。
“紅飯綱事件”の血石を積み上げたのは、メノウの発案だった。
人食い刀が本当に血を求めるのなら、おそらくこの部屋には、今ソーンで一番血があふれているに違いない。
スイの解説によると、この小さな石一つで人種一人分らしいから、兵舎で詰めている兵士の数よりも多い。
アーベンは“紅飯綱事件”の恐ろしさに戦慄したが、だがそれのおかげで人食い刀の被害が防げるのならば、その不思議な源樹の導きに感謝するほかなかった。
メノウの作戦はこうだ。
このブロックマルツの事務所に血石を積み上げ、人食い刀をおびきよせる。これはアーベンとアザミの解読を信じるほかない。
そして飛んできた人食い刀が血石に喰いついたところを、トリモチで捕まえ、鉄箱に収めてしまう。
人食い刀が飛び出したのは、ムツラが箱を開けたからだ。しっかり閉じ込めてしまえば、少なくともしばらくは大丈夫だろう。さらに箱にはいくつか細工をしてある。
箱に入った人食い刀を、少なくとも一旦ブロックマルツに渡す。それがメノウの出した条件だった。
「その後で、あんたが説得すりゃあいい。目の前で暴れるのをみれば、猫爺だって話を聞くさ」と、メノウは言った。
血石を盗み出したのはムツラだ。王女府に願い出れば借りだすこともできるだろうが時間がかかるし、なによりそれをしたなら樹法具はブロックマルツに渡らない。
人食い刀に切られれば治らない傷がつく。せめてブロックマルツらに作戦を伝えるべきではあるのだが、もしそうすればそもそもメノウの作戦が成り立たない。アーベンらは、彼らを守りながら人食い刀を捕まえる必要があるのだ。
よだれでもたらさんかという顔で血石を見ているスイをこっそりと足でつついて、アーベンは開け放たれた窓に視線を移した。
窓は小さいが、複数ある。そして鉄の補強の入った鎧戸は頑丈だ。
もし飛び込んできたなら、まずは窓を閉ざさなければ……。
もちろんメノウは気が気ではない。
彼の作戦はすべてアーベンとアザミの解読の上に成り立っている。
もし彼らがぽんこつで解読が間違っていて、血の多いところではなくそれこそ適当な場所を樹法具が襲うのなら……ソーンは血の海となり、彼らは待ちぼうけで、ブロックマルツはメノウをこの部屋から出すことはないだろう。
頼むぞ、と、メノウは人食い刀とかいう樹法具に祈る。
その時!
窓から何かが鋭い風切り音と共に飛び込んできた。
「来たぞ!」
メノウが叫ぶ。
積み上げられた血石に何かが突っ込んで宝石が飛び散る。
スイとルイーズがブロックマルツを蹴倒しながら窓に飛びついてこれを閉ざし、アーベンがトリモチを短槍のように突き出した。
「な、なんだ?!」
ルイーズに踏まれたブロックマルツが椅子から転げ落ちながら叫んで、メノウは安堵の叫びをあげた。
「人食い刀だ!」
◆◇◆
「わたくしの人形が完成しなくなっちゃいましたわ」
人形職人ミルシュカは可愛らしく口を尖らせた。
街外れの沼に船を浮かべ、アザミが竿でその船を操っている。
秋口の風は穏やかに流れ、空にはうろこ雲が天枝との間に漂っていた。
アザミの操る小舟にはルイーズとミルシュカのほか、鉄の箱が乗っており、もう一艘のボルブ・ボルドリック・ボロボレイトの操る船には、万一のためにトリモチと網を抱えたアーベンとスイが乗り組んでいる。
鉄の箱は前より一回り大きい。鉄の外側を青銅で囲んであるのだ。
盗賊メノウの作戦はこれ以上なく上手く行った。
ブロックマルツの事務所はめちゃめちゃになりあちこちトリモチだらけにはなったが、くだんの“人食い刀”は無事取り押さえられた。
石器は素早くアザミの持っていた箱に収められ、そこに穿たれた小窓から、ミルシュカがもともとスイに注文してあった人形の目のための光石を入れる。しばらくはこの中で暴れていた人食い刀は、やがて大人しくなった。
持っていた杭をぶちこんで小窓を閉ざしたアーベンは、箱を前にしてブロックマルツに言う。
「さて。この樹法具はあんたの物のわけだが……この……危険で取り返しがつかず、もし暴れ出したらソーンを血の海にする……そしてそうなったら誰もあんたを許さないであろうこの樹法具は……あんたの物になったわけだが……私はこれを正しい知識で引き取る用意がある……」
「くそったれ!」
ブロックマルツはトリモチのついた毛を引っ張って叫んだ。
「わかったよ! それも、あの“子分”も持って消えろ! とんだ厄介ものだぜ! あぁ、くそ! おいメノウ! あの若造をよく躾ておけよ! 次はやったら命はないと思えってな!」
血石はいくつかが足りなくなっていたが、ムツラの手で再び軍事拠点に戻された。
“人食い刀”は、王立樹法研究院のトビア・サンチェスの口利きもあって、アーベンたちの主導で、今ここにある。
「軍のエライさんに持たせとくと、誰ぞ“あくどいこと”を考えないとも限らんしな。ないほうがいいんじゃよ」とは、トビアの弁。
ソーンから丸一日ほどの場所にある湿原には、いくつか“底なし”と言われる場所がある。
もちろん本当に底がないかは確かめた者がいないのでわからないが、すくなくとも、上がってきたものはない。
「結局、古代人のやり方が正しかったわけね」
ルイーズは、空を見上げて呟いた。
「なに、学習してるさ」
と、アーベン。
箱の外装には、帝国公用語で事細かに“人食い刀”のあらましや取り扱いが刻まれている。もっとも、遠い未来にこれを発掘した者が帝国公用語が読めるかどうかはわからないが、出来る限りのことはしておくべきだろう。
「石マニアには見せるなって書いた?」
それを見たミルシュカは、皮肉っぽく言ったものだった。
「よいしょ」
アザミが両肩の膂力の刺青を使い、箱を持ち上げる。船がぐらりと揺れて、ルイーズとミルシュカはへりにしがみついた。
「気を付けてよ! ここ、底なしなんでしょ?」
「ごめんごめん」
アザミが苦笑し、箱を沼の中ほどに放り投げた。
重い箱は、すぐに茶色い泥の中に沈み、そのまま見えなくなる。
「あぁ、僕の石……」
「勘弁してくださいよスイさん……」
スイとボルブを脇に、アーベンはようやく万一のためのトリモチを沼に投げ落とした。なるほど、ひょっとしたら古代人もこんな気分で生活用品を投げ込んだのかもしれない。
樹法具、樹石。
これらは偉大で貴重な品物である。
そして同時に、極めて危険で……それから。
「実に興味深い」
アーベンは、秋の空にため息をついた。
Novel.hirabenereo
Tweet Follow @twoq_jp