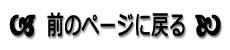●百合おばけ通りの新人
色街・百合おばけ通りのスカーレットの娼館へ、裏町の重鎮ブロックマルツから一人の少女がやってきた。
そんな少女のためにスカーレットは仕事を用意したりと、指導の準備を整えていこうとするが、少女は……
【登場人物】
・スカーレット
・ブロックマルツ
・ドロイ・トピアス
・ザクロ
・ジャン・ジルベルト
・ヨキ
・ヴォル
・ヴァリュー
・ニレル・ナタン
・シャロン
・アステール
・ルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオ
・グルーヴィー・ハイブランダー
・ユピテル
窓のない薄暗い部屋で、猫の獣人種である裏町の大物ブロックマルツと娼館経営者のスカーレットが向かい合って座っている。
上品にソファへ腰掛けるスカーレットはブロックマルツの表情とテーブルに並んだ書類を交互に確認してから、顎に手を当てた。些細な挙動一つとっても妖艶さがにじみ出ている。
まるで本当に娼館の主のようだ。しかし実際にはもっと仄暗い正体が彼女にはある。
東方から流れてきた元奴隷である彼女は、実のところ密輸品や表向きに存在できない薬や道具を商う商人でもあるのだ。
しかしスカーレットはそれを微塵も感じさせない態度で手元にあった水を一口含む。白い肌がまるで蛭のように滑らかに嚥下をする。
「それで、これのお守りを私に引き受けろということですか?」
スカーレットはブロックマルツに気を使っているのか敬語だ。その様子にぴくりと反応したブロックマルツは、静かに傲岸な態度を解いた。背もたれに預けていた身体を伸ばす。
「もちろん報酬は払います」
「官憲から目をつけられるような不利益はこちらが支払うことになりますが、その点についてはどうお考えですか」
スカーレットはブロックマルツを信用していない。
この懸念は必ずしもはったりというわけではない。
と、いうのも、たまに店へ顔を出す地元の大工の一人が、治安維持を担う王国軍騎士の一人、ルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオの御用聞きであることを、もちろん海千山千の彼女は知っているからだ。
ブロックマルツとて知らない事情ではなかろう。十分理解した上で、すぐに次の手を打った。
手元の水を飲み干したのだ。
この場所はスカーレットが用意したもので、この水も彼女なら細工ができる。本来の仕事から考えれば、スカーレットにとっては造作も無いだろう。それを理解しつつ、あえてブロックマルツは水を飲んだのだ。スカーレットを信用している何よりの証。会話で不要な波風を立てない老成された態度。
そのうえブロックマルツは畳み掛けるように言葉を重ねた。
「今の料金で不服なら支払い額を増やすことも検討しますよ」
「では一応この額面はリスク込みの値段なんですね?」
そうです、とブロックマルツが頷く。
「でもなぜこんなことを? わざわざこんなところに預けなくても、十分に引き取り手は見つかるでしょう?」
スカーレットはリスクの詳細を探った。
それも見越したかのようにブロックマルツは筋立てて、説明をする。
「最近、親がいなくなって手に入れた子なんですがね、実は買い手が見つからないんですよ。それもまあ東征の影響だって噂でしてね。そこで人攫いがずいぶん横行したみたいで、ある程度の需要は満たされてるみたいなんです。まあ、そういう趣味の人たちは消耗が激しいのでさっさと代替品を買うことになるでしょうから、待てばいいんですがね。ただ、これがあまり教育されていないものでして、私の手元に置いていても腐らせるだけかと。それでその手のプロかなと見込んでスカーレットさんに頼みに来たわけです」
買い手がつくのを待つ間、スカーレットのところへ身元を預けて教育してもらうというわけだ。
ただそれを無料で頼むには虫が良すぎるというものだ。いずれ引き取られるわけだからスカーレットも無料では身が入らないだろう。ということで、ブロックマルツは金を払ってスカーレットのところで働かせてもらうよう頼んでいるのだった。
猫爺の仏心か。と、スカーレットは思う。
この哀れな娘にブロックマルツがどういう思いを抱いたかは、彼女にはわからない。単に商品価値を上げるためかもしれない。いずれにせよ、つまりはこの娘の教育費をブロックマルツが持つ、という契約である。
幸運な娘だ。この娘からすれば納得いかないだろうが。
手に入れた知識や技術は誰にも奪われない。スカーレットのそれように。ならせいぜい教育してやろうではないか。ブロックマルツの思うようには育たないかもしれないが、そんなことは知ったことではない。
スカーレットは書類の額面を睨んで首を縦に振った。
「ではその商品、こちらで預からせていただきます」
ブロックマルツは太い指を鼻頭に当てて、口角をあげた。本心で笑っているのかは誰にも分からない。
「いえいえ、これは商品ではないでしょう? この都市には奴隷制度などない。身元を預かっていただくだけです」
テーブルの書類の一枚は雇用契約書だ。スカーレットの経営する娼館で働く旨が記されており、契約年数は三年となっている。
もう一枚はブロックマルツからスカーレットへの金銭授受に関する書類だった。先程の雇用契約書に書いてある額面とは桁が違う。
そして二人の横には痩せ細った女の子、シビル・ハーコートがちょこんと座っていた。
**
それから数日が経った。スカーレットはシビルに娼館での生活のために準備を整えてやりつつも、娼館の仕事ばかりに精を出すわけにもいかないので、シビルに付きっきりではなかった。
しかし今日は流石にスカーレットも店で待っていた。重要な荷物が届くのだ。
スカーレットは店の扉が音を立てて開いたのを察して、カウンターから出た。
「お疲れ様です、荷物です」
「あら、ドロイじゃない。待っていたよ。早かったねぇ」
「いえいえ」
新進気鋭の裁縫職人であるドロイ・トピアスはカツカツと硬質な足音を響かせながらスカーレットに近づき、服の入った袋を差し出す。そこまで重い荷物ではないが、スカーレットは丁寧に両手で持つ。
「とりあえず上がるといい」
ドロイを招いて奥の事務室につれていく。テーブルへ荷物を置いて、少し待ってもらうよう言った。そして従業員の一人へ声をかけてシビルを呼ぶよう頼み、服の代金を持って部屋に戻った。
「じゃあこれが今回の分だ。間違ってたら言っておくれ」
ドロイは目礼して包みに入った報酬を数える。テーブルに出した銀貨を何度か数え上げてから、落ち着いた態度で顔をスカーレットへ振り向けた。
「あの、これちょっと多いんですけど……」
「正直でいいね、でも気にしなくていい。ここまで持ってきてくれたおまけだよ」
「あ、ありがとうございます」
外から扉をノックする音が聞こえた。
「いいわよ」
「失礼します」
おずおずと入ってきたのは質素なシャツ一枚に生地の伸びたズボンを履いたシビルだった。一見貧相に見えるが、数日同じものを着ているという様子はない。シャツの袖口や襟ぐりに穴もなく、だいぶまともな服装だった。
つい先日まで客商売なんてしたことのない少女だ。とりあえず仕事をさせながら、貴族の家で働けるような使用人としてある程度の技能を身につけさせようということで、そんな彼女が店で動ける服装をドロイが用意したというわけだ。
「この子にぴったりだと良いんだけど」
既に採寸の際に一度シビルと会っているドロイは特に驚いた様子も見せずに、服を見た。
「もし入らなかったら困るでしょうし、一回着てみては?」
スカーレットは頷いて、シビルに服を着るよう言った。
するとシビルはその場でシャツに手をかけた。
「うわあっ……!」
普段は冷静なドロイもこれには驚いて、思わず仰け反った。上半身のバランスが崩れて、相反するように滑らかに動いた下半身の義足が身体を支える。滑るようにして転ばないように姿勢を直したドロイがいい匂いのする柔らかい感触に突っ込んだ。
「あらあら、悪いね」
「っ! す、すいません!」
勢い余ったドロイはスカーレットの胸に頭から突っ込んだが、スカーレットが寸前でドロイの肩を掴んで支える。
動揺したドロイは、ずれた眼鏡を直しながら、慌てて部屋を出ようとした。
そんな二人が視界に入っていない様子のシビルだったが、スカーレットに静かに止められる。
「年頃の女の子がはしたないじゃない。着替えるなら部屋を移るべきだよ」
シビルは上目遣いにスカーレットを見て、シャツを戻す。
「すいません」
その声に覇気はなかった。
それから別室へ移動した。今日仕事の入っていない娼婦たちが野次馬にやってきた。スカーレットが何を言うでもなく、新しい衣装の物珍しさに釣られたのだ。ドロイの仕立てる服は注目を集めやすい。
我先にと手伝いたがる娼婦たちにされるがままに棒立ちのシビルはあっという間に着替えを済ませて、部屋へ戻ってきた。
緋色の生地に、金の装飾が施されたドレス。大きく開いた背中は白い肌が見えている。装飾品を他に身につけなくても様になるよう作られたものだから、着て髪をアップにしただけで十分服の魅力が際立っていた。
「サイズは合ってるみたいですね、良かったです」
そう言ってドロイは事務室を出た。スカーレットは少し後ろをついていきながら、
「せっかくお金があるんだし、遊んでいかないかい? うちは飯もそれなりのものを出してるつもりだよ」
ドロイは振り返って、少しだけ店を見渡してみる。
カウンターの横では簡易的な仕切りが立てられており、そこに何人かがいた。
「あれは?」
「今日は出張マッサージが来てるんだ。試してみるかい?」
出張ということで専門の人が来ている。ドロイのようないかがわしいのが苦手でも問題ない、という意味で少し仕切りの向こうを覗かせてやる。
今日来ているのはラ・メル・ソーンの近くでマッサージ店を経営しているザクロだ。質は良いが店を一人で回しているということもあってそこまで儲けているわけではなさそうだった。
クリーンな仕事をしている人物を定期的に招くことで、この娼館自体も怪しいものではないとアピールしていた。スカーレットは娼館共々、官憲に疑われているのだ。疑いを晴らすためには真っ白な根拠を示すべきだが、それはできない。なぜならスカーレットは全く真っ白などではないからだ。
少しずつクリーンさをアピールしていく他に対処方法はなかった。
ちょうどザクロのマッサージで客が寝ている。適度な指圧が身体をリラックスさせて、疲れていることを否応なく自覚させる。施術用のベッドでうつ伏せになっているジャン・ジルベルトは疲れ切っている男だった。
ドロイは少しだけ様子を覗いたが、あまりそそられなかったようだ。
「いや、今日はマッサージって気分じゃないんで」
「あらそう。じゃあご飯は? せっかくだし少しおまけするよ」
そんなに大きくない仕切りによってテーブルごとに別れている店内は、様々な客がいた。
ドロイが仕立てたドレスよりずっと大胆なドレスを着た女性が、男の横に座ってお酌をしている。ひと目見て高いと分かる透明度の高い酒をグラスに並々と注がれた人の良さそうな貴族風の男は向かいに座る男と乾杯して、一気に飲み干した。相手の男――ヴォルのほうはほとんど女にも酒にも興味が無いのか、ひたすらテーブルに並んだ食事に手を出していた。柔らかそうな魚の煮込みをガツガツと頬張っている様子が伺える。
また別のテーブルでは団体の客が大騒ぎしている。大皿がいくつもテーブルに並んでいるが、ハイペースで消費されているのが伺える。女を相手にぐいぐいと盛り上がって話をしているせいで端っこにいる男――シャロンは肩身が狭そうだった。おおかた無理やり連れてこられたのだろう。それでも必死に皿をつついて揚げ物を口にしている辺りに飯の評判の良さが垣間見える。
ドロイはずいぶん悩んでいたようだったが、それでも結局は首を縦に振らなかった。
「家で待ってるのがいるので、一人で食べるのはちょっと」
「じゃあ弁当にしてあげる。待ってるのは一人かい?」
流石にこれ以上断るのは失礼かとドロイは感じて、ええ、と短く頷いた。
スカーレットが店員の一人に指示を出して、すぐに弁当が二つ分でてくる。ドロイが少し弁当に反応した。まだ包まれていない弁当の中身にはニンジンが入っていた。思わず顔をしかめそうになったが、ここは客先だ。表情には出さずに我慢した。いざとなれば姉――レビィア・トピアスに食べてもらえばいい。
受け取った弁当をドロイは両手で抱え、スカーレットたちに見送られる。
「ドロイくん今度は私につくってねー」
「ダメよ、次はわたしが予約ー」
さっきシビルの着替えを手伝っていた娼婦たちが次々に見送りに来る。ドロイは落ち着いた表情で会釈だけで済ませて店を後にした。
見送ったスカーレットは、ドロイの姿が見えなくなるまで店前に立っていたが、見えなくなるとすぐさま中へ戻った。
ここからが大変だ。
スカーレットが振り返ると、シビルが床をじっと見つめて突っ立っていた。
「じゃあ仕事しようかね。問題はなにかあるかい?」
「いえ、特にないです……」
シビルは俯いて言った。
スカーレットは目線を彼女に合わせて腰を下ろす。
「返事するときは元気よく、相手の目を見て。まあ忙しいときに見るのは難しいかもしれないけどねえ。だけど、元気はいつでも大事だよ」
「は、はい」
「もっと声出して!」
「はい!」
幼いがよく伸びる、いい具合の声だった。
まずはシビルをフロアに出しつつ、料理を運ぶのを手伝わせた。
意外と力持ちなのか、両手に皿をいっぱい抱えてもそつなくこなしている。小さいながらテキパキと動いていた。
「よくやるねえ。もしかして経験があったりするのかい?」
シビルはふるふると首を横に振った。
「家が農家だったので手伝ってたんです」
なるほどねえ、とスカーレットは頷いた。
「じゃあ他のもやってみようかね」
スカーレットはシビルへ次の仕事を頼んだ。配膳をしてその後注文を聞く。読み書きができないので、覚えて来るだけだ。いずれ読み書きも学ぶ必要があるだろう。少し雑談が入るかもしれないが、あんまり深く考えずに相手を否定する強い語調だけ避けて話してみて、と伝えた。
シビルは難なく大皿を二つ持って、奥の個室へ入っていく。スカーレットもさり気なく後ろへついて部屋へ入る。
窓がない代わりにランプではなく樹法で明かりがついている。熱くもならない光源が、天井から吊るされたガラス細工で複雑に光を屈折させ、部屋全体がきらびやかな雰囲気を漂わせていた。
一番奥に座った神経質そうな細い男は二、三人の連れがだらしなく女たちにもたれ掛かっているのを見ながら、淡々と食事をしている。なみなみと注がれた酒もすぐに飲み干すほど健啖家だった。常連だし、上客である。
「これはそこに置いてくれ」
食べ終わった皿を端に避けようとするのをさり気なく店の子に取って代わられながらも動じることはない。
シビルは丁寧に皿をテーブルへ置いて、空いた皿を重ねていると、男がまた口を開いた。
「あと酒の追加を頼む。頼んでも大丈夫だよな?」
「あ、はい」
男はそっとスカーレットを見るが、にっこり微笑むに留めた。シビルに頑張ってもらわなければ困る。
だが想定外なことが一つあった。
「……!」
シビルが空いた皿を手にしたところで息をのむ。動きが止まる。瞬きを繰り返し、動悸が激しくなっている。
男のボディガード、ヨキがジロリとシビルを見ていた。
尻尾も耳も髪もボリュームがある。だが入念に手入れされており、隙はなかった。彼女の顧客の品位に相応しい格好だ。
二本の斧を腰に提げており、一部の隙もなく部屋全体を注意深く見ている。肩幅ほど開いた足には力が入っているのか入っていないか窺い知ることはできず、次の瞬間部屋の端から端まで一歩で飛んでいけそうな軽やかさと、後一年でもこうして立ち続けていられるのではないかという落ち着きが同居していた。
何も睨んではいないにも関わらず、目が合った者すべてが怯えるような瞳には、何者も人とは思っていないような冷徹さが籠もっている。
緩く垂らした手はいつでも斧を握れるような位置にあり、次の瞬間何かが襲ってきたらすぐさま首を刎ねてしまえるような緊迫感が漂っていた。
そのあまりにも静かな気迫に、シビルは思わず気圧される。
「……おい、もっとにこやかにしていろ。その子が怯えているじゃないか」
奥の男が嗜めるが、ヨキはただ手を後ろに回しただけだった。それで斧を握る気はないという意思表示なのだろうが、シビルに伝わるはずもない。
表情の読めない恐ろしい存在にシビルは思わず尻もちをついて、持っていた皿を床へぶちまける。カーペットに落ちた皿は割れることこそなかったが大失態だった。
前に出たスカーレットが一も二もなく頭を下げる。
「大変申し訳ありません、すぐに片付けます」
男の鷹揚な許しを得てスカーレットは皿を片付けた。
それからシビルは仕事を任されることが少なくなった。
シビルの怯えは両親のいなくなった原因に由来するからだ。
元の家では毎日借金の取り立てが激しく、武装した連中が家で物を奪ったり壊したりするのは日常茶飯事だった。そしてその末路として両親は死に、シビルは売られることになる。
シビルが暴力の影に怯えるのは当然だった。
それを無理に仕事へ出しても、ヘマをして余計にトラウマになるだけだ。スカーレットはまず最初に今の環境に慣れさせるべきだと判断し、あまり外向きの仕事をさせず、館内での手伝いに専念させることにした。
そうしてしばらくが過ぎた。
**
日が落ちてすっかり夜が更けている。
獣人種の薬剤師ヴァリューは遅めの夕飯終わりの一杯を飲もうとカフェ・ド・エクスに入ったところでいつものように飄々とした樹法研究院の問題児アステールに捕まった。
「どうした? 俺の休憩を邪魔するなんて」
「ちょっと来てもらっていい? 薬売ってほしいんだ。暇だろ?」
ヴァリューはため息をついて頷いた。こんな風に傍若無人な頼み方をしてくるのはアステールくらいのものである。
「大丈夫だろうな? 変な事件には絡まれたくないんだが」
「そんなんじゃないさ。さ、行こ」
そう言うとアステールは俺の腰をぐっと掴んだ。それから素早く樹言を唱えてくるりと俺に蔦を絡ませ、固定する。
「歯を食いしばって!」
なんで、と聞く前に視界が地面から飛んだ。
「うわああああ!」
叫び声が風にかき消された。
「食い逃げ?! この犯罪者! 捕まえてガルムさんに突き出して……」
というカフェ・ド・エクスの用心棒グルーヴィー・ハイブランダーの声も最後までは聞き取れないし、もちろん弁解もできない。
はためいた風に乗っかるようにして二人の身体が浮き上がり、放物線を描いて街中を飛ぶ。頂点に来たところでまた浮力がかかり、上へ上へと飛んでいく。まるで見えない階段を登っていくボールみたいな軌道で二人は街を横断した。
たまたま上を見上げた人々がぽかんと口を開けている。明日のユピテルのピアネータ新聞あたりに載るかもしれない、と思うと、ヴァリューは暗澹たる気分になる。
そうしてたどり着いたのは色街だった。
人混みを避けて裏路地に狙いを定めたアステールはちり紙のごとくソフトに着地した。
「ナイス着地。褒めていいよ?」
「勝手な奴だな!」
ずかずかと歩いていくアステールに気圧されつつ建物の一つに入る。扉はあまり綺麗ではなく、中も綺麗な印象はなかった。
勝手に入っていったアステールがするすると階段をあがって目的の部屋まで行ってしまう。慌てて追いかけたヴァリューは甘ったるい香水の匂いを嗅ぎ、ここが娼館だと気づく。
「あ、ヴァリューさん」
「どうも」
前に治療した女が心配そうな顔で扉の前に立っていた。他にも数人が屯している。アステールの登場にさっと道を開けたが、緊張しているわけではなさそうだった。むしろ馴れ馴れしい。だが今はアステールにとってその女たちはどうでもいいようだ。ぞんざいにかき分けて扉を開ける。
「薬屋を連れてきたよ!」
「声が大きい。患者には毒なのだよ」
白い法衣を着た小人種の聖職者ニレル・ナタンがベッドで寝ている女を見ていた。端っこには簡素な格好の女の子――シビルもいる。
それでヴァリューはここに呼ばれた理由を察した。アステールの女が寝込んだから治してほしいということだろう。危なそうな話ではないので、ようやく一息つくことができた。
「どんな症状がある?」
「ただの高熱だよ。風邪をひどくこじらせたらしい。多分我慢してたんじゃないかな」
「お前には聞いてない」
ヴァリューは顔近づけてくるアステールをぐいと突き放して、女の方へ向く。
寝込んだ彼女は辛そうに何度か咳き込んでから、喉の痛みなどを主張した。どうやら風邪というのは本当らしい、とヴァリューは納得する。
一通り診察が終わって、ニレルのほうとも話をした。彼の見立ても同じだった。大体の見解が一致したところでようやく、黙って横で二人の話を聞いていたシビルへ意識が向いた。
「嬢ちゃんは何者だ? 樹法使い?」
シビルは慌てて首を横にふる。
「いえ、私はただ看病してただけです……それしかできないので」
「いやいや、キミのおかげで術はそれほど使わなくても良かったのだよ」
ニレルの称賛。確かにヴァリューから見ても女は症状の割に落ち着いている。
女の頭に乗っかっているタオルは何度か取り替えられているのかシーツよりずっと清潔だ。
シーツは寝たきりなので換えられないからタオルだけでも換えていたのだろう、とヴァリューは推測する。それが彼女の精一杯だったのだろう。
「まあ熱ならこの薬でいいか。ニレルはなにをかけたんだ?」
「これ以上熱が上がらないように軽い処置を。後は自然に治るのを待とうと思っていたのだよ」
「じゃあエマ草の根がいい。滋養がある。栄養もここ数日あまり取っていないだろうし、これで治りが早くなるはずだ」
ヴァリューは化粧台に薬を置いて、アステールのほうへ向き直った。
「じゃあ薬代はこの子じゃなくてあんたから貰えば良いんだよな?」
「いやー、スカーレット持ちだよここは」
アステールは両手を振ってにっこりと笑う。色気のある艷やかな笑み。それから軽く視線を扉へ向ける。
ほぼ同時に少し控えめなノックとともに扉が開いた。
スカーレットが入ってくる。扉の向こうには入って来ない娼婦たちが心配そうな表情で部屋の中を覗き込んでいる。
ヴァリューのほうを見たスカーレットは、手元から袋を取り出した。
「いつもすまないね」
「まあ、アステールに呼ばれて」
「こちらは?」
「治癒術師のニレル・ナタン先生さ」
「はじめまして、教会のニレル・ナタンなのだよ」
ニレル・ナタンはにこやかな笑みで一礼。スカーレットも合わせて頭を下げた。
「それで、こいつが治療費払わないって」
ヴァリューはアステールの首根っこを掴んでスカーレットの前に突き出した。
アステールは軽やかに動いて、スカーレットの後ろへ立つ。結構人数が多いので廊下はいっぱいだ。
「ああ、いいさいいさ。むしろこれがいなかったらおまえを連れて来れなかったろうしね」
そういって手元の袋からニレル、ヴァリューへそれぞれお礼を支払う。
「いいのかよ、お前の女じゃねーの?」
「別に。決まった相手は持ちたくないし」
ヴァリューには分からない世界の話だった。
「まあ俺には関係ないか。さ、連れて帰ってくれよ。まだカップの半分も口つけないんだから」
「え、俺を足代わりにする気? 高くつくよー」
ふざけんな、とヴァリューとアステールが言い合いになった。野次馬の娼婦たちの一人がアステール贔屓なのか擁護を始めるが、それに対抗してヴァリューが少し前に薬を売った女も口を出し始め、収集がつかなくなる。忙しそうにするニレルはさっさと帰ってしまい、スカーレットも仕事に戻ろうと踵を返す。
シビルはそんなスカーレットの袖を掴んで止めた。スカーレットが少しの驚きとともに振り返る。みんなの言い合いも止まった。
切実な表情を浮かべたシビルが、おずおずと口を開く。
「あの、わたしが病気になった場合はどうなるんでしょうか」
スカーレットが腰をおろしてシビルの頭を撫でる。
「大丈夫、ここにいる間は私が面倒をみるさ」
それだけ言ってスカーレットは階下へ行ってしまった。
ヴァリューはシビルが何を恐れているのかわからなかった。ただスカーレットを見送る、妙に決意のこもった瞳が印象的だった。
**
私――シビル・ハーコートは怒りのあまり涙を流しながら、ベッドの上で丸まっていた。
悲しいから泣いているのではなかった。悲しみはとっくの昔に過ぎ去っており、今あるのはただただ燃え盛り続ける怒りだけだった。
心が痛くて泣いたのは、両親が小屋の梁に首を吊って死んでいたときが最後だ。
両親の死を知ってからすぐに私を村から引き離したブロックマルツは、借金のカタにちょうどいいから仕方ないと私を諭した。そんなのちっとも納得できなかったし、到底理解することもできなかった。彼にとっては日常茶飯事のことであっても、私の人生は一回きりだ。それをそんな風に捻じ曲げられて、納得するはずがない。
そのうえブロックマルツは私の売値をつり上げるためにスカーレットへ預けた。
彼女は血も涙もない冷血女だということがすぐさま分かった。常人ならば、そんな風に売られようとしている私を見れば、あの猫爺に怒ったってよさそうなものじゃないか。しかし彼女はただ淡々と取引をこなした。あまつさえ私を商品呼ばわりしたのだ。
そんな彼女は私が病気になったら助けるという。
――ここにいる間は
彼女にとって私は大切に扱うべき商品なのだということが端的に理解できる一言だった。私はブロックマルツにとってもスカーレットにとってもただの商品で、私が生かされているのはお金になるからにすぎない。私の人間としての尊厳はもうなくて、全てが数字に置き換えられる商品としての存在になってしまったのだ。
そんなことが許せるだろうか? 私は絶対にできない。
ブロックマルツもスカーレットも商品としての私を、人間とは思っていない。ただ便利で、少し見栄えがいいだけの物くらいに考えている。そんな彼らに私は怒っているのだ。
だがそんな怒りが諦めに変わり、自分で私自身を商品でもいい、と思わない唯一の希望がある。
ここでは教育が受けられるのだ。次に売られる相手に有用な商品となるべく、スカーレットが様々な教えを施してくれる。
これを利用しない手はない。
私は絶対に自分を自分で救ってやる。周りにいる全ての人は敵だ。いつか必ず仕返しをしてやる。自分がモノ扱いした人間が、決して侮るべきではなかったことをその身に余すことなく叩きつけてやる。
そうして私は怒りでカッカと熱くなった身体を丸めて、ごわごわしたベッドで眠る。
瞳の裏には闇が広がっていた。
いまにみていろ!
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp