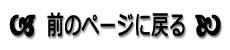●海水浴場の楽しみ方
南国育ちのお嬢様であるフィアマは兄に連れられてやってきたソーンの海水浴場で、あまり楽しめずにいた。
そんななか不満が溜まって一人飛び出し、夏を遊びつくそうと考えているところにルミアと名乗る子が現れた。
【登場人物】
・フィアマ・ソルフィネア
・ファコン・ソルフィネア
・リア・エイリコ
・ルミア・バリシス
・カイル
・ゲルマン・オフチーンニコフ
・リッカ
・ザクロ
・キキ・テリヤ・ニートカ
・エルルカ
・マトリ
・ファル・ワン・エンワン
・ロック・トライボー
・ムツラ
・ノシュマン
・ライル・クロイツァー
・ウィク・イグナイター
・トニョ・ベルトラン
・ヒルデガルト・リーデルシュタイン
・アルトレーゼ
・ルー
・リーズ
・ヴォル
・アフィーネ
・ヴェステルナ
・シェルク・ウェスティン
・マリアンヌ・フィケ
・ルティン
白い砂浜に燦々と陽の光が降り注ぎ、天枝の影が大きく伸び上がっている。海の向こうまで波に揺れる影は続いており、見渡す限りに果てがない。海の向こうで豆粒のように浮かぶ船影が動いているのか止まっているのか分からないようなスケールで見える。
じりじりと水平線の向こう側が揺れる暑さが砂浜を焼く。湿った海風が肌をべたつかせ、塩辛い空気を運んでいる。
フィアマ・ソルフィネアはつまらなそうに頬を膨らませて、ウッドデッキの縁にもたれていた。
「もう少し楽しそうな顔してくれよ、せっかくの海だろ」
「だってわたくしは泳ぎたいんですもの! なんでこんなところで……」
兄のファコン・ソルフィネアがフィアマの露わになっている肩にそっと服を着せると、水着を隠した。
海は遠い。
浜辺は人工的に岩肌を砕いて砂を投入し、海水浴場としての体裁を整えられている。差し渡し2ケルの浜辺には海と平行に屋台が立ち並んでおり、両端には岩肌がまだ残っている。すり鉢気味の地形には海を見下ろすようにログハウスがいくつか建っている。そして城壁の外である街外れ側にはいくつかの石造りの建物が立ち並び、城壁で守られていない海水浴場を保護している。
海水浴場への入り口は海側になく、入るには砂浜を管理している建物で入場券を買わなければいけない。養浜と海獣対策と穀倉地帯側の警備、周辺環境の開発を含めてかなりの資金が投入されているため、海水浴場は無料で開放できる余裕はなかった。
しかしそうした事情によってある程度の客の質が保たれており、安心して遊ぶことのできる施設となっている。そうした条件がファコンにとっては都合が良かった。名家であるソルフィネア家の人間が仲間を誘って遊びに出かけるなら、これくらい胸を張れる場所であるべきだった。それに妹への心配も少しは緩和される――はずだ。
だがそんな海水浴場ではフィアマは満足できない。
「なんでみんな泳いでないんですの! わたくしがいたエードローエではみんなもっと海に出てましたわっ」
「年中暑いわけじゃないし、天気が悪いと海もぐっと冷え込むから仕方ないじゃないか」
そういう兄は学友を大勢引き連れて、貸しきったログハウスを開放し、肉を焼いていた。つまらなそうにしている妹のためを思って皿に肉をよそっている。ちゃんと野菜もセットだ。
「でも今日は天気も良いしきっと泳いだら気持ち良いんですのよ。なのにこんなに海から離れて! これじゃあ別に家の地下で肉焼いたって代わり映えしませんわ」
「流石に違うだろ……」
呆れるファコンはあーんと無理やり妹の口へ肉を放り込む。不満たらたらでも食欲はあるフィアマがもぐもぐとされるがままに食べていると、途中でファコンは学友に呼ばれて友人たちの輪に帰ってしまった。
この夏、キキ・テリヤ・ニートカが発表して話題となり夏の入道雲のようにあっというまに模倣品を含めてソーンに広まった肌の露出の大きな海水浴用の水着の上に明るい色の薄い布を羽織ったマトリがファコンの口へ野菜を放り込み、どよめきが笑いへ移っていく。さらにはバイトの経験を活かして火加減をうまく調節しながら肉を焼くエルルカへの歓声が湧き、輪から外れたフィアマだけが場違いみたいだった。
一人になったフィアマは中途半端に残った肉に目をおとし、それからゆっくりと顔を上げて辺りを見渡す。
学友たちに囲まれる兄は楽しそうで、じりじり焼ける肉は熱気で陽炎が立ち、ウッドデッキの周りはフィアマの不満もどこ吹く風で盛り上がっている。自分だけが一人違う世界にいるような気分になり、とたんに兄たちとの距離を感じた。
エードローエの熱風とは違う冷たい風がうなじを撫でて、フィアマの背中に生えた白い翼をくすぐった。
だがそこでフィアマは立ち止まらない。皿に盛られたものを綺麗に食べ終え、いつも持っているハンカチで口元を拭う。
――兄に海で遊ぶ気がないなら、自分だけで遊びに行ってやる。
そう決心を固めた。
**
こっそりとログハウスを抜け出してつづら折りになった道を降りていく。見下ろしていた砂浜が近づいてくるにつれて潮の匂いが濃くなり、喧騒が大きくなった。
整備された白い砂浜は、プロタ・リズマの短い夏を楽しむ人々で溢れている。露店がいくつも賑々しく立ち並び、その周囲には幾つもの丸テーブルが据えられており人でごった返している。テーブルには大勢がアルコールを囲んで騒いでいるのもいれば、上品に背筋をピンと伸ばし綺麗な所作で食事を取っているものもいた。
ヴェステルナはその筆頭で、塩の効いた魚の串を礼儀正しく食べている。黒っぽい落ち着きある水着が映えていた。
潮の匂いと美味しそうな匂いの混じったものが流れてきて、フィアマはうきうきとした。幼い日のエードローエでは、よくこうして海で遊んだものだ。
フィアマはきゅっきゅと砂にサンダルで足跡を付けて、文字通り飛び上がらんばかりに歩く。
フリルをたっぷり使ったピンク色の甘い水着は、彼女自身が考えるよりずっと似合っていて、選んでくれたファコン(と、彼にアドバイスを与えたエルルカ)に、彼女は感謝すべきだろう。あとは彼女の動作がその可愛らしい水着に似合うくらいにおしとやかに落ち着けば、この水着を縫った職人も浮かばれるというものだ。
フィアマは露店の一つ、“出張・虎の鰭亭”とのぼりの出ている店の前で立ち止まり、白身魚のフライから漂うハーブの香りに、思わずポシェットから赤いお財布を取り出した。
「これいただけますかしら?」
「はいよ、4リルね」
ぴょこんと耳を跳ねさせたルティンが威勢の良い声でバックヤードのリア・エイリコに魚を揚げるよう指示をだす。慌てて動くリアが揚げた魚に塩を振って古紙で包む。二人とも水着の上から着たエプロンには油ハネがついているが、おかげで肌は守られているようだった。
まだ熱いから気をつけなよ、というルティンの話を聞いてるのか怪しいフィアマは笑みを浮かべて受け取り、すぐさま魚を頬張った。立って食べるのははしたないからやめなさい、ということは親にも乳母にも兄たちにもエードローエの教師にも寮監にも言われていたが、今はそのいずれもここにいない。フィアマは自由なのだ。誰に気兼ねすることがあろうか。
塩の振ってある魚は表面にサクサクと歯ごたえがある。だが白い身は柔らかく、何度か噛んでいると旨味が染み出してくるようだ。すっかり食べるのに集中してしまったフィアマは人通りの多い場所を避けて、木陰の一角を陣取った。
財布は膝の上において、盗まれないように紐を太ももの間で挟む。ソルフィネアの家紋が縫いとられた高級な一品物の財布だが、フィアマの扱いはあまり良くなく細かい傷がいくつもついている。今もフィアマが食べる魚から垂れた脂がこぼれて跡をつけている。
しかしフィアマはそれに気づくこともなく食事をしていた。
「もしかして一人? 迷子でしょ」
気づけばフィアマの横には物音一つ立てずに女――ルミア・バリシスが立っていた。
思わず顔をあげるが、その拍子に最後の一口を取り落としそうになる。あわあわと手を振って揚げ魚を掴もうとするがいずれも空を切った。
「――っ、はい」
そんなフィアマをよそにルミアはすんなりキャッチして、手渡した。
「あ、ありがとう」
なんで急に横に現れたのかとかなんで話しかけてきたのかとか、そもそも誰なのかとか色んな疑問が浮かんだが、いずれも綺麗に頭から抜け落ちて、とりあえず感謝を述べることしかできない。フィアマは呆けた顔で魚を受け取り、最後の一口をもしゃりと頬張る。
「どういたしまして、私はルミア。あなたは?」
「フィアマですわ」
思わず相手へ自己紹介してしまう。フィアマより数年歳上であろうすらりとした出で立ちのルミアは落ち着いた雰囲気で満ちていて、なぜかフィアマは素直に答えてしまった。よく見れば腰に刀を佩いていたり、目だけで周囲を軽く伺っていたりと怪しいのだが、それらをかき消すほどの人懐っこい空気も同時に滲ませていた。
偶然会ったのか、露店を巡っている時点で目をつけられていたのか、はたまたこの海水浴場に来るまでの間にターゲットにされていたのか。
そうした疑問が湧き上がってルミアへの不信感へと切り替わる前に、またもやルミアは話しかけてきた。
「ねえ、もしかして一人?」
「そんなところですわ。いいじゃない、別に」
フィアマはつんと突き放してさっさと海へ行こうとした。
「ま、待って!」
それをルミアはぎりぎりのところで腕を掴んで止めて、強引に向き合う。フィアマは驚いて目を丸くするが、ルミアが刀を抜く様子はないとみて、少し安心する。
「なに?」
「一緒に回らない? 私も一人なの」
ルミアの真剣とも冗談とも取れる奇妙に脱力した笑みがフィアマに向けられる。
その笑みをどうにもフィアマは疑えなかった。
それに一人で遊ぶより二人のほうがきっと楽しい。
**
二人はそれからとりあえず腹ごしらえを楽しみつつ済ませた。
歩きながら食べやすいということで串焼きの店により、両手いっぱいの串を頬張ったり、しょっぱい肉の後は甘いフルーツが食べたいと軽食屋に寄ったりと一通り腹に詰めこめるだけ入れ、食べたいものを食べた。
「嬢ちゃんたち、そんなに食べると腹壊すぞ」
串焼きの屋台を営んでいるカイルは心配そうに二人の豪快な注文を慮り、
「まあ、ちょっと大きめのボウルを用意しなきゃ。待っててね」
軽食の屋台を出しているノエルには驚きつつ歓迎されていた。
そうして一通り腹に収めるものを収めたあと、二人はのしのしと浜辺へと繰り出した。先導するのはフィアマだ。ルミアは彼女が何をしようとしているのか知らず、ただほいほいと付いて行った。
浜辺には大勢の客がビーチチェアに座ってぼんやりと海を眺めている。幾人かで固まって雑談に興じているグループもあれば、ひたすら酒を飲んで騒いでいるグループもある。小さめのテーブルを砂の上に置いてカードをしている人影もいるし、一人でただ何もせずにひたすらぼんやりと贅沢に時間を使っている者もいる。
バイト中の学生であるファル・ワン・エンワンはビーチチェアでのんびりしている客たちにドリンクなどのサービスを配達しているし、巡回の警備担当として帯剣したロック・トライボーが砂浜を巡回したりもしていた。そうした仕事中の人々も砂浜には大勢いる。
しかし逆に変な連中も多い。ムツラはその一人だ。
周囲をまるで知り合いを探しているかのように歩きまわっているが、実際のところ知り合いがいるわけでもないし、待ち合わせをしているわけでもない。物盗りの算段を立てているのだ。注意散漫な連中を狙って財布の一つや二つ盗ってしまおうというわけである。
しかしそうした目論見は、ルミアにとって見破れて当然のことだった。ひと目見て怪しい動きをしているムツラを見つけるや、ルミアは大事をとってフィアマをそれとなく誘導して接触ルートから遠ざける。海水浴場には意外な危険がそこかしこに潜んでいた。
しかし危険だけが跋扈しているわけではないし、むしろ多くの人々は無害だ。
準待機中で暇を消化しているライルもその一人だった。近くにはちょうど最近彼が知り合ったウィク・イグナイターもおり、二人して日焼けする気満々の格好でチェアに寝そべっている。二人とも際どい水着を着ているが、あまりそこに頓着はしていない様子で、たっぷり果肉が入ったカクテルを二人して飲み干してのんびり海風に当たっていた。
それと同じように、鍛冶師のノシュマンもチェアに寝そべって本を読んでいた。彼はあまり日焼けが好きではないのか、日除けのパラソルの陰に隠れており、長い足から伸びるつま先だけが日に当たっていた。
いずれもあまり海に入っている様子はない。
「なにをする気?」
椅子なら窓口で頼めばレンタルできるよ、というルミアの言葉はフィアマの強い断言にかき消された。
「海といったら泳ぐに決まってますわ! それ以外ないでしょうに!」
「え?」
本気かどうか訊ねようとしたルミアだったが、一目散に浜辺を駆け抜けるフィアマの後ろ姿を見ていると答えを聞く必要はなさそうだった。長い刀をがちゃがちゃ鳴らしながら追いかける。浜辺で寝そべる人たちから奇異の目線が向けられる。気にする暇もない。
あっという間に波が押し寄せる海辺まで近づく。まばらに足を海水につける子どもたちがいるばかりで、大人どころか年頃の娘は全くいない。そこに乗り込んだフィアマはずんずん海の方へ進んでいく。波が押し押せては返っていき、フィアマの足取りは遅い。
ルミアは後ろから難なく追いすがり、波にさらわれないようにフィアマを見つつ、自分も海に足をつける。
「あー、なんで海にあまり皆さん入らないのか少しわかった気がしますわ」
「どうして?」
「ちょっと水温が冷たすぎる気がしますもの。これで天気が悪かったり風が強い日とかになるともう入れないでしょうね。水温が真夏でもギリギリってところかしら」
「あー、確かに。それだと根付かないよね。もしかしてフィアマって南のほう出身だったり?」
「そうですわ、よく分かりましたわね。実家はエードローエですの」
「そりゃあ海水浴もするわけだ。なるほど」
得心のいった様子のルミアは腰ほどまで海に浸かったところで足を砂から離して、水の流れに身を任せた。ほんのり冷たい海水が熱い日差しで温まった体に心地よい。水温に慣れてくると体の境目がなくなったような感覚に襲われるのも楽しかった。
ばしゃばしゃと泳ぎながらあっちへ行ったりこっちへ行ったりを繰り返すフィアマは、しばらくするとルミアへ近づいてくる。淀みない泳ぎ方に南国出身らしさが垣間見えた。
「どう? 楽しいかしら」
「気持ちいいなー、天気が良いときはみんなもっと泳げばいいのに」
ぱっとフィアマの顔が明るくなった。
「でしょう!? やっぱりお兄様も無理を言って連れてくれば良かった……」
「お兄さんがいるの?」
「ええ、でもこっちじゃ泳がないからいいんだって」
「そりゃあもったいないなあ、海水浴場にも来なかったのかい」
「向こうで学校のお友達と遊んでますわ」
そう言ってフィアマは崖のほうを指さした。もうすっかり最初のことは忘れていて、自分が一人でいる、なんて話をしたことは頭から抜け落ちていた。ルミアはそれを指摘することはせず、一人黙って頷くに留めた。目を眇めて崖の方を見る。
「これ以上いたら身体が冷えるからちょっと私はあがるよ」
あらそうですの、とフィアマは言ったが浜辺へ戻ることはしなかった。ゆったりと身体を波に預けている。
その間にルミアは海から上がるが、なぜか今度は海へ入っていく人影が増えていた。
「危ないからあんまり遠くには行かないのよ」
「分かってるって」
マリアンヌ・フィケは娘の後ろをおろおろしながら歩いている。さらにその後ろには二人の保護者を買って出ていたゲルマン・オフチーンニコフが仁王立ちしており、いざとなれば二人とも海からすくい上げるつもりで待機していた。
他にも数人の子供連れが海へ入っているようだった。さらには子供だけの友人グループと思わしき人たちも海へ向かっていた。トニョ・ベルトランは友人であるヒルデガルト・リーデルシュタインが大蜘蛛のテオに乗ったまま海へ入るのを少しの間心配そうに見つめていたが、やがて何の問題もないということが分かると一転楽しそうに水を掛け合って遊んでいた。
ルミアは彼らの行動を少し観察してから、遠くにみえるフィアマを見つめる。
どうやら彼女の行動力が、海の楽しみ方に一つの転換点をもたらしたようだった。
浜辺には先程までゆったりと椅子にもたれていた人々が数人立ち上がっており、興味津津な様子で海を見ている。その中から一部が海まで足を浸け、さらにごく一部がびしょ濡れになって遊んでいた。
剣を佩いたまま海の境目でうろうろしているシェルク・ウェスティンもその一人で、大いなる好奇心がそこまで手を伸ばしているにも関わらず、最後の一歩が踏み出せないようだった。後ろで見ていたヴォルが前後にふらふらしながら迷っているシェルクの背中をたたき、
「とりあえず剣だけ置いてったほうがいいだろ、何に使うんだよ」
と言って無理やり海のほうへ押し込んでいた。シェルクはシェルクでマイペースに「だって魚が……」と言っていたが、有無を言わせないヴォルの様子に根負けして剣をおいて海へ入っていった。
他にも子どもの姿に釣られて海へ行こうとする聖職者、アフィーネの姿もある。脇には同じく聖職者のアルトレーゼもいてどうにかアフィーネを止めようと足を突っ張ってはいるが、踏ん張りの利かない砂浜では分が悪い。あっという間にアフィーネは子どもの輪の中に突撃していった。
ルミアはそうした人々の様子を横目に、フィアマをじっと見つめる。
徐々にフィアマの周りには人が集まり始めており、それ以外の面々も楽しそうに海水に飛び込んでいた。
それを尻目にルミアは視線を崖の方へ移す。フィアマはおそらくあそこで兄と遊ぶのが今日の予定だったのだろう。そこから一人で抜け出してきた、というのが妥当な推測だ。なら今頃は兄や他の知り合いがフィアマを探しているに違いない、とルミアは当たりをつける。
そもそもたとえ治安が良いとしてもあの歳でひとり外を歩き回るのは危険だ。
目を離さず、てきとうなところで元いた場所に連れ帰るのが良いだろうとルミアは判断する。
「やっぱりもう少し遊ばせてくれーっ」
そういって無邪気を装ったルミアはフィアマが新しい友達に囲まれているなか突っ込んでいき、みんなでひたすら水を掛け合い遊んだ。
様子を遠巻きに眺めるだけだった砂浜の人々もしばらくするうちにさらに海へ入っていき、徐々に海で遊ぶ人が増えていく。
そうしてフィアマとルミアは疲れ切るまで海で遊んだ。気づけばもう空は茜色に染まっており、天枝の長い影が水平線の向こうまで伸びていた。
**
出張営業をしているラ・メル・ソーンではいつもの湯船がない代わりにいくつもの個室が並んでいた。水を出せる樹法使いを用立てたり、都市内から運んだ清潔な水を個室内に設えられた大きな水槽に貯めているのだ。個室利用料金はいつもの入浴料より少し高い2タレルだが、海水浴場で流した汗を洗い流してから帰りたい人は多いため、客は多い。
需要を見越してラ・メル・ソーンに樹法使いやテナントの貸出をしたのは一説によると裏町組合と言われているが、実際のところは分からない。そもそも海水浴場自体裏町組合が一枚噛んでいると言われている。そもそもソーンで大規模な養浜などの開発工事を行えるノウハウを持っている団体は少ないため、必然的に大規模な犯罪組織が絡むことは避けられなかったのかもしれない。
それでも海水浴場に訪れる客の質は大半が高い水準にあるため、変な揉め事が起きるようなことは滅多にない。
疲れ切って後は着替えて眠るだけのフィアマをつれてきたルミアもそれほど注意を払うことなく、隣同士の個室へ入って海水と汗を洗い流した。フィアマも疲れをなんとか振り切って身体を洗う。服は有料の乾燥サービスを使って綺麗にしてもらっていた。
そうしつつもルミアは一足先に個室を出て、濡れた身体を拭った。そうしてこっそり出ていき、周囲を伺う。
普通の屋台とは違い、しっかりとログハウスのように建設された店内は長い廊下が続いている。途中にはラ・メル・ソーンの外で開かれているマッサージ屋などが中にテナントとして営業していた。
そこに当たりをつけたルミアは髪を乾かして、フィアマが出るのを待つ。
「あら、早いんですのね」
ようやく出てきたフィアマは髪の毛がまだしっとりと濡れていた。背中の翼も水を吸って重そうだ。ぶわりと体ごと震わせて水を払いたいのを我慢しているのか、フィアマの表情は硬い。
それを見越したルミアは廊下の一角へ案内した。
「いらっしゃいませ! こっちがあたしに頼みたいって客かい?」
「うん、代金は払っといたから楽しんでね」
「え? どういうことですの?」
ルミアは困惑するフィアマを獣人種向けのエステなどを営んでいるリッカの店へ放り込んで、自分はすぐさま外へ出た。それから先程フィアマが言っていたログハウスの方へ走っていった。かなり遠いし、人も多い。フィアマが店から出てしまえば、「代金は払っといた」という嘘がバレてしまう。
そうして浜辺とはまた別の喧騒の広がるログハウス周辺へたどり着いたルミアは片っ端から話を聞いて周り、フィアマの兄のファコンを見つけた。若干青ざめた顔と、話しかけても鬱陶しそうにする瞳で、ルミアはすぐさまフィアマのことに気づいているのだと知った。他の学生たちもフィアマ探しを手伝っており、心配そうに眉を潜めている者たちが大勢いた。いつもは泰然としているゴーレムマスターのリーズもしきりにうろうろする程度には焦っており、背負った棺桶がたびたび学友たちにぶつかっている。後頭部に思い切り棺桶をぶつけられたルーは、綺麗に受け身を取ってくるりと地面に転がる。その様子を見もせず、心底心配したふうに鼻頭を抑えるファコンがルミアに頭を下げる。
「本当にありがたい。あんたがいなけりゃ今頃どうなってたか……」
「いやいや、いいよ。困ったときは誰かに頼るもんだよ」
そう言ってルミアはファコンの顔をバレないように観察する。どうやら本当に焦っているらしい。それならもう自分がやることは道案内程度だな、と判断してルミアはファコンをラ・メル・ソーンの出張営業所まで連れて行った。
ちょうどブラッシングとエステが終わったところでフィアマが店前に出ているところで、ファコンはいち早く彼女の姿を見つけた。
「なにしてるんだ!」
「うわ、お、お兄様……」
流石のフィアマも今回の遊びが怒られるものだというのは承知していたらしい。目を見開いてファコンの顔を凝視する。ファコンのほうは大股でフィアマに近づいて、目の前で見下ろすようにして止まった。
フィアマは一瞬目をぎゅっと瞑って次の瞬間の怒号に備える。しかしそんな彼女に待ち受けていたのは、
「心配したんだぞ……いくらなんでも急にどこかへ行くのはやめろ!」
抱擁だった。
ファコンは思い切りフィアマを抱きすくめて、顔を彼女の髪に埋めた。いつもはぴょこんと立っている両耳が力なく垂れて、心底不安だったことが伺えた。
ルミアはそれを横目に笑みをこぼし、気づけば横にいたマッサージ屋のザクロという女性に不思議そうな顔で見られていた。周りも抱擁する二人をにやにや笑って眺めているルミアが不思議なのか、遠巻きにして見ている。リッカだけは「あたしのせい!?」とかなり困惑している様子だったが、誰も答えるものはない。
**
しばらくしてからログハウスへ片付けに戻ろうと店を出た二人は、慌てた様子のリッカに引き止められる。
「ちょっとお客さん! 代金は?」
「え?」
「だから、代金だってば。ブラッシングとエステと石鹸代」
ファコンとフィアマは二人して顔を見合わせる。
「代金は払っておいたとルミアさんは仰ってましたわ」
「それより石鹸代ってなんだ? エステで使ったならエステ代に含まれるんじゃないのか?」
二人の前で仁王立ちして通せんぼするリッカは二人の会話を不思議そうに聞いている。
「いや、代金は払われてないぞ。それに石鹸代はさっきこの子を連れてきた女の子が持っていった分だよ。聞いてないのか?」
二人はようやく何が起きたのか気づいて、怒ればいいのか駄賃として気にしないでおくべきなのか少し悩んだ後、顔を見合わせて笑った。
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp