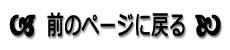●アリーナの罠
双子都市ソーンには、建設以来千五百年の歴史を持つアリーナが存在する。
そのアリーナをめぐる事件に巻き込まれた花形剣士レビィア・トピアスとアキレァは……。
【登場人物】
・レビィア・トピアス
・アキレァ
・トビア・サンチェス
・ニレル・ナタン
・リーズ
・ウリエラ
・ドロイ・トピアス
・シェック
・アリミナ
・ベルゼ・カロン
・ドクトル・ハニィマシュー
・ノワ
・ガルム・ウォレス
・ルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオ
・ブロックマルツ
・レイ・セライン
・ラスグィル・ダルジェエリング
・アルフレド
わあっ!
双子都市ソーンのアリーナに歓声が上がる。
楕円形のすり鉢のようにくぼんだ形のアリーナは、千五百年前にソーンが建設されて以来の施設であり、現在よりもゴーレム技術が優れていた時代の産物である。現在はこれほど巨大な建造物を造ることは難しい。
直径は長いところで四分の一ケル(約250メートル)に及び、およそ四万人の観客を収容できるこのアリーナは、現在さまざまな用途で活用されている。
例えば市民に対し公開するような閲兵や、月の夜の音楽祭、馬を入れてのレースなど。
しかしその最大の用途こそが、この闘技である。
「よいしょぉ!」
赤毛の獣人種が黄金の大剣をすくい上げるようにぶちあげると、甲羅の高さが2ミルはあろうかという亀(甲羅にとげがついていて、さらに強靭な顎を備えたカミツキガメの怪物だ)の前足が跳ね上げられる。斬るのが狙いではない。この鈍重だがどっしりした安定感のある恐るべき魔獣のバランスを崩すためだ。
“鮮血の赤兎”レビィア・トピアス(彼女自身はその通称にはなはだ疑問を持っていた)はにいっ、と笑う。客席に笑顔が見えたかどうか。入口で売っているガラスを使った望遠鏡はあまりに高価だ。高級な席をリザーブしている貴族や議員の方々はお持ちだろうが、お父さんに肩車されているような子供は持ってはいるまい。
レビィアはちょっとサービスして左腕を上げてコールを要求。獣人種の鋭い目が、客席の少年の掲げる拳をとらえた。
彼女はたたらを踏む亀の腹に突進し、肩から体当たりした。
危険な攻撃だ。もしタイミングが合わず亀が彼女の方に倒れ込んできたら、小柄なレビィアなど“のしイカ”のようにペシャンコになってしまう。
しかしそうはならなかった。
よろけて元の四足状態に戻ろうとふらつく亀はさらに上体を起こされる。
ふらふら……。
観客からすれば、いつレビィアが亀の下敷きになるかと気が気ではない。あのカミツキガメが演技しているなどとは誰も思えない。実際にそれができるはずもないのだが……。
レビィアはすっとしゃがみ込むと黄金の大剣をこんどは横薙ぎに振るった。
彼女の剣は樹法具だ。もっとも、レビィア自身は樹法などとんと心得がないから仕組みは分からない。内部が液体金属になっていて重量配分を変えることができて……などと説明されても良く分からない。彼女の弟のドロイ・トピアスの義足と仕組みは同じで、おそらく一組で使うように作られたものなのだろうが、彼女はそれらの来歴すらよく知らなかったし、興味もなかった。王立樹法研究院の樹法具研究家トビア・サンチェスなどに見せたら、黄金剣の変形機構など早口で説明した挙句に彼女の理解のなさを口ぎたなく罵るに違いない。
しかし、アリーナの人気剣士レビィア・トピアスにとっては、持ち主には見た目より軽くしかしぶんまわすと敵に重い、というその実際的な効果だけで充分だ。
薙ぎ払われた黄金の大剣は亀の後足に命中し、よろけた亀の足をすくう。
亀の足は甲羅ほどではないにせよ頑丈な鱗に覆われており、いかなレビィアの大剣とはいえ両断するのは難しい。しかし、その必要は無いのだ。
ずぅん。
上がる砂ぼこり。
固唾をのんで見守る観客席。
渡る風が砂ぼこりを吹き払い……。
ひっくり返って丸太のような足をバタバタさせる亀と、得意満面で黄金の大剣を掲げる鮮血の赤兎の姿がそこにあった。
◆◇◆
「いやぁ、助かったよぉ!」
小太りの中年男性が、控室に戻ってきたレビィア・トピアスを迎えた。
「どうだった?」
「大盛り上がりさ!」
「でっしょー?」
「実際、亀が死ななかったのも有難い……」
「いや、あれ殺す方が大変だよ……」
中年男性……興行主のバート・ロウ氏は、耳の分自分より背の高いレビィアの腕をぽんぽんと叩いた。
「シルヴァーのやつ、急に来ないなんてなぁ……レビィアがいたからいいようなもんの」
バートは首をかしげる。その表情は心配そうだ。
シルヴァーというのは、バート氏と契約しているアリーナ戦士の一人だ。
彼は見上げるような巨漢の獣人種で、毛むくじゃらのぶっとい腕と脚、狂暴に笑うと覗くごつい牙、額に白銀の模様がその名の由来で、勝利すると胸を叩くパフォーマンスで人気があった。
レビィアも何度か対戦したことがあったが、力勝負となるといかにも分が悪い。彼女の黄金剣は人種相手には封印しているので刃引きした同じような大剣をつかうのだが、彼はなんと素手でレビィアと対戦し、やくざな大剣を叩き折ってしまった。対戦後怪我をして治癒術士ニレル・ナタンのお世話になっているレビィアを、小さな(彼が大きな手にのせていたので、まるで豆粒のようだった)お菓子を持って見舞いに来てくれたものだ。
そのシルヴァーが、本来あのカミツキガメと戦うマッチングになっていたのだが、珍しいことに時間になっても現れなかった。
仕方なく、すでに別の相手と一戦終えて大きな怪我もなかったレビィアが代役に立ったというわけだ。
「シルヴァーの代役だからね、みっともないマネはできないよ」
と、レビィア。
もしシルヴァーがあのカミツキガメと戦っていたなら、きっとがっぷり四つに組んだ力比べが拝めたことだろう。彼ならゴーレムだって止めて見せるに違いない。
「まったく。どうしちまったんだろうな、ウチの戦士どもは」
バートがため息をつき、レビィアはそれを聞きとがめた。
「ども?」
「あぁ。来てないのはシルヴァーだけじゃないんだよ」
「ヘェ」
「つまり、自分の出番というわけさ」
急に後ろから聞きなれた声がして、レビィアは振り返った。
「アキレァ。午前中に対戦したじゃない」
「キミとね」
立っていたのは、レビィアも知っているアリーナ剣士アキレァである。
レビィアよりも身長が頭二つほど高い。どちらかと言えばトランジスタグラマーなレビィアと違い、すらりとした長身で手足の長い彼女は、レビィアとは違った層のファンを獲得していた。
アキレァはその身体のようにしなやかで細身の長剣をひらめかせ、長いリーチと華麗な身のこなしで戦う。客が前列で食べ物を持っていると、試合後の挨拶の時にそれを食べてしまうパフォーマンス(レビィアはそれがパフォーマンスなどではないと確信している)のため、若い女性ファンの中にはわざわざそれ用に屋台で骨付き肉を買って準備していく者もいるほどだ。
アキレァとレビィアは午前に対戦し、結局引き分け。どちらも大きな怪我もなく、賭けていた観客に損をさせただけで終わっていた。
「サックスも来てないんだ」
バートは頭を掻いた。
サックスはシルヴァーの親友と言ってもいい友人の広人種で、小柄で袖口に仕込んだナイフで戦う戦士だった。
「で、自分が代役ってわけさ」
アキレァは腰に佩いた愛用の長剣を叩いた。
「バート、相手の奴は……やっつけちゃっていいんだろ?」
「大きく出るじゃない、アキレァ。レビィアと戦ってへばってたくせに」
「そう見えたかい? 見る目が甘いよ、ウサギちゃん」
「何よ!」
「はっはっは。キミがせっかく場を暖めてくれたからね、このアキレァに賭けておくといいよ。少ないファイトマネーを倍にできる」
アキレァは笑いながら、ニギニギしい呼び出しに応じて入場ゲートへと歩いて行った。
「それにしても……」
口をとがらせてその背中を見送るレビィアの横で、バートは腕を組んだ。
「二人とも、どこ行っちまったんだ」
◆◇◆
「ねぇロジィ」
まだ霧が漂う朝のカフェ・ド・エクスで、二人の美女が優雅にお茶などたしなんでいる。
双子都市ソーンの中央を流れるエルディソン川は汽水域で、朝夕に霧を発生させることがある。夏だというのに少し肌寒い。今日はそんな日だった。
「あなたがいつも飲んでるそれ」
「お茶の事?」
赤いパイレーツコートを羽織り、異国風の大きな羽根を飾った帽子を脇に置いた金髪の女性……レイ・セラインが、おおぶりのサンドウィッチをぱくつきながら指を差した。差されたほうの、やはり金髪碧眼、青いドレスを優雅にまとい、白磁のティーカップを揺らしていたロジィことラスグィル・ダルジェエリングは、白い指を伸ばしてレイの指をつまむと天井を向ける。
「失礼でしょう。指をささないで」
「ごめん」
「結構。それで?」
「あなたいつも、ここのが美味しい、今日はいまいち、家でわたしが淹れてあげたら“なんですのこの泥水”とか言うけど」
「そこまで言いましたかしら」
「言った。それって、あなた味解ってるの? 雰囲気で、なんかそれ飲んでたら知的な自立した先進的な女って感じでカッコイイとか思ってるだけじゃない? あなた基本かっこつけよね」
「喧嘩売ってますの。買いますわよ。おいくらかしら?」
「ロハでいいよ。気前いいでしょ」
「ただより高いものはない、っていう言葉をご存じないようですわね」
朝のカフェ・ド・エクスに客は少ない。
アルフレドはため息をついた。アルバイトに来てくれるリーズは夕方からだ。彼女には学校がある。つまり、知的で美しい美女二人の、あまり知的とは言えない会話にしばらく一人で耐えなければならないのだ。この際、普段はやっかいな客と思っているウリエラでも来てくれればいい。そうすれば雑談で時間を潰せるだろう。彼との会話はそれはそれで疲れるのだが。この街の美人さんはめんどくさくないといけない法則でもあるのだろうか。と、彼は(自分のことを棚に上げて)考えた。
からん。
音が鳴ってドアが開き、じっとりとした霧を連れて、一人の中年男性が入ってきた。
「いらっしゃいませ」
アルフレドは顔を上げる。見ない顔だ。初めてのお客だろう。
彼は店内をきょろきょろして、そして奥の席に座っているレイとラスグィルを見つけた。レイが片手をあげ、二人の暇つぶしもといじゃれあい否喧嘩は休戦となる。どうやら待ち合わせをしていたらしい。アルフレドは聞くとはなしに聞きながら、カップを磨く仕事に戻った。
「やぁ、どうも」
男性は慣れない店内を見回しながら、レイとラスグィルの座るテーブルについた。
「お話はお伝えしていると思うのですが、どうも、バートと申します」
「ごきげんよう。ラスグィル・ダルジェエリングですわ。こちらは助手のレイ・セライン」
「相棒よ」
「お話は伝わっておりますでしょうか」
バートは二人にちょっと頭を下げてから小さなハンカチを取り出し、額をぬぐった。ロゴの染め抜きがある。
「さて、できればあなたからもう一度お伺いしたいですわね。なにせわたくしには、あなたがアリーナの興行主のひとりで中堅どころ。抱えている戦士はだいたい十人程度ですけれどその中には結構な人気者がいらして、同じ中堅仲間の中では羽振りのいい方。でもそれをひけらかすことの危険性を知っているくらいには知恵が回り、戦士をそれなりに大事にしている。そのくらいしかわかりませんもの」
「えぇ、えぇ、確かに」
バートはアリーナで配っているハンカチでもう一度額をぬぐった。
「しかしなぜそこまで……? 私は使いには人探しをして欲しいとしか伝えていなかったはずですが」
「種明かしはしませんの。“まほう”は解らないからこそ“まほう”なのですわ。どうしてもというならお話しますけど」
「喋りたいくせに」
レイは苦笑する。ラスグィルは彼女をちらりと見て、言った。
「オホン。ほんとうに優れた技術は魔法と見分けがつかない、ですわ。あくまでわたくしの優れた技術と知識と知性によるものであって“まほう”ではない、とだけ。では、魔法が解けてバートさんが値切り交渉を始める前に、ご依頼についてお話していただけますかしら?」
アリーナの興行主バートは、連絡の取れなくなったお抱えの戦士、シルヴァーとサックスの捜索を依頼した。
二人は一昨日の試合に結局現れず、昨日、家(彼らはごく普通の長屋に住んでいた)に行ってもいない。大家も二人の行方を知らず、ほとほと困り果てたバートは、うわさに聞いた探偵業なるものを営むレイとラスグィルに話を持ち込んだ、というわけだ。
「それは心配ですわね」
と、ラスグィルは顎に人差し指を当て相槌を打つ。
「シルヴァーは知ってる。見たこともあるよ」
「へぇ。あなたがアリーナにねぇ」
「賭けたこともあるけど……それよりもシルヴァーは筋肉ムキムキでね、かっこいいのよ。悪役で、狂暴で。あの狂暴な人がねぇ。失踪かぁ。悩み事なんて噛み砕いちゃいそうだったけど」
「そういう男性が好みだったの?」
「そうじゃないけど。何よ、気になる?」
「ぜんぜん」
「いや、シルヴァーは実際はそんなに狂暴な男ではないんです。結構繊細なところもあって」
脱線をはじめそうな二人に、バートは割り込んだ。
「サックスとも仲のいい友達でして。あの容貌なんで悪役をすることは多かったですが、実際のところは気のいい男だったんですよ」
「へぇ。意外」
「人は見かけによらないってことですわね。勉強になりましたかしら?」
「……そうね。あなたの目の前の友人も、案外違う顔があるのかもよ」
「あなたが? ふふ、まさか! ではお引き受けいたしますわ。報酬は終わってからで結構。かかった経費も請求させていただきますけれど、よろしくて?」
「もちろんです。あの二人に何かあったら……」
「儲けられない?」
レイが口をはさんで、ラスグィルは目を細めた。
「まぁ……それはもちろんありますが……二人は友人でもありますし……。それに、ほんとうに気のいい男なんです」
バートはもう一度ハンカチで額をぬぐい、二人は目を合わせて頷いた。
「大変結構。あなたが儲けなんてどうでもいい、とおっしゃったら引き受けないつもりでしたの。わたくし、嘘つきは嫌いなの。まして依頼人としては。行きましょう、レイ」
「オウケイ。まずはどこから?」
「現場ですわ」
「現場って?」
「アリーナ」
レイとラスグィルは立ち上がると、ぽかんとするバートを残し、こつこつと靴を鳴らして霧のソーンに繰り出していくのだった。
アルフレドは、二人のお会計はあのバートさんとやらに頼もうと決めた。
◆◇◆
「だからね、自分は言ってやったんだよ。おととい来いってさ」
アキレァは酒場・宵闇の華亭のテーブルで盛大に肉にかぶりついた。
差し向かいに座っているのは、ガラの悪い悪党だ。だが、料理には何の罪もない。
「さすがですねぇ」
と、目の前の悪党が言う。彼は密輸業を営む男で、たしか裏町のブロックマルツとかいう猫爺の子分だったはずだ。
「アリミナってゴーレムマスターを抱え込んでアリーナでゴーレムを戦わせようって話も出てるけどね。自分は感心しないんだよね」
「へぇ、どうして」
「アリーナの偉い人が言うにはさ、ゴーレムなら派手にぶっ壊れても直せるし、壊れりゃ観客がもっと沸くだろうって言うんだけど、そういうのって、ちょっと違うだろう? 鍛えた華麗な武術で沸かせるのがアリーナ剣士だよ。血を出しゃいいってもんじゃない」
「いやまったく」
「ゴーレム同士とかゴーレム相手のバトルが悪いってんじゃあないよ。アリミナさん? のゴーレムはそりゃあたいしたもんだった。自分だってデカブツに遅れは取らない自信はあるさ。ぶっ壊れりゃ沸くって考えが安易だって話。行きつく先は見世物の殺し合いだよ。何百年前の話だっていう」
わかる? と骨をぷらぷらやるアキレァに、悪党氏はさもそのとおりと言わんばかりに頷いてみせた。
そしてその後で、さて、と切り出す。
「実はそのアキレァさんに一つお願いがありまして」
彼のお願いは単純明快だった。
用心棒になってほしいと言うのだ。それも、ほんの一日だけ。用心棒というよりボディ・ガードだろう。
「名が売れてる人がいいんすわ」
と、彼は言う。
「取引がありまして、そこに立っててくれるだけでいいんです。相手側が、こりゃかなわねぇ、って思ってくれるような感じで」
「フゥン」
アキレァは思案する。そこまで買われるのは悪い気分ではない。
「取引相手ってのは? あぁ、いや、どんな奴かを教えてくれればいい。名前を聞いても、どうせ解からないから」
「それが……ちょっといわくつきで。子供も殺すような悪党なんです」
「ふん」
彼女は鼻を鳴らして、鳥の小骨をぱきっと噛み折る。それなら遠慮はいらない。
「もし交渉が決裂したら?」
「そりゃもう……やっつけてしまって構いません」
悪党は、もっと悪い悪党とやらについてもう二三、悪事を語ってみせた。
一方そのころ、西側の商業港の近くにある小さな酒場で、レビィア・トピアスもやはり奇妙な会合を持っていた。
「用心棒、ねぇ」
火の入った帆立の貝柱が入ったいい香りのピラフにスプーンを突っ込んで、レビィアは眉間にしわを寄せた。
「レビィアさんなら、取引の間相手も震えあがって何もしてこないと思うんですよ!」
太った商人がそう力説する。
そういったオファーを受けたのは初めてではない。鮮血の赤兎と言えば(その名前が本意かどうかは置いておいて)それなりに有名なのだ。
彼女は自分をあくまでアリーナの剣士であると自認していたから、ウチで働かないか、といった話はすべて断っていた。
レビィアには弟がいる。足の不自由な弟で、縫製服飾を生業として過ごしていた。黄金剣とペアの樹法具である黄金水の靴を手に入れたおかげで生活に不自由はなくなったが、それでもできるだけ一緒にいてやりたい。だから長時間拘束される仕事は引き受けたくなかった。
しかし、「一日だけでいいんで」という商人の言葉は、彼女にとって一考に値するものだった。
そこまで困窮しているというほどではないが、拘束なしでの用心棒ならそんなに悪い話ではない。
くだんの弟ドロイに新作用に生地を買ってやれる。彼の才能はたいしたものだ。新作発表の機会を、お金のために逃したいとは思わない。彼がいつか自分の手から羽ばたいてゆくときのために、準備だけはしておいてやりたいではないか。
とはいえ、レビィアには気になることがあった。
「相手はどんな奴なのさ」
「それが……」
商人は声を潜めた。
「とんだ悪いやつで……無慈悲な人斬りを雇ったって言うんです。子供も殺すようなワルで……」
「そりゃ悪いね」
レビィアは胸の下で腕を組んだ。子供を殺すのはよくない。
「そんな奴なら、レビィアがいても殴りかかってくることだってあるんじゃあない?」
「ま、まぁそうかもしれませんね」
「その時は……やっつけちゃうよ?」
レビィアは不敵に笑うと、貝柱のピラフを口につっこんだ。
遠慮なく殴ってもいい相手なら、アリーナの“鮮血の赤兎”は無敵なのだ。
◆◇◆
レイとラスグィルは、その日のうちにシルヴァーの行方を掴んでいた。
彼女らには商売柄情報網があったし、“現場”であるアリーナにも(ラスグィルが言うには)はっきりとした痕跡が残されていたからだ。
だから彼女らは、ベッドの脇で小さくなって座っている身の丈2ミル半もあるような巨漢の獣人が「どうしてここが」と消え入るような声でつぶやいたとき、「いろいろ」とだけ答えた。
「あなたが、シルヴァーさんですわね」
「……」
「その額の銀の毛並みは特徴がありますもの」
裏町近くにある施療院“ラズライト”は、深夜営業するベルゼ・カロンという医者が経営する、いわゆる闇医者だ。
そこに、サックスもシルヴァーも二人ともがいた。
小柄なサックスは半死半生。肋骨が折れており、各部に裂傷。打ち身。その他もろもろ。
シルヴァーのほうも同様で、あちこちに鋭い切り傷。だが分厚い筋肉と毛皮が彼を守ったようだ。サックスほどの傷ではない。
「見せたまえ」
レイとラスグィルをここに案内したドクトル・ハニィマシューが眉をひそめてシルヴァーのほうに近寄った。シルヴァーは力なく首を振り、後ずさる。
「おれはいい」
「よくはない。ベルゼクン、彼に治療は?」
「頼まれてないからね」
問われた鬼人種風の衣装をまとったベルゼ・カロンはにこにこと首を振る。
「こういう商売だと、あまり深入りしない方がいいこともあるんだ」
「いいから見せたまえ! あたしは医者だよ!」
鼻を鳴らして、ドクトルがぐいっとシルヴァーの腕を取る。
「バートさんも心配してたわ。大丈夫。料金は彼に請求するし、あなたのことも守るから。わたしたちのことはいいから、バートさんは信用してあげて」
レイが助け舟を出すと、シルヴァーはうなだれた。
「親方が」
「そう。彼に頼まれて、あなたがたを探しに来ましたの」
「それにしても……高名なアリーナ戦士をここまで痛めつけるなんてね」
ドクトルが医療カバンを開けて呟いた。ベルゼもいそいそと治療の準備を始める。彼だって、本心では治療すべきだとは思っていたのだ。
「そうでしょうとも」
ラスグィルはその人道的行為の現場から少し離れて、椅子に脚を組んで座ると両手の指先を合わせた。
「その傷は、やはり高名なアリーナ戦士、サックスさんによるものですものね」
「……そうだ」
シルヴァーは一度はっとしたように顔を上げ、それから牙の間からうめくように肯定し、またうなだれた。
「こいつ以外にだれがおれをここまで追い詰めることが出来るもんか」
「一体どうして」
ドクトルが傷口を見ながら言う。
「確かに、鋭い刃物による傷だ。しかしどれも急所を外している。……もちろん、強靭なキミでなければどれもが致命傷だったかもしれんがね」
「仕方なかったんだ!」
シルヴァーは頭を抱えた。
「仕方なかった! サックスは悪くない。悪いのは……おれなんだ」
シルヴァーは続けた。
アリーナの花形戦士であった彼のもとに、ある依頼が舞い込んだ。
用心棒になってほしい、という依頼だ。
ほんの一日。取引の間だけ立っていてくれればいい。そんな簡単な依頼で、かつ、破格の報酬。
そのころ、シルヴァーには金がなかった。
別に親方であるバート氏がけちだったわけではない。ただ、シルヴァーは大食漢だったし、少々知恵が回らない部分もあった。色街・百合お化け通りである女に騙され、結構な額を持ち逃げされていたのだ。
彼はそれ自体は後悔していないし、まぁいいか、と思っていた(田舎の親が病気で、と語る娼婦の涙が、サックスの言うような完全なウソだったとは思っていなかった)のだが、金がなかったことは確かだった。
そこで、シルヴァーは二つ返事でこの依頼を承諾し、やくざものと一緒に取引会場とやらに向かうことにしたのだった。
ところが、馬車に乗せられて着いたところは見慣れたアリーナだった。
ただし、深夜。
そして目の前にいるのは、親友のサックスだったのだ……。
「奴らはおれたちに戦うように命じたんだ。さもなくば二人とも殺す、と」
シルヴァーは、いまだ意識のもどらないサックスの脇で涙を落した。
「……奴ら、とは?」
レイが聞き、ラスグィルは口をはさんだ。
「見当はついていますわ」
◆◇◆
酒場・一角獣の森亭。
本来であれば、ノワのような盗賊が足を踏み入れるような場所ではない。
調度品は高級で、出される酒も一級品。ステージでは美しく着飾った男女の芸人が、ゆったりとした音楽を奏でている。ヴァージナルと声楽のペアだ。
集まるのも紳士淑女で、いつものノワであればまったく場違いだっただろう。
しかし、今は違う。
彼はここに、仕事で来ている。盗賊ノワにとっての仕事といえば、すなわち盗みである。
ノワは見事な刺繍の入った黒いチュニックをまとい髪を撫でつけて、ポケットからはご丁寧に絹のハンカチをのぞかせている。彼は三人目のご婦人の誘いを丁寧に断り、鷹のような目で獲物を探した。
彼は義賊ではないが、盗みに入るなら貴族の家がいい。同じ苦労をして錠前を外し金庫を開けるなら、中身は多い方がいいに決まっている。
油断した間抜けな貴族がいれば、彼から鍵をすり取る。それができればまったく仕事は簡単だ。そうでなくても、懐から財布を頂戴できるだけでもいい。
「アリーナなんて所詮はお遊びですよ」
ひそひそ声で話す男に気付いて、ノワはそちらに耳を向けた。彼ほどのものであれば、意識を集中させれば雑音から特定の会話を聞き取ることもできる。
話す男は同業者だ。
確か、ブロックマルツのところの若い衆。
奴の仕事の邪魔をすれば面倒なことになるかもしれない。裏町組合では、組合員同士の盗みはご法度だ。
そいつは若い貴族に熱心に話しかけている。
「アリーナ剣士同士の真剣勝負。命のやり取りですよ。男なら気になるでしょう?」
「殺し合いなんて」
「ただの殺し合いじゃありません。アリーナの花形剣士同士です。つまり、あのアキレァと、レビィア・トピアス」
「はは。まさか」
「気になりませんか? あの二人が真剣で立ち会って、どっちが強いか」
ノワはタバコ売りの女性に近づくふりをして、二人の背後に近づく。同業者の男はノワに気付いていない。
「そりゃあ、鮮血の赤兎だろう。この間は引き分けだったが、あいつは人種相手の時は黄金剣を使わないからな。ハンデマッチで引き分けにしたようなものだ」
「それはどうですかね? アリーナでのアキレァの動作には、パフォーマンス用の無駄が多いって言う戦士もいますよ」
若い貴族は興味をそそられたようだった。
「面白いね。賭けようか」
「是非。まぁ、相手は私じゃないですが……」
「しかしどうやるんだい」
「それは企業秘密で……。まぁ、アイドル気取りの娘っ子ですから、どうとでも」
同業者の男は、若い貴族にメモ書きを握らせる。
「ここで、やるんです。興味があればぜひ……。もちろん、他言無用でお願いしますよ」
ノワは同業者を見送り、それから若い貴族の背後についた。
いい加減に出来上がっている貴族の心は、どうやらすでに夢の対戦に飛んでいるようだ。
下手なスリはわざとぶつかったりしてスキを作るが、ノワはそんなことはしない。自分でスキを作るなんてリスクでしかない。ノワは油断なく周囲を確認し、貴族がワインを口に運んだ瞬間、素早く右手をひらめかせた。
それからゆったりとカウンター席に戻り、左手でさっき買ったタバコを火をつけずにもてあそびながら、右手で自分のポケットを確認した。
さっき同業者の男が渡していたメモ紙と、貴族の財布、それから小さな鍵を確認する。
ノワは決して慌てずワインをもう一杯楽しむと、さっきの同業者が別の貴族に話しかけているのを眺めた。
あの様子なら、このメモ紙を誰かに流したとしても、それがノワの仕業だとは、あの猫爺のところまでは伝わらないだろう。
売らずに渡しただけなら、そもそもとがめられる筋合いもない。何も知らずにすり取って落としたも同じ。あの間抜けな若い衆は、ノワに気付いていない。
妙な企みしやがって、と、ノワは思う。
と、いうのも。
「あのうさぎさんを殺されてたまるか」
ノワはレビィア・トピアスのファンだったのだ。
◆◇◆
探偵がノワから手に入れたメモ紙をもとにサックスとシルヴァーの元にたどり着いていた頃。
渦中にあるレビィア・トピアスとアキレァは、酒場・虎の鰭亭で豪華なメニューを楽しんでいた。
「やぁ、ずいぶんと羽振りがいいじゃないか」
「そっちこそ」
アキレァは山盛りの仔牛のローストを。レビィアは魚介を使ったたっぷりのサラダを。そこそこ高めのメニューを出す虎の鰭亭のなかでも宴会メニューとしてさらに若干高価で豪華な料理を、モリモリと胃袋に詰め込んでゆく。
二人を眺めるドロイ・トピアスは健啖家二人を前に押され気味だ。
「ドロイ、ニンジンも食べなさい」
「え? いや、いいよ……姉さんが食べなよ」
「はっはっは。遠慮するなドロイ。大丈夫だ。このアキレァさんがおごってやろう」
「いや……結構です……ニンジンくらい別におごってもらわなくても……」
「バカ言え。ここのニンジンはいいものだぞ」
「どういうところがですか」
「赤い」
「なるほど、これは赤い」
「赤さはどうでもいいっ! ドロイ、なんでも食べないと強い子になれないんだぞ」
レビィアは自分の皿に移された赤いニンジンのバター焼きをドロイの皿に戻した。
「支払い、大丈夫なんだろうな」
虎の鰭亭の魚料理担当であるシェックが、どん、と生ニシンの酢〆を置きながらうさんくさそうに二人を見た。
「あとで姐さんにどやされるのはおいらなんだぞ」
「心配いらない」
アキレァは胸を叩く。
「ちょっと割のいい稼ぎがあってね。レビィア。なんならゴチソウしてやろうか」
「馬鹿言え。アキレァに御馳走になるほど落ちちゃいない。こっちだって割のいい稼ぎがあったんだ。ドロイ、遠慮しないで食べていいんだからね」
「……」
ドロイは皿のニンジンをさりげなくどかして、眼鏡の奥の目を細めた。
「割のいい稼ぎって?」
「用心棒さ」と、アキレァ。「なんでも悪いやつ相手の取引で、有名な戦士の用心棒が欲しいとかでね。一日だけ」
「フーン」
レビィアは鰊を取り分けてシェックにもう一杯注文する。自分には甘めのワインを。弟には涼しげな柑橘系のジュース。
「似たような話知ってる」
レビィアは自分に依頼してきた商人の顔を思い浮かべた。用心棒か。
「流行ってるのかな」
レビィアはそう言うと、弟の皿にニンジンを戻す作業に戻った。
◆◇◆
その夜、レビィアは商人に連れられて馬車に乗り込んだ。
「先生、今夜はよろしくお願いします」
「先生なんて」
と照れるレビィアだったが、なんとなくものものしい雰囲気は感じていた。
馬車は一頭立てのたいして大きいものではないが、幌ではなく屋根付き。窓には分厚いカーテンがかけられている。レビィアの向かいにはくだんの商人が座り、絶え間なくなにかをしゃべり続けていた。
ソーンの石畳はでこぼこしているので、蹄の音と車輪の音は結構響く。まして深夜だ。
「けっこう揺れるね。取引はどこで?」
「港です。もう少し」
レビィアは黄金の大剣を引き寄せた。なんとなく危険を感じたのだ。虫の知らせ、とでも言うべきか。ドロイが縫ってくれた、フチに刺繍の施された黒いマントをかき合わせる。
「何か?」
「あんた、レビィアに何か隠してないか?」
金色の目をすっと細める。商人はごくりと喉を鳴らした。
「まさか、何も……」
と、そこで、馬車ががくんと揺れる。
「?」
「やや、もうすぐです、もうすぐですよ」
「話は終わってないよ」
「いや、終わりですよ」
レビィアの鋭い耳が、馬車の背後で何か重い扉が動く音をとらえた。商人が馬車の扉を開き、転がるように外に出る。レビィアもそれを追ったわけではないが、ことさらにゆっくりと、しかし油断なく馬車を降りた。
「あれ……ここは……」
レビィアはきょろきょろする。
港ではない。
そこは見慣れた、いつものアリーナだった。
「どういうことよっ」
レビィアは思わず商人に食って掛かった。しかし商人の脇から完全武装の男が二人、立ちふさがる。すでにアリーナにいたのか。その後ろには武装した連中がずらり。
剣闘用のアリーナは最大よりも狭い。アリーナの多くの客席は可動になっており、催しに応じて大きくしたり小さくしたりできるのだが、今はごく狭くなっていて、直径10ミルほど。アリーナ内は樹法の光で明るく照らされているが、客席は暗くてよく見えない。
「どうもこうも。お話の通りですよ。取引の……用心棒」
「港って言ってたじゃない」
「そうでしたっけ? いや、手違いがあったかもしれませんが……やることは同じです。相手の用心棒が出てきます」
例の無慈悲な殺し屋か。
なるほど、用心棒かと思ったら、殺し屋と戦わせるために雇われたってわけだ。レビィアは思った。子供を殺すような殺人鬼が相手なら、まぁいいだろう。やりくちは気に入らないから後でたっぷり仕返しさせてもらうとして……。彼女は黄金剣を握り直した。
しかし、レビィアはぽかんと口を開ける。
アリーナの対戦者側から出てきたのは、つい夕方一緒に虎の鰭亭でバカ騒ぎをした相手、アキレァだったのだ。
「アキレァ?!」
「あれ。レビィアじゃないか。どうしてここに」
「それはこっちのセリフよ!」
「いや、自分はここに残虐非道な悪いやつがいるっていうんで、用心棒にね」
「流行ってるみたいね」
「どうも、そのようだね」
アキレァは彼女の後ろを見た。やはり屈強な男たちが完全武装で立っている。
「あれが、残虐非道なもっとあくどい悪党?」
アキレァは自分を案内した悪党氏に尋ねた。
「そのようで」
「子供も殺すような?」
「そうですね」
「……バカを言え! あいつにそんなマネができるか!」
アキレァは珍しく柳眉を逆立ててよく通る美声を張り上げた。セリフを覚えることが出来れば舞台役者にもなれるだろうに、と、レビィアは思う。前に演劇風の出し物をやったとき、彼女はセリフを覚えられずすべてアドリブでこなし、いや、こなすことができず、劇はめちゃめちゃになった。その時の悪役はシルヴァーで、あの大男はきちんとセリフをすべて覚えたのに。
ぱっ、と明かりがともる。
見れば観客席には身なりのいい紳士淑女が並んでいる。護衛にはゴーレムすら見えた。
「では!」
突然商人が声を張り上げる。
「今夜のメインイベントです! 戦うのは……“鮮血の赤兎”レビィア・トピアス! 対するは“華麗なる肉食獣”アキレァ!」
商人(レビィアはこいつが商人ではないとうことだけは確実だ、と、思ったが、名前を聞いていないので他に言いようがなかった)と悪党氏を含む連中が、ざあっと壁際まで下がり、レビィアとアキレァに武器を突き付けた。アリーナの中央に二人。レビィアとアキレァだけが残される。
アキレァは片眉を上げてレビィアを見て、レビィアもそうした。
「この闘技場を生きて出られるのはどちらか一人! アリーナの華の真剣勝負でございます!」
客席がわっと沸く。
殺せ! 殺せ! 血を流せ!
悲鳴を上げろ! 這いつくばれ!
戦え! 殺し合え!
「さぁ、先生」
商人だった男は、猫なで声をかけた。
「やっつけちまってくださいよ」
レビィアとアキレァは、お互いに武器を構えて対峙した。
◆◇◆
アキレァとレビィアは長いこと動こうとしなかった。
「困ったね」
アキレァは呟く。彼女の通る声は、この下品な歓声の中でもきちんと、レビィアの耳に届いた。
「どうやら、年貢の納め時みたいだ」
「どうして?」
「この間の試合とは違う。キミには黄金剣がある。持ち主に軽く、敵に重い。試合の時はなかったからね。いささか分が悪いや」
「何言ってるのよ」と、レビィア。「この観客相手にパフォーマンスはいらないでしょう? 客席の女の子にウィンクしなけりゃアキレァの勝ちだった」
「だって骨付き持ってたから」
「それが目当てだったの?!」
「さぁね。兎に角、負けるのは自分だよ。キミにはドロイがいるだろう。帰りたまえ」
「バカ言わないで。ともだちを殺して帰ってどんな顔してドロイに会えばいいの」
「知らんぷりしときなよ。わかりゃしない」
「あの子、ああ見えて鋭いの」
「キミと違うね」
「アキレァともね」
なかなか戦おうとしない二人に、武装した連中の輪が少し縮められる。その数ざっと二十人。親玉と思しき悪党氏と商人氏がいるから二十二人か。アキレァはじろり、とそっちを見た。もちろん、追加がいないとは限らない。客席にはゴーレムだっているのだ。
「戦わなければ二人とも、というわけかい」
「その通り」
と、悪党氏。
「困るんだよなぁ。いつもやってることだろう?」
「何を」
「真剣勝負ってやつをさ」
ほォン、と、アキレァは合点がいく。さっきから耳障りな歓声が何を期待しているのかが(ようやく)呑み込めたのだ。
彼らは普段のアリーナでの戦いに満足していないのだ。
してみると、ゴーレムのぶっ壊し合いを企画した興行主の言葉もあながち間違いではなかったのかもしれない。
「いや、自分たちの不徳といたすところだね」
「何が」
レビィアはむすっと言う。
「彼らは真剣勝負をお望みなんだよ。つまり、殺し合いをさ。普段の自分らの真剣勝負じゃお楽しみいただけなかったと」
「知ったことじゃないわ!」
「悪党クン。ひょっとしてなんだが、シルヴァーとサックスにもこれをやったのかい?」
「え?」
レビィアは目をぱちぱちして悪党氏を見た。悪党氏と商人氏は顔を見合わせ、頷く。
「あの二人も、なかなか戦おうとしなかったぜ」
「当たり前よ! あの二人は親友同士だったんだから!」
「あの狂暴な獣人が?」
「何もわからないでぇ!」
レビィアは地団太を踏み、アキレァはすっと彼女の脇に立った。
「諸君はどうやら、アリーナというものに詳しくないらしい。昔はどうだったか、未来はどうなるか知らないが、今はここは楽しい場所だ。我々は残念ながら、諸君のお望みの楽しみは提供できそうにない」
アキレァは芝居がかったしぐさで長剣を胸の前で立ててみせる。
「さて、お集りの紳士淑女様方。アリーナで催されるバトルにはいろいろある。剣闘、拳闘、馬上槍試合、戦車戦……その中には、闘技場のあちこちに障害物や罠を仕掛けた変則バトルもあるんだ。自分もこの“鮮血の赤兎”もベテランだからね。もちろんやったことがあるよ」
周囲の輪が一段小さくなり、レビィアはアキレァを見もしないで黄金剣を担いだ。
「多勢に無勢じゃない」
レビィアが言う。
異変を感じた商人氏と悪党氏が後ろに下がり、武装した連中がさら刃をぎらつかせて輪を詰める。これ以上は脅しではないだろう。だがしかし。
「なぁに。我々アリーナ剣士にとって、罠ってのは……踏み破るもんなんだよ!」
「その通り!」
どしゃっ、と、客席から身なりのいい若い男が投げ込まれた。
はっとして見上げると、そこにいたのは2ミル半はあろうかという毛むくじゃらの巨漢。その隣には両手首からナイフをひらめかせた小柄な男。
「シルヴァー! サックス!」
「地獄から戻ってきたぜ!」
シルヴァーは胸を叩くパフォーマンスを決めて、吠えた。
「なんだってんだ?!」
「それはわたくしがお答えしますわ」
混乱する客席の後方やや高い位置で、ぱっと樹法の明かりが灯る。そこにいたのは、青い優雅なドレスをまとった女と、羽根つき帽子をかぶり細剣を下げた女の二人。
「ちょっと、やっぱりショウアップが過ぎるって」
「黙って。いいところなんだから」
「へんにかっこつけなんだから……」
ラスグィルはレイを黙らせると、光源としたまことの銀のナイフを振った。
「アリーナ剣士をだまして戦わせ血なまぐさい見世物にしようという企みは、今夜でおしまいですわ。シルヴァーさんは相棒への愛情ゆえに、サックスさんを殺すことが出来なかった。半死半生でしたけれど。あなたがたは確認を怠りましたわね。親分さんに見放されるわけですわ」
「な、なに……」
「シルヴァーさんは急いでサックスさんを施療院に運び、お二人は一命をとりとめました。見かけによらず知恵の回る方ね。もし大っぴらに姿を見せれば今度こそ殺されると思って、闇医者に隠れていた。ま、わたくしの目からは逃げられなかったわけですけれど。でもおかげで、ドクトルとニレルさんに出会うまで生き残ることが出来たわ。お二人……それから名前は伏せますけれど闇医者さんの尽力で、こうしてここにいらっしゃる」
「まだあちこち痛いが……借りを返すくらいはできるさ」
サックスは姿勢を低くしてにやりとした。
「さ、すでにガルム・ウォレス卿にも通報済み。ブロックマルツ氏は知らないとおっしゃる。観念しなさいな」
「満足した?」
「まぁね」
いそいそと高いところから降りるラスグィルをよそに、客席の貴族たちは大慌てだ。先を争って出口に殺到する。
「逃がさないわよ!」
レイが電光石火、腰からフリントロックピストルを抜いて足元に発砲すると、護衛のゴーレムが動き出した。しかしそのゴーレムに、シルヴァーが組みつく。
がっしと正面から腰を掴み微動だにしない。ぎしい、と、ゴーレムの関節がきしんだ。そこにサックスが飛びつく。ゴーレムの背中を駆け上がり、うなじの隙間の部分にナイフを叩き込んだ。
その間に貴族たちはゴーレムを捨てて出口に急ぐ。なにせ捕まれば“コト”だ。必ずしも法を犯しているわけではない。とはいえ罪を犯していないとも言い切れない。黒王女の鋭い目にさらされれば、もうその先はないだろう。相手が“ちび宰相”ならなお悪い。彼らの中には、プロタ・リズマの貴族や議員でない者もいる。外交官やその息子など。悪名高い“ちび宰相”なら、使い道はゴマンと考え付くはずだ。
その彼らの前に、今度はアリミナのゴーレムが立ちふさがった。
「アリミナクン。殺しちゃだめだよ。生きていればなんとかなるけどね」
ドクトル・ハニィマシューが腕組みのまま白衣を翻し、まるで悪の親玉のような顔でふはははは、などと笑う。逃げようとする貴族の若者たちには実際そのように見えたかもしれないが、ゴーレムマスターであるアリミナはうんざり。
「ゴーレムの戦いも、新しいアリーナの出し物ですよ。どうぞご覧になって行ってください」
礼儀正しくアリミナは言って、可能な限りやさしく“なでる”ように、ゴーレムに命令した。
客席が突然の大混乱に陥り、レビィアとアキレァはぽかんとする。
悪党氏と商人氏も同様だ。
二人を包囲していた連中(こちらは客席とは違う。正真正銘の犯罪者だ)は刃の向ける先を探している。
そこに客席から、アリーナ興行主であるバートが身を乗り出して叫んだ。
「大丈夫か、レビィア、アキレァ!」
「やぁ、バートさんじゃあないか」
「何がやぁ、だ。助けに来たんだ! 俺の大事な楽しいアリーナを、こんなことに使われてたまるかよ!」
「なるほど。素敵なセリフだ。心に刻むよ」
「覚えてられないくせに」
アキレァはようやく事態を飲み込み、レビィアも苦笑する余裕が生まれた。
悪党氏と商人氏はぎろりとふたりをにらみつけ、武装した手下に向かって叫ぶ。
「そいつらをとっつかまえろ! 人質にするんだ!」
ざっ、と彼らが再び白刃を二人に向けた。バートがしまった、と口を押さえ、レビィアとアキレァは顔を見合わせる。
「そいつらを助けに来たんだ。なら人質に取れば逃げられる!」
「ふぅん」
ちらりと、口を押えておろおろするバートを見上げ、言う。
「こいつら」
「やっつけちゃって、いいんでしょ?」
◆◇◆
「いやぁ、ひどい目にあったが、めでたしめでたしだったな!」
アキレァは柔軟体操をしながら、傍らのバートに笑いかけた。
結局あの後、アリーナに踏み込んだルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオ率いる官憲隊によって悪党どもは一網打尽。彼らの親玉だったはずの裏町のドン、ブロックマルツは、知らぬ存ぜぬを決め込んだ。
観客だった貴族たちがどうなったかは、アキレァたちの知ったことではない。なんらかの政治的取引があったのかもしれないが、少なくともただではすむまい。
レイ・セラインとラスグィル・ダルジェエリングは、わが仕事は完了せり、とばかりに満足げにアパルトマンに帰って行った。事件そのものが報酬とはよく言ったものだ。
シルヴァーとサックスの本格復帰はもうしばらく先になるだろうが、そう遠い話ではあるまい。
バートは腕を組んで、余裕しゃくしゃくのアキレァを見やる。
「ずいぶん余裕じゃないか」
「余裕? そう見えるかい?」
ゲートが開き、明るい歓声が聞こえた。
霧は晴れ、空は青い。
ニギニギしい呼び出しの声が響く。
「本日のメイン・イベント!」
アキレァは刃引きした長剣を二、三度振ってから鞘に納めた。
「命なんてかけなくたって、アリーナ剣士はいつだって、真剣勝負さ」
にっと笑って、歩き出す。
向こうから出てくるのは、赤毛の兎獣人少女。
「“鮮血の赤兎”レビィア・トピアス! 対! “華麗なる肉食獣”アキレァ!」
レビィアはフンスと鼻を鳴らし、アキレァは観客にコールを要求し、バートは腕組みのまま満足げに頷いた。
わあっ!
双子都市ソーンのアリーナに歓声が上がる。
こうでなくっちゃ!
END
Novel.hirabenereo
Tweet Follow @twoq_jp