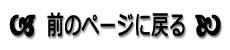●エストリフォの“まほう”
【登場人物】
・トビア・サンチェス
・エイカ・ロロノトリ
・シエラ
・オルヴァ
・ファコン・ソルフィネア
・エルルカ
・ルー
・リーズ
・エストリフォ(NPC)
・ミニジン(NPC)
・アステール (名前のみ)
・エレナ・ウォレス (名前のみ)
・サイウォー・ドレシス (名前のみ)
・ルミア・バリシス (名前のみ)
・ヴェステルナ(NPC) (名前のみ)
・メシュ・メシュ(NPC) (名前のみ)
「樹法。そはいかなるものか」
久しぶりに教壇に立ったトビア・サンチェスは、曲がった腰に左手を回して精一杯声を張った。
オーリエル学院の講堂は広い。
日程によっては、ここは西側の議員たちが議事堂として使うこともある。と、言うよりも、本来はこの建物は王太子府であり、それを“ちび宰相”メシュ・メシュが学校として改装してしまった格好になっているのだ。
すなわち、次代を担う若者たちを育成するために。
この試みはよく理解されていなかったが、トビア・サンチェスはその数少ない理解者の一人だった。
オーリエル学院は、白王女エストリフォによって設立され、そこで学んだ若者たちは、いずれプロタ・リズマの中枢に関わるようになるだろう。
そうなった時にまだ次の王が決まっていなかったら。
これは大きな差として、黒王女と白王女の勢力争いに関わってくるはずだ。
現状は黒王女派の勢力の方が強いが、五年後はどうなっているか分からない。メシュ・メシュはやり手だ。彼女はこの二人の争いに決着をつける最短の手段である、両王女によるエルディカ親征を引き延ばし続けている。
先に最深部に到達したほうが勝ち、というルールは分かりやすいが、分かりやすければいいというものでもない。
目の前に座っているオーリエル学院の有望な若者たちは、あるいは源樹に頼らない国を作るかもしれない。
そうなったらわしはお役御免だな。
トビアは思った。
「わしは、王立樹法研究院のトビア・サンチェスだ。毎日毎日、樹法のことばかりを研究している。専門は、樹力と樹法を物体に焼き付ける樹法具だ」
トビアは自己紹介した。
彼がなぜここに立っているかというと、つまり樹法についての講義をして欲しい、と、頼まれたからだ。
オーリエル学院はまだ生まれたばかりで、生徒数に対して教員数が不足している。特に樹法使いは徒弟制度に近い形で教わることが多かったので、体系的に教えることができる人材は稀だった。
“王立”樹法研究院としては、この頼みを無碍にも出来ない。最初は物腰柔らかなエレナ・ウォレス嬢に頼むつもりだったのだが、彼女の父が反対し、また彼女自身も外に出ることを望まなかったため、たらいまわしの挙句にトビアに白羽の矢が立った。
そうなると現金なもので、研究員からも数人が彼の講義を聴くために生徒に混じって同席している。どうせ来るならお前らがやればいいんじゃないか、と言ってもエイカ・ロロノトリなどは「僕のやり方は特殊ですから」などと抜かすし、シエラは「私はおしゃべりはちょっと……」と言う。
一緒に来ているオルヴァは、助手の席にも座らず生徒に混じって面白そうにこっちを見ているだけだ。奴は当てにならない。
「本来わしは研究者であって講義する側ではないんじゃが、そちらの学長さんに頼まれて、今日は諸君に樹法の基礎を教えるためにここに立っておる。しらふでな」
「これは珍しいことなんだよ。トビアさん……トビア先生はね、いつでもお酒の匂いをぷんぷんさせてるのさ。それも、安いやつ……あんま儲からないからねぇ、私たちって」
オルヴァが披露して生徒たちが目をぱちぱちする。トビアは彼に対する評価を変えた。悪い方に。
講堂の左手側では、眼鏡の小人種の教師が熱心にメモを取っている。彼女はこの学校の教師として雇われているミニジンという女性で、トビアをここまで案内してくれた。
ミニジンは樹法について知っているが、樹法使いではない。
「オホン」
空気を変えるべく、トビアはひとつ咳払いをした。
「諸君の中には、ここに来るまでに樹法を使えるようになっている者もいるだろう。樹法とはなんだ?」
「樹力を操る技術です」
指されてもいないのに、さっと立ち上がってファコン・ソルフィネアが答えた。
「樹力は万能で、あらゆることを行えます。それを操ることが出来るのは、一握りのエリートだけです」
もちろん俺は使えますが、と、彼は言い足した。隣に座っている狸の獣人少女が小さく顔をゆがめる。
トビアは名簿を眺める。聞いている。ファコン・ソルフィネア。エードローエの問題児だ。
「正しい。が、間違ってもいる」
トビアは指摘する。
「樹法とは、あー。ソルフィネア君の言うように、樹力を操る技術だ。樹力、すなわち源樹から発生する不可視の力だな。わしは物質か、あるいは物体、場合によっては生物ではないかと考えているが……それは置こう。もしここに、樹法の祖であるプロンミウスか彼の娘エルディールがいれば是非聞きたいがね」
シエラが小さく首を振る。彼女は星の配置など様々なものから世界の意思、過去の情景、未来の予兆を見出そうと研究しているが、今もって死者の意志を、そのかけらすら見つけたことは無い。人々のおとぎ話に出てくる幽霊やデリド――悪魔の類――は、未だに観測されていない。シエラはあると信じているが、トビアは信じてはいなかった。死体の“死にぞこない化”、つまり、死体が動き出す現象にしても、ノードス化の一種であると結論付けられている。喉などの重要部位に樹力を遮る“墓鉄”や“冷たい鉄”を打ち込むことで妨害できることから、それが樹力によるものだと分かる。魂や意志はそのような金属に阻害されない。もし阻害されるなら、生きている腕に“冷たい鉄”の釘を刺したなら腕が動かなくなるはずだが、そうはならない。痛いだけだ。魂は“冷たい鉄”に阻害されない。つまり、“死にぞこない化”は樹力によるものであり、魂が戻って来て死体を動かしているわけではない。閑話休題……。
「樹法とは、その樹力に命令する技術のことだ。樹法使いになるには二つの才能と、一つの幸運が必要になる。これを三つの才能と言うこともあるが、わしは最後の一つは才能ではなく幸運なのではないかと考えている」
トビアは説明を続ける。
この授業のために、トビアは通常の業務を一旦停止して準備を行った。それは自分の今まで当たり前だと思ってきた理論を再構築するのに役立ったが、それはそれとして寝ている生徒には腹が立つ。もっとも、自分の若いころを思えばあまり大きなことは言えないが。
「まず、周囲の樹力を感じる才能。樹力への親和性だな。これは誰にでもある程度あるはずだ。源樹に近づけば周囲の温度や空気が変化する。これを感覚的に把握する才能。雨の前の湿った空気を感じ取るような才能だ」
樹力を感じ取ることは誰にでもできるし、その感覚を訓練で研ぎ澄ますこともできる。小人種や鬼人種は樹力に対し比較的高い親和性を示すが、個人差の範囲に収まることが多い。
問題は次だ。
樹法を使うには、自分の“まことの名”を見つける必要がある。
これはどこにも書かれていないし、どんな文献を当たっても出てこない。法則性も、少なくとも現在に至るまで見つかっていない。
探す方法は、総当たりだ。
かたっぱしから樹文を試す。
樹文を唱えるとき、術者は必ず先立って己の“まことの名”を宣言し、それに重ねて樹文を唱える必要がある。
樹文の発音は、現在使われているような言語と全く異なるため、ある程度の基礎を覚えたら思いつくものを次々唱えてゆく。樹文が正しく通り樹力が反応したら、それがその者の“まことの名”である、ということになるわけだ。
トビアが才能ではなく幸運と言ったのはそれで、運が良ければすぐに巡り合うし、悪ければ死ぬまで巡り合うことはない。
「だから」
と、トビアは言う。
「樹法使いは限られた存在だが、選ばれたエリートではない。単にツイてただけだよ。よい生まれに当たるのと同じにね」
ファコンは口をとがらせ、狸の獣人……エルルカは背もたれに体重を預ける。
「さて、“まことの名”を知った樹法使いは、これでようやく樹文を覚え始める。最後の才能は、記憶力だ」
樹文は言語であるとされる。される、というのは、これを言語として扱うことができたのが、樹法の祖である“源初の樹法使い”プロンミウスとその娘“反逆者”エルディールだけだからだ。
樹法使いは、樹文を丸暗記して唱えているに過ぎない。
ある樹文は小さな火を起こす。ある樹文は空中に高圧の電気を発生させ、またある樹文は自らの周囲に水を生じさせる。
正しい樹文を正しい発音で“まことの名”とともに唱えれば、樹力はその命令に従って決められた効果を発生させるのだ。出力や調整などは、さきほどの樹力との親和性が関わるという。まったく同じ樹文でも使うものによって出力は多少異なる。樹法研究院でいえば、アステールが強力な破壊の樹法を得意とするが、トビアは異論を持っている。本来、樹法は同じ樹文で同じ効果をもたらすのではないか。アステールは逆に出力を絞るのが苦手で、種火を熾すだけの樹文で焚火を作ってしまう。この違いは何から来るのか。トビアは長年研究を続けている。
いずれにせよ、樹法使いに求められるのは、一つでも多くの樹文を記憶し、正しい発音で唱えることのできるだけの記憶力だ。
「それと、音感だね」
エイカは助手らしく付け足した。
「音痴に樹法使いは難しい。樹文は正しい発音で唱えなければ、場合によっては全くことなる効果を及ぼすことがある」
「それで、新しい樹文が発見されることもあるんだけどね」
オルヴァが茶々を入れ、歌うように樹文を唱えた。彼の指先がぼうっと明るく光る。光は小さく、蝋燭くらいだ。
「これは私が四つ首の大蛇に追われたときに編み出したんだ」
トビアはオルヴァから前にこの話を聞いたときは双頭だったことを覚えていたが、あえて黙っていた。
「閃光を出して目くらましをして、その隙に逃げようと思ったんだよねぇ。レーンがいればよかったんだけど、迷子になっていたから。あわてていたせいか樹文を間違ったらしくて、出たのはこれだった。小さな光だ。ここにはいないけど、サイウォークン……ちゃんが来なかったらどうなっていたことか。でも私はこの、新しい光の術を編み出したってわけさ」
「樹法使いに必要なものを言い足そう。冷静さ、だな」
トビアはじろりとオルヴァを見た。
「かくして、樹法使いは樹文を唱え、樹力はそれに従って様々な効果を及ぼす。ソルフィネア君。先ほどのをもう一度頼む。樹力は?」
ファコンはトビアに指されて、今度はやや渋って立ち上がった。
「樹力は万能で、あらゆることを行えます。それを操るこ……」
「結構」
トビアはそれを制した。エリートのくだりをたしなめられるのだろうと予想していたファコンは拍子抜けする。
「優れた記憶力の持ち主だ。結構結構。樹力は万能。これはよく言われる勘違いだ。樹力は決して万能ではない。なんでもできるような、おとぎ話に出てくる“まほう”など、この世にはない。それはデリドの類だ。あるかもしれんが観測できないので、とりあえずない、とするしかない。夢を見るのは自由だがね」
トビアは厭味ったらしく言うが、別に誰に向けたものでもない。そういう男なのだ。
「樹法にも出来ないことがある。樹法にできることは、何か物体、物質、エネルギー……これらを生み出し、操ることだけだ。物体を空中に浮かせることはできる。火柱を上げ、水を落とし、海水をどかして道を作ることもできる。肉体を変容させ姿を変えることもできるだろう。偉大なるプロンミウスは上空に雲を生じさせ天候すら操ったという。対応する樹文を発見できれば、もっといろいろなことができるだろう。だが、万能ではない。樹法使いはそれを忘れてはいけない」
戒めるような彼の言葉に、樹法研究院から同行した若い術者たちも居住まいをただす。
「プロンミウスの時代から樹法にできないことの最も大きなもの。樹法で触れることのできないもの。それが」
トビアはとん、と自分の胸を指差した。
「こころだよ」
◇◆◇
「樹法かぁ」
ルーはぼんやりとつぶやいた。
講義はその後、いくつかの先生方の実技が続き、既定の時間をややオーバーして終わった。
トビアはリーズの持つゴーレムに興味を示しそれを借りたがったが、彼女は兄弟同然のゴーレムを手放すことはしなかった。ゴーレムが時に意志を持つような行動をとることは報告されていたが、実例は少ないし、理由も分かっていないという。オルヴァ先生の連れた先祖代々という“力”もそうだし、動物が言葉を話す例もあるというが、いずれも現在の樹法の基礎では解明できていない。
「樹法、使いたいのか?」
と、ファコン。
「俺が教えてやろうか」
「使えたらいいですけど、でも言ってたじゃないですか。運もあるって。それに僕は武術の稽古もあるし」
肌を出さない改造制服の襟に顎をうずめて、ルーは肩をすくめた。
「そうだな。ひとには得手不得手や本分ってもんがある。お前はそれでいいんだ。きっとその武術で、誰か立派で高貴な人の役に立つのがお前の本分なんだ」
うんうんと言うファコンに、エルルカがぷっと噴き出す。
「なあにそれ。続いては“俺みたいな”?」
「そうだよ。おかしいか? お前だって取り立ててやれるかもしれないぞ」
「エルルカはぁ……そういうの、あんまし……。そういえばルミアちゃんは?」
「サンチェス先生って聞いたら、やべっ、って言ってどこか行きましたよ」
「なんだそれ。相変わらず不真面目な奴だな」
楽しそうな同級生を眺めて、エストリフォは少し遠くを見た。
彼女はごく幼いころに“まことの名”と巡り合った。
姉であるヴェステルナは早々に樹法使いの道を捨てたので、樹法はエストリフォにとっては数少ない、姉に勝っている部分だ。少なくとも、彼女自身はそう思っていた。
メシュ・メシュからいくつも樹文を学んで、ごく少ない便利な樹文や身を守る樹文を知っている。
しかし幼いエストリフォが、“ふしぎですてきなわたしだけのまほう”を手に入れたときに欲しかったのは、そんなものではなかった。
結局、樹法はエストリフォにとって自信の源になることはなく、自我の礎ともならず、むしろそれをもってしても姉の影にあるばかりの自分を情けなく思うばかりだった。
「ユー、どうしました」
沈んだ顔をしていたのだろうか。そんなエストリフォを、大きな棺桶を担いだリーズが見上げるようにのぞき込む。
見れば、他の生徒たちもまた、エストリフォを心配そうに振り返っていた。
エストリフォがずっと“まほう”で欲しがったものは、結局樹法では手に入らなかった。
ひとりぼっちの小さな女の子。彼女がちょっとばかり便利な力を手に入れたとしても、彼女が自分を憐れんでそこにうずくまる限り、何も変わらない。
樹法ではこころを動かすことは出来ない。
「ううん、なんでもない」
エストリフォは級友たちに微笑んで、小走りに彼らに追いついた。
ファコンはほっとしたように微笑み、エルルカはおどけてエスコートのまねごとをする。ルーは大きな棺桶を背負って遅れがちなリーズに歩調を合わせて彼女が転んだらすぐに助け起こせるように準備している。
誰かのこころを動かすことが出来るのは、決まりきった樹文でもおまじないでもない。
“ふしぎですてきなわたしだけのまほう”。
前に踏み出す、自分のこころだ。
エストリフォは、幼い日に欲しかったものを今、手に入れつつある。
◇◆◇
「素晴らしい講義でしたよ」
エイカがトビアのカバンも合わせて軽々と担いだまま微笑んだ。
「僕も久しぶりに基礎を学び直しました」
「樹法なんて手段にすぎんよ。わしはもう何十年も樹法に人生をささげているが、一部の思い上がった樹法使いが言うような万能感は、研究すればするほど薄れていく」
トビアは楽しそうにかたまって歩く生徒たちを眺めながら言った。
「わしは失われた……“源初の樹法使い”プロンミウスの技法、それを求めて研究を続けているが……我々人種が求めるべきなのは、古い樹法などではないのかもしれんなぁ」
「それは違いますよ、先生。新しいものは、常に古い物の上に築かれるものです」
オーリエル学院の図書館から借りてきた書物を山のように抱えたオルヴァはそう言って、おどけてみせた。
「つまり私たちは、先生の上に立たせて頂くというわけで……」
「なら次の講義はお前がやるんだな」
トビアは鼻を鳴らして、オルヴァは悲鳴を上げた。
Novel.hirabenereo
Tweet Follow @twoq_jp