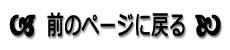●とさかの騎士
【登場人物】
・トニョ・ベルトラン
・ヒルデガルト・リーデルシュタイン
・ラバンニャ
・マロン
・ノダ
・アメリア
・シル
・キャンデロロ
日が暮れ始めていた。
「えい! やぁ! とぉ!」
双子都市ソーンの街外れに、良く通る元気な声が響く。
春の新緑もまぶしいミズナラの林は、今はオレンジ色にきらきらと輝いて天枝の影を落としていた。
双子都市ソーンは千五百年以上の歴史を持つと言われる大都市で、周囲をぐるりと石の壁で囲われているのだが、年々増加する人口を市内だけでは抱えきれず、壁の外の街外れにはのんびりとした農村や宿などの街並みが、小麦畑や林の間に並んでいる。
ミズナラの林が切れたこの気持ちのいい場所は、獣人種の少年トニョ・ベルトランにとって秘密の練習場所だった。
今日は天気も良かった。
トニョは愛用の木剣を抱えると、同居しているヒルデガルド・リーデルシュタインの目を盗んで、朝早くからここを訪れた。
剣術の訓練のためである。
この小さな黄色いひよこ頭には、最強の騎士になるという夢がいっぱいに詰まっているのだ。
「違いますよ。体が開いてる」
その彼の秘密の訓練場に、今日は訪問者があった。
「もっと身体を横にして。剣を前に。左手は後ろ。剣と同じ足を前に」
「こ、こう?」
「そうです。そうすれば斬り込まれる身体を小さく見せることが出来ます」
「小さくないよ!」
「小ささも長所なんですよ」
白い翼をもつ獣人種の少女であるアメリアは、くすりと笑った。
この場所は、彼女にとっても秘密の素敵な場所であったのだ。
同じく街外れにある小さな鍛冶屋で父と兄と暮らしている彼女は、時折この場所で空を眺めて過ごすことがある。
今までは二人が一緒になることはなかったが、このいい天気である。二人の気分が同じになっても何らおかしなことは無い。
かくして二人の鳥の獣人種は、このミズナラの林で出会うことになったのだった。
トニョにとって幸運だったのは、アメリアが彼女の兄同様戦士としての訓練を積んでいたことだ。
それまで型も何もない素振りを、最強の騎士になるための特訓として行っていた彼に、アメリアは簡単な訓練法を与えてくれた。
「アメリアさんも戦士に?」
「えぇ。兄さんが傭兵だから。人のためになりたくて」
「お兄さんも戦士なんだ? 強いの?」
「多分。私、勝ったことないです」
「会えるかな」
「今度、話してみますね」
「やったぁ!」
トニョは素直に喜び、アメリアは彼のやわらかな“とさか”をそっと撫でた。
同じ鳥の獣人でもこうまで違う。獣人種はそもそも姿かたちに関しては千差万別だ。親とすら似ていないことは珍しくない。
「あの、トニョさんは、ご両親は?」
アメリアは控えめに尋ねた。
彼女の父と兄は、実のところ本当の血縁者ではない。アメリアは父がオルオラに行商に出ていた時、雪の中で拾われた子である。父にわだかまりがあろうはずもないが、それでも気にはなる。
アメリアが戦士の訓練を受けたのは、兄と同じように、というのももちろんあったが、いつか自分の出生を確かめに行きたい、という衝動があったからかもしれない。
「親? いないよ」
トニョはあっけらかんと答えた。
「小さいころにはぐれちゃって……猫に襲われてたところをヒルデガルドさんに助けてもらったんだ」
「そうだったんですか……」
アメリアはこの小さな騎士に親近感を覚えたが「私も」とは言えなかった。
今のアメリアには父と兄がいる。口に出して「親はいない」と言うことは、なんとなく二人に申し訳が無かったのだ。
「寂しいですね」
だからアメリアはそう言うにとどめた。
「でも僕はきっと最強の騎士になるんだ。大きくなったら翼が生えて……かっこよくなるんだから」
アメリアは獣人種の姿が年齢で大きく変わるという話については聞いたことが無かったが、この新しい不屈の友人に、それを指摘しようとは思わなかった。
「えい! やぁ! とぉ!」
夕暮れの迫る秘密の訓練場に、元気な声が響いた。
◇◆◇
その日、兎の獣人種であるマロンのお手伝いしている街外れの宿屋には彼女一人しかいなかった。
従業員が、である。
昨日かなり冷え込んだので、今日もそんなにお客は多くないだろう、と宿主は考えて、彼は店を彼女に任せて出かけたのだが、それは裏目に出た。
ぽかぽかした春の陽気に誘われて、宿の一階にある食堂は、食事と呑みの客で溢れたのだ。マロンはてんてこまいだ。
「だからね、酒は毒の一種なんだ」
ラバンニャは機嫌よくたまたま居合わせたかわいそうな犠牲者に講釈を垂れる。眼鏡の奥の目は少しとろんとして、まだ夜も浅いというのにかなり出来上がっている様子だ。
「ただ、ある種の毒は身体にとっていい影響も与えるんだよ。もちろんこのタバコもそう。茄子の仲間の植物なんだけど、乾かして刻んで……」
「麻薬だろ」
付き合わされるノダはいい迷惑だ。
彼女はこの近くの小屋に一人暮らしをしている。家があるので宿に泊まる必要は無い。今日は単に調理が面倒になったので食事に来ただけなのだが……。
「いい指摘だね」
ラバンニャは食い気味に言う。
「そう。麻薬。中毒性があって手放せなくなるが、このタバコという植物は煙にして吸うことで頭をハッキリさせ眠気を覚ます効果がある。橋の見張りなんかに渡せば効果的だろうね。高価だけど。これは駄洒落」
「酔いは覚めないのか」
「覚めるとも」
「そりゃすごい。あんた、いつもそうなんだな」
ノダは助けを求めるように店員であるところのマロンを見て、マロンはそっと目をそらした。
「……」
ノダは大きな胸をテーブルに乗せて頬杖を突き、この新しい友人の講釈を聞き流すことに決めた。
「助けて!」
宿屋に高い声が響いたのは、そんな弛緩した時間帯だった。
宿の客が一斉に戸口を見る。
見れば黄色い鳥の頭を持つ獣人の少年が、白い翼を持つ少女を担ぎ上げている。彼の黄色く柔らかい“とさか”は、今は赤い血にぬれていた。少女の血だ。マロンが真っ先に駆け付ける。
「トニョくんだよね? どうしたの?!」
普段はのんびりしたマロンもさすがに慌てる。トニョはその容貌から、街外れの住人達にとってはよく知られた少年だった。
「アメリアさんが……僕をかばって……一緒にいたんだ……。剣を教えてくれていて……そうしたら、いきなりでかい猫が……」
「とにかく下ろして! 店員さん、水をたくさん!」
マロンの後ろから、店の隅で食事をしていた広人種の女性が走り出る。彼女はケープを脱ぎ捨てて、板張りの床に下ろされたアメリアを診察した。その彼女に、トニョが縋り付く。
「助けて! お願い、助けて!」
「大丈夫。私はシル。治療術師よ。傷は浅く見えるわ。きれいに塞げば跡も残らない。大丈夫だから」
シルは自分が言うよりも傷が深いことに気付いたが、それは言わなかった。何か鋭いもので斬りつけられた傷に見える。アメリアの白いおなかから、彼女の命とともに血がとめどなく流れた。顔色が悪い。出血のせいだろうか。
彼女は集中し、樹文を唱え始める。
まず、自分のまことの名。それから筋肉を繋ぐためのフレーズと皮膚を繋ぐためのフレーズ。内臓は傷ついていない。もし傷ついていたら、どの臓器かを特定しなければ癒せない。
「待った」
そのシルの樹文に、ラバンニャが口をはさんだ。
「まだ傷を塞いじゃいけない」
ラバンニャは吸っていたタバコを注意深くアメリアから遠ざけると目を細めた。
「顔色がおかしい。出血だけじゃない。毒を受けているぞ。傷を塞げば消毒できない」
「毒?」
シルとトニョが同時に悲鳴を上げる。
「おいボウズ。詳しく話せ」
おろおろするトニョに、ノダは屈み込んで視線を合わせると問いただした。
◇◆◇
トニョとアメリアは、ひみつの場所でおおいに訓練を楽しんでいた。
楽しい時間はあっという間だ。
やがて赤い夕日は沈み始め、夜のとばりが下りる。
「そろそろ帰りましょうか」
「うん……でももう少しだけ……」
トニョは木剣を握り、教えられた通りに半身に構える。アメリアは苦笑して翼を広げて伸びをした。でもそろそろ夕食の準備をしないと。
その時だった。
ミズナラの木の陰に巨大な猫科の猛獣が、そのゆらぐ姿をあらわしたのは。
大きさはざっと肩までで1ミルとちょっと。鋭い鉤爪と牙を持ち、目は赤く燃えている。毛皮は黒だが、それは定かではない。そいつは周囲に溶け込むようにまるで陽炎めいて揺らいでいた。
「危ない!」
アメリアは反射的に飛び出してトニョを突き飛ばし、その獣の前に立った。獣はしなやかな四肢を躍動させ、アメリアにとびかかる。とっさに翼を前に出したため喉笛に噛みつかれることはさけられたが、ナイフのように鋭い鉤爪がアメリアの腹を抉った。もし父が作ってくれた鎧を着てきていれば助かったかもしれない。だが、その日のアメリアは単に日向ぼっこをするつもりだったのだ。
「逃げて!」
アメリアは叫んだ。
◇◆◇
「ダスクビーストだ」
ノダは鼻を鳴らした。盗賊として各地で活躍したこともある彼女はその魔獣を知っていた。
世界にはいわゆる“源樹の子”である動物種のほかに奇妙で不思議な能力や姿を持った動物が存在する。それらを称して“魔獣”と呼んだ。彼らは複数の生物の特徴を兼ね備えることが多く、行ってみれば獣人種も魔獣である、と言える。
ダスクビーストはそんな魔獣のなかのひとつで、光を屈折して反射させる奇妙な毛皮と、加えて鉤爪に毒を持つ巨大な豹だ。
「解るか?」
ノダはラバンニャに聞いて、ラバンニャは頷いた。
「ツイてるね」
彼女はそう言うと、ずかずかと酒のボトルの並ぶ棚に近づいた。そこから高価な蒸留酒のガラス瓶をいくつかと、スパイスの入った陶器の小瓶を取り出し、両手に抱えて戻ってくる。マロンは目をぱちぱちした。
「それで一体……」
「“黄昏豹”の毒を除去するのは二段階ある。あの鉤爪には毒腺が入っていて、ひっかいたときにその毒線を残すんだ。その毒は獲物を麻痺させてしまう。奴はたまにもっと巨大な生き物を狩るからね。まず毒腺を取り除く。傷は一つだから……あった。これだ」
ラバンニャはベルトのポーチから取り出した針でくだんの毒腺を取り出し、それから水で洗ったジョッキに酒とスパイス、それからポーチから黄色い瓶を取り出し、数滴たらす。
「これで洗って、あとは傷を塞いで」
「それで大丈夫なの?」
「大丈夫。傷がふさがったら、同じものを作るからがぶがぶ飲ませるように。それで毒は排出されるから」
「わかった」
シルは頷くと、改めて治療の樹文を唱え始めた。
◇◆◇
アメリアの傷は跡形もなくふさがった。
目を覚ました彼女は、トニョを抱きしめてその無事を喜び、突然の事態に緊張していた宿の空気は再び柔らかく温かいものに戻る。マロンはその時来ていた客全員に一杯ふるまった。ラバンニャが使ってしまった蒸留酒一本の半分にも満たない出費だ。彼女の雇い主も納得してくれるだろう。
「ところで」
ノダが振る舞い酒を傾けながら足を組み直すと、小さな鳥の獣人に聞いた。
「ダスクビーストの奴はどうしたんだい? お嬢さんに言うのも何だが、重かったろ。担いで逃げ切れるとは思えないけど」
「そうだ! 一体どうやって……」
アメリアは強い蒸留酒から出来た解毒薬を苦労して口に運んでいたが、震える手を苦労して制御してテーブルに戻した。ラバンニャが「飲みな」とそのカップをつつく。
「ぼ、僕、夢中で……よく覚えてないんだ……」
トニョはお湯で洗ってもらった黄色い“とさか”を振った。
「何があったかは分からないけど、とにかくあいつは逃げて行って、僕はアメリアさんをかついで逃げたんだ」
「フゥン」
ノダはラバンニャと顔を見合わせる。傷を与えた獲物を逃がすような魔獣ではない。だがとにかく、こうしてトニョもアメリアも生きている。
森に現れた魔獣については、一刻も早く狩人や戦士を集めて狩りだす必要があるだろう。
しかしとりあえず確実なことが一つある。
「トニョさん、よく頑張りましたね。あなたがアメリアさんを守ったんですよ」
マロンは言って、未来の“最強の騎士”を称えたのだった。
◇◆◇
その数日後、街外れの川を訪れたキャンデロロは、その口の中に木剣を突き込まれたダスクビーストが死んでいるのを見つけた。
Novel.hirabenereo
Tweet Follow @twoq_jp