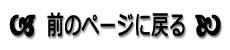●はじめての料理
食事を摂ろうと酒場・虎の鰭亭に訪れたヴェステルナは、運悪く夜営業の仕込みの時間に店へ入ってしまう。
昼の余り物なら残っていたが、料理人兼ウェイトレスのルティンの捌く魚に惹かれたヴェステルナは……。
【登場人物】
・ヴェステルナ
・ルティン
・シェック
・ルシェン
・リア・エイリコ
・シャロン
・アキレァ
・キナ・ラトセラ
・エルルカ
・メイ・アサーシャ
・ギネヴィア
・ムツラ
・ヴェックマン
”虎の鰭”亭。
強い日差しが白い漆喰の壁を明るく照らしている。昼の盛りを過ぎて通りの人だかりはすっかり捌けた後だ。
挑みかかる虎の後足が魚の鰭になった看板が目印の店の前に人影が一つ。
店の前に立った彼女――ヴェステルナは鮮やかに塗られた扉を押し開いた。
中ではカウンターの向こうに長い耳を垂らした女――ルティンが魚の下処理をしている。
「お、ちょっと遅かったな」
ヴェステルナに気づいたルティンが顔をあげる。
「遅い? 今日は特に来ると伝えていなかったはずだが」
「あー、そうじゃなくてさ。単に来るタイミングがちょっと悪かったなって話だよ」
なるほど、と呟いたヴェステルナはカウンターの向こう側であるルティンのほうへ視線を走らせた。
昼飯時はすっかり過ぎており、かといってまだ夕飯には早い。酒場である”虎の鰭”亭はちょうど仕込みの時間だった。
カウンターからだと首を伸ばしても背中しか見えないシェックも料理の下ごしらえをしているところだ。
ヴェステルナは動きを止めて、座ったまま固まる。表情に微塵の変化もない。
「賄いならまだ少し残ってるぞ。どうだ?」
「……いま捌いてるのはいつ頃食べられるんだ」
「うーん、これだけやって終わりってわけじゃないからなあ。少し時間がかかるぞ。陽が落ちるころには絶対食べられるけど」
「じゃあそれまでここに居てもいいか?」
ルティンは眉をひそめた。
「結構かかるんだから、どっか見て回ればいいじゃないか」
ヴェステルナは表情の変わらない仮面のような顔をルティンへ向けた。
「邪魔なら出ていこう。少ししたら戻る」
そう言って立ち上がろうとしたところを、慌ててルティンは呼び止めた。
「おいおい、そうは言ってない! 別に居たけりゃそれでいいよ。でも退屈だろうなと思っただけだ」
ヴェステルナは頭を振った。今度はカウンターにもたれて、ルティンの手元を見ている。
「なんか珍しいのか?」
「料理をしているのを見るなんて滅多にないからな」
腕を組んだヴェステルナはじろじろとルティンの手元を見ている。
ルティンは頭を落とした魚の内臓を掻き出して、桶に溜めた水で背骨についた血合いを丁寧にブラシでこそぎ取っていた。
その作業が終わったところで視線に耐えかねたルティンは、顔を上げた。
「もしかして、自分で料理をしたことないのか?」
「ああ」
「もったいない! 楽しいのに」
ヴェステルナはルティンの驚いた表情を見て、わずかに瞳を伏せる。きっちりと見なければ、誰にも分からない表情の変化。
「まあ習う機会がなかったからな」
黒王女として王位継承権を所持してるヴェステルナは、料理を一生しないという選択を容易に選ぶことが出来る立場だった。
だがそんな彼女の逡巡に気づくもしないルティンは軽々と話を進めてしまう。
「じゃあ魚の捌き方くらい教えるって。自分で釣って自分で捌けるようになると楽しいぞー」
楽しげな表情を浮かべるルティン。
その快活な笑みに、ヴェステルナは泥のような思索の沼に浸かるのを妨げられた。
**
「まあまずは見てろ」
そう言われたヴェステルナは髪をまとめ、使い古しのエプロンを着て、手を爪の隙間まで綺麗にしている。全部ルティンに言われてやったことである。
ルティンは新しくまな板にのせた魚の鱗を落として、頭を落としていく。
それからも滑らかに次々と工程を済ませていく。
「ひれの後ろから刃を入れて、後はすとんと刃を落とすんだ。そうしたら綺麗に頭が取れる」
一つ一つの作業にどんな意味があるのかルティンは説明している。ヴェステルナはそれを横で見ながら、ふむふむと頷く。
しばらくするとまな板には三枚おろしになった魚が出た。
「真ん中は焼いてから茹でれば出汁になる。食べるのは基本的にこの二枚だな」
そう言ってルティンは包丁を置き、まな板の前をヴェステルナに譲った。
「今やった感じでやればいい、というわけか」
「そうそう。最初はそんなに上手く出来ないだろうが、まあ物は試しだ」
明るい口調で言い切ったルティンは奥の木箱から魚をもう一匹取り出した。今日釣れたばかりの分厚い魚だ。
「まずは尾びれ以外を切って、鱗を取る……だったな」
ヴェステルナは魚を前にして手順を口に出しながら、包丁を動かす。
魚をはじめて捌くにしては滑らかな手付きで、ひれが切り取られる。鱗落としの扱い方も荒々しい割りには身を傷つけることはない。
「それで次は頭を落とすんだったな」
ひれを軽く掴んで頭側へ引っ張り、根本に刃先を当てた。そこからはコマ落ちしたように包丁がまな板へ落ちる。
「ん?」
「なにかまずかったか?」
「いや……なんでもない。続けて」
頭を断つときは背骨を断つから初心者ならそこで確実に刃が止まる。そこから強引にもう一度力をこめて、ちょっと断面が汚くなるのがよくあるパターンだ。しかしヴェステルナの包丁さばきにはそれがなかった。頭の断面を見てみると、綺麗に関節に刃が通っており、一寸の狂いもない。
ルティンはこれをビギナーズラックだと判断した。こんなことをいきなり狙ってはできない。いきなり細かすぎる説明はどうかと思っていたから、話してすらいないのだ。
「それでここで下を切って内蔵を出すわけだな」
するりと刃が皮を切っていき、滑らかに内蔵が引き出される。端が身についているが、ヴェステルナは弾くように刃先を使って軽く断ち切った。ルティンが見せたとおりの――あまりにも見せたまますぎる包丁さばきだった。
ルティンが唖然としているうちに血合いの膜が切り取られ、身を洗うのも済まされていた。
「じゃあここからはさっき切ったとこに合わせて尾まで切っていけばいい、と」
身と中骨の間をするりと刃が通る。ルティンにはほとんど切っている動作が見えなかった。単に包丁を動かす手が早かったわけではない。どんな動きにも起点と終点があるが、ヴェステルナのそれはあまりにも些細で動作を動作と思わせないような繊細さがあった。
それは黒王女が戦場で見せる剣術と似ていた。当然だ。魚を切るのも人を切るのも、刃物を使うという点では同じだ。だから普段、ヴェステルナが人を切るのに使う剣術が魚を捌く際に顔を覗かせるのも当たり前と言えた。
魚を三枚におろすことでさえも、ヴェステルナは人生の一端を垣間見せる。
それからヴェステルナは綺麗に魚を捌ききった。断面がぎざぎざになってもおらず、中骨のついた部分へ無駄に身が残っていることもない。ルティンが普段おろすのとほぼ変わらないほどの腕前だった。
「どうだ。まだまだか?」
ヴェステルナは包丁をまな板へ置いて、ルティンへ向き直った。
「す、すげえ! これが初めてって本当かよ!」
言ったのはいつの間にか後ろで眺めていたシェックだった。
身をしげしげと眺めて、仮面から覗く目を輝かせている。
「うん、本当にすごい。もうちょっと練習したら私より上手くなるかもしれないぞ」
「……ありがとう」
そこへまだ店に残ってテーブルで談笑していた客たちも近づいてくる。常連のルシェンは興味津々といった様子でカウンターを覗き込む。
「新しい人ですか?」
「いやいや、この人は別にそういうわけじゃない。ちょっと魚の捌き方を教えてたんだよ」
「じゃあこの辺で今度屋台かなにかを出すんですか? この腕なら楽しみですね」
「いや、私は別に料理人ではない」
「そうなんだよ、今日初めて魚を捌いたのにこの上手さなんだよ」
へえ、とルシェンの横で感嘆の声をあげたのはムツラだ。自信に溢れた目を細めて、ヴェステルナの手元を見る。
「包丁さばきが凄いんだね。何かやってたのかい?」
艶を帯びた声でヴェステルナに呼びかけるが、ヴェステルナは頭を振った。
「料理自体初めてだ。ルティンの教え方が上手かった」
「そういうわけじゃないって! こんなの普通じゃムリムリ、本当にすごいって」
ルティンはヴェステルナの肩をばしばし叩いて褒めた。
そこへ扉の鈴が鳴って、人が入ってきた。
「遅れましたっ、お疲れ様です」
「お疲れ様です!」
昼間は桜花広場で屋台をやっているリアと、夜だけ手伝いに来ているエルルカだった。二人はたまたま近くで一緒になったらしい。珍しく一緒の出勤だ。
人だかりが出来ているカウンター付近に気づいた二人は早速近寄ってきた。
「どうしたんです?」
リアは大きなリュックを裏へ置いてから、ルティンに近づいた。
「これ、ヴェステルナがやったんだよ。しかも初めて。すごいだろ?」
緑の瞳をぐっと魚へ近づけたリアは感嘆の声を漏らした。
「すごい! この魚は捌きやすいですけど、一回でここまで綺麗にやれるなんて。でもこれってよく市場であがりますよね?」
リアの勘違いに気づいたルティンが笑みを浮かべた。
「いや、そうじゃない。この魚を捌くのが初めてってわけじゃなくて、魚を捌くこと自体初めてなんだ。しかも料理が初めてときた。すごいだろ?」
えっ、とエルルカは口元を抑える。
「凄すぎません?」
「だろー、なのにヴェステルナは自覚なし。いやー、こんな才能が近くに眠ってたとはな」
そこで良いことに気づいたという表情を浮かべたシェックが、手を叩いて注目を集めた。
「いっそ料理も全部教えてみよう! 流浪の天才料理人が誕生するかも!」
**
だがそう現実は甘くなかった。
「うーん……ちょっと塩コショウ足して、後は……」
木箱の上に置いてある麦のような野草を握ったルティンは、先端を軽く手で振る。すると黄緑の粉のようなものが鍋へたっぷりと落ちた。香辛料の一種だった。
「これでどうだ……ウン、美味いかな。どうだ?」
具沢山のスープの中にもう一度スプーンを入れたルティンはヴェステルナの手にひとしずく落とす。
「ああ、美味しい」
「あー、良かった。今日の仕込みどうなるんだろうと思ったよ……あ、別にあんたのことを悪いって言ってるわけじゃなくてな」
「いや、あれは私が悪い」
「そんなことないって! な、次やったらきっと上手くいくさ」
ヴェステルナは続いてスープを作る練習をしたが、味付けの段階で失敗してしまったのだ。味が薄すぎて、お湯にただ具材が放り込んであるような状態になっていた。その上煮込んだ具材の形が崩れて、せっかく綺麗に切った魚も一匙掬うたびにぼろぼろになる始末だった。
火加減と味の調整がまだまだといった具合だ。
具材を切るという点では、剣術を学んだヴェステルナに分があった。しかし他は初心者にはまだ難しすぎた。そもそも火加減などは、どう調整するか説明するところからだったから、ルティンも手が回らなかった。普通の人なら一度くらいは家でやったことがあることでも、黒王女であるヴェステルナには馴染みのないことが多い。
「落ち込むなよー。別に最初から全部上手くいくやつなんていないんだから」
「……少し家で練習するかもしれない」
「おお。そっか。料理、楽しんでもらえて良かったよ」
ヴェステルナはルティンの顔をまじまじと見つめた。
「楽しんでいるように見えたか?」
「ああ、次は上手くするんだろ? コツをメモにまとめとくから後で渡すよ」
ヴェステルナは自分の頬を指先でなぞる。どことなくいつもと違う感覚が指に伝わった。
**
ほとんどの仕込みが終わったらもう夕暮れに差し掛かる頃合いだ。
ちょうど人が増える時間でもあり、あっという間にテーブル席は人で埋まった。
一番カウンターから近いテーブルには錬金術師たちが陣取っている。シェロンもその中に混じって、愚痴大会に耳を傾けている。朝早いこと自体に不満を持っているものから、客の曖昧な注文に不満を持っているものまで幅広い。シェロンはほとんど酒を飲むばかりで聞き手に回っていた。
その横にあるテーブルではすっかり出来上がっているアリーナの美人剣闘士、アキレァが隣の男――ヴェックマンにガッと肩へ手を回していた。
「おいおい、キミ見たことあるな。アリーナに来てただろ? 良いもの食ってるじゃないか」
「うるせえ、見たことあるのは前もタカられたからだよ!」
ヴェックマンは酒臭い息を吐くアキレァをぐいぐい押し返しているが、その間にグラスが空にされたことには気づいていない。
テーブルの奥、二階へ上がる階段の反対側にあるスペースではキナ・ラトセラがウクレレを弾いていた。
カウンター席に座る何人かはその音に耳を傾けており、曲が終わるたびに小さな拍手が起こる。だがほとんどの客は話すのに夢中であまり聴いていない。彼女の知り合いらしき人たちが時折近づいては、二言三言話をしていた。
一方、扉に一番近いテーブルでは大道芸を普段やっているメイ・アサーシャが妙な歓待を受けていた。
「前見たときから、本当に大ファンなんです! おひねり以外でお金を払う方法ってないんですか!?」
「あー、いや……別に考えてないけど」
「じゃあとりあえずここだけでも奢らせてください! 本当に大好きなので!」
妙齢の獣人の女がふさふさに生え揃った毛に覆われた手で何度もメイの手を握った。
「いやあ、あたし別に大道芸が本業ってわけじゃないんだけどね……」
ぼやいたその声は熱を上げているファンの女には届いていないようだった。
カウンターの端に座る女、ギネヴィアはそんな喧騒で包まれた”虎の鰭”亭で一人静かにスープに口をつけていた。湯気のたったボウルへ静かにスプーンを入れる。
一見ぼーっとしているようにも見える彼女だったが、少し離れた位置で同じく一人の客をちらりと伺っていた。
黒衣の美女。
どこかで見たことがあるような気がするが、ギネヴィアはついにその正体が黒王女ヴェステルナだとは見抜けなかった。東征で従軍した時にちらりと見た、最前線で指揮を執っていた黒衣の騎士王女がまさかこんな酒場にいるとは思えなかったのだ。
一方でヴェステルナは視線に気づいていたが、特に話しかけられることもないので淡々と食事をしていた。
自分で捌いて、途中まで調理したスープをボウルいっぱいによそってもらっている。
「いつもと違う気がする」
ヴェステルナは背筋を伸ばした状態で丁寧に食べている。酒場にも関わらず手元に酒はない。
調理の合間に顔を上げたルティンが苦笑いを浮かべた。
「そりゃあいつも違う味付けだからな。ちょっとコクがあるだろ?」
「そういうわけじゃないんだ。何か味とは違うところで、変な感じがする」
ルティンはしばらく手を動かしつつ、考えた。ヴェステルナはもっと根本的な話をしているのだ。
「じゃあ自分で作ったからかな。飯って食べる時間より調理する時間のほうがずっとかかるだろ? だから頑張った分だけ美味しく感じちゃうもんなんだよ」
「なるほど。達成感とか満足感が足されてるわけだな」
ヴェステルナはゆっくりと頷いた。
「それに今、ヴェステルナが作ったものをみんな食べてるわけだろ? スープを頼んだ客はとりあえずみんな食べてるし。そういうのも嬉しいじゃないか」
「そうか。今、私は嬉しいと思っているんだな」
なんだそれ、とルティンは笑った。
「ま、家でも練習してみればいい。料理は振る舞うのも楽しいからな。誰か食べてもらいたい人を意識してみるのもいいかもしれない」
そうすればもっと楽しくなるぞ、とルティンは言った。
ヴェステルナは誰に、と考える間もなく一人の人間が思い浮かんだ。
青い瞳に、自分とは真逆で透き通るような白い髪の毛をした少女――唯一の妹であるエストリフォを。
誰に対しても優しくて――だからこそ王として各国の毒蛇の群れを渡ることなどできそうにない。あの子には王など似合わないし、それは本人が一番分かっているだろう。そのことについて思いを馳せるたび、エストリフォの苦しみを想像してヴェステルナ自身も同じように胸を痛めた。
もうずいぶんと妹が笑っている姿を見ていない。
料理ならもしかしたら、とヴェステルナはいま眼の前で笑みを浮かべているルティンをエストリフォに重ねた。
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp