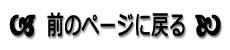●白樺広場の失せ物探し
白樺広場では祭りが開催されており、露店や大道芸で広場は盛況だ。みんな、思い思いに祭りを楽しんでいた。
そんな時、祭りを楽しむシュネーバルはより楽しくなればと用意していた薬を出そうとするが、見つからず……
【登場人物】
・キナ・ラトセラ
・グルーヴィー・ハイブランダー
・シュネーバル
・スズラン
・アルトレーゼ
・エニシ
・ヴェックマン
・リン・フィーリス
・ロア・フィーリス
・ジャン・ジルベルト
・ルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオ
・イスラ
・ヴァネッサ
・ノシュマン
・ギネヴィア
・アフィーネ
・ハノワリ
・ダイン
・エミリー
・ウィク・イグナイター
・エニマ
・ノワ
・シャロン
・ヤエ
・アルメル
・レノ
・メイ・アサーシャ
・ライル・クロイツァー
・ノエル
・リア・エイリコ
・シェック
・ムツラ
・ルイーズ
・アラワク
・ウリエラ
・ヘンリー・オーグスト
・ルミア・バリシス
・チノ
「荷物見ててね」
「あたしのも頼むよ〜!」
「キナさんは何もないじゃないか」
そうだった〜、とキナ・ラトセラの声が雑踏に消えていく。もうスズランの背中も見えなくなった。
シュネーバルはもう日が落ちそうな白樺広場で、丸テーブルに一人残された。
周囲の喧騒が心地よく、背もたれに身体を預けて屋台の串を食べていると楽しい気分で満たされるようだった。
今日は祭りの日だ。
白樺広場には露店がいくつも立ち並び、テーブルがいくつも並べられ、広場へ繋がる道にまで露店がひろがっている。
シュネーバルと先程まで意気投合していた二人は、物足りなくなって屋台を見に行ったところだ。シュネーバルは手元にある空のコップを弄びながら、周囲を見渡してみる。
すぐそばの露店では列を成している。さっきシュネーバルが食べていたイカの串焼きもその店のものだ。
その列に並ぶ客相手にお菓子の歩き売り――アルメルが近づいていた。時々買う客もいるようだが、串焼きを食べたい層には不人気らしく、しばらくするとテーブルや観光客に紛れて姿を消した。新たな売り場を探しているようだ。
祭りの機会を逃さず、ここぞとばかりに珍しいものを見せる者たちもいる。
客が半円で囲んでいるのは、大道芸や音楽を披露するものたちだ。
メイ・アサーシャは大きな玉を五つほど投げてジャグリングをしている。他にもたまたまそこへ集まったものたちが即興で音楽を合わせたりして、客たちは大喜びしていた。
他にも花弁がほのかに光る花を両手に一輪捧げ持った少女――レノがふらふらと歩いている。喧騒とあいまってもはや見世物なのかただの個性的な者なのか区別がつかない。
人混みの中では迷うものもいるようで、メイド服で風呂敷と棍棒モップを握りしめたエニシなどはキョロキョロと周りを確認しながらあたりを彷徨っている。
さきほどのシュネーバルのように楽しくテーブルを囲んでいる集団も当然多い。
綺麗な羽をつけた青年――ウリエラはテーブルにごちゃごちゃとコップや紙袋を広げてぼんやりと大道芸を眺めている。その横には、おどおどとした調子でコップを両手で握りしめるヘンリー・オーグストと見かけの割には泰然とした態度で足をぷらぷらさせているルミア・バリシスがいた。
三人とも他愛のない会話をしつつ、そろそろ日が暮れていく白樺広場でお酒を飲んでいる。
よく見るとルミアは制服姿だ。ちゃっかりとコップを紙袋で隠して、中身が分からないように工夫していた。
他にもテーブルを囲んで楽しそうな者たちは多い。
シュネーバルにも声が届くほどに近いテーブルでは、仲の良さげな男女二人組がいた。
「うわ、これ美味いな」
「ちょっと味濃い気がする。お兄ちゃん、まさか私のご飯より」
「まさか! リンが作るのが一番に決まってる! だけどたまには外で食べるのもいいよなって」
「ふーん、というか味が濃いのが美味しく感じるのは飲みすぎなだけじゃない? お酒で舌がバカになってるんだよ」
どうやら兄妹らしい、とシュネーバルは見当をつける。
自分にも弟がいたこと。もうずいぶん会っていないこと。どんな顔をしていたか。最後に会ったときにした会話。
何もかもが懐かしい。思わず仲の良さそうな兄妹――リン・フィーリスとロア・フィーリスに話しかけてしまいたくなるくらいには。
「こういうところの料理って、とりあえず味を濃くして素材の鮮度を誤魔化したりするらしいですよ」
唐突に割り込んだシュネーバルが身を乗り出して、二人のほうへ笑みを向ける。
「へー、そうなんですか。じゃあこれも……」
ロアの食べるタラのフライにリンは顔を近づけて、匂いを嗅ぐ。ロアは一瞬だけシュネーバルに鋭い視線を向けるが、無害そうな柔らかい笑みに、祭りで浮かれているだけと判断を下す。
「ならお酒さまさまですね。俺はとりあえず美味いものが食えればそれでいいから」
そう言ってロアはリンの顔をぐいと押しのけてフライにかぶりついた。飲み込んでから、口の中を洗い流すような豪快さでビールを半分ほど飲む。
「こういうとこで食べるってだけで美味しくなったりしますしね」
「楽しいと、それだけで美味しく感じますよね」
リンがシュネーバルに同意を促すようににこりと微笑む。シュネーバルも応えるようにしてリンへ向かって微笑みかけた。
その直後、シュネーバルは手を叩いた。忘れていたことを思い出したのだ。
「あ、そうだ。もっと楽しくなるものを持ってたんだ」
そういってシュネーバルはポケットの中を漁る。
「もしかして、樹法具とか?」
のんきにロアはシュネーバルの手元を見ている。
しかしシュネーバルは困った顔をして、二人のほうへ向き直った。
「どうやらなくしたみたいだ。このくらいの瓶だったから、どこかで落としたのかな」
シュネーバルは親指と人差指、中指でコップの半分ほどの高さを示す。
中身は薬だ。
例えば近くの露店に置いてあるビール樽のなかにひとたらし入れるとする。きっと楽しいに違いない、とシュネーバルは確信していた。
眠くなったり動かなくなったりはしない。飲んだものはみんな、その場で痙攣し、朝まで踊り狂ってくれる。
その様子を想像したシュネーバルは、楽しそうに笑った。
**
「あれ、これなんだろ?」
片手に露店の柔らかい蒸し焼きパンを手にしたイスラは、地面に転がっていた小瓶を拾う。底面が六角形でカットが入っていて、ロウで封印がされている。
中身は淡い緑色の透き通った液体だ。
慎重に拾い上げたイスラは、連れ立って祭りへ来ていたシャロンとダインにそれを見せる。職人街で知り合った二人だ。みんなまだ一人前ではない、ということで共感できる話題に事欠かないため、最近はたまに会うとすぐ集まりがちだ。
今日も祭りということでイスラは師匠に暇をもらっている。祭りが終われば明日の朝ごはんの準備をしつつ夜中の勉強もしなければいけないが、一時の暇を逃すほどイスラは疲れ切っていない。常に元気で笑顔がモットーなのだ。
「どっかの売り物だな。かなり綺麗に封がされてるから高価そうだ」
シャロンはイスラの手にある小瓶を眺め回し、目を細めた。
「高いなら落とした奴は大変だな。やべーかもしんねえぞ」
ダインは背中を丸めて、イスラの手へ視線を落とす。じろりと睨む目はガンを飛ばしているように見えるが、実際はよく小瓶を見ようとしているだけだ。
「すぐ届けたほうがいいよね。見回りの人に渡せばいいかな?」
イスラは周りをキョロキョロ見渡す。祭りで人が多いので、いつもいるルイ=シャルル・ド・ポラリス=ヘカテリオたち衛兵もいつもより多い。仕事を委託されているグルーヴィー・ハイブランダーのような傭兵たちも辺りをうろついており、人の多さの割に広場の治安は保たれている。
小瓶を片手にイスラは衛兵を探す。そうして小瓶を拾った場所から離れるようにして歩きだそうとした。
「ちょっと待って!」
それを止めたのはシャロンである。
「まだこの近くに落とした人がいるかもしれない。聞いてみたほうが早いかも」
「え、でもそれじゃここで大声を?」
「問題あるかな」
イスラは辺りを見渡す。テーブルを囲んでいる者たちは楽しそうに喋っているし、露店を物色していたり、歩きながら食べている者たちも何かしら喋っていたり、音楽が鳴り響いていたりと、音には事欠かない。それでもここでいきなり大声を出すのは……とイスラは尻込みしていた。
だがシャロンとダインは特に気にしていないようだった。
「すみませーん! だれかこれを落とした人はいませんか」
「小さな瓶だ! 中身がまだあるぞ!」
シャロンとダインは大声であたりへ呼びかける。一斉に視線が三人のもとへ集まった。
ちょうど子どもたちにお菓子を渡していた聖職者のアフィーネは、手を止めてイスラの小瓶に視線を向ける。子どもたちも一瞬言い争いが止まって、ちらりとイスラの方を見た。だがすぐに興味を失って言い争いに戻る。
どうやら兄妹ゲンカらしい。どっちがお菓子を多くもらったか、とかあまり大事ではない話だった。アフィーネもすぐにイスラたちへの興味を失って子どもたちの仲裁に入る。
「さっきの羽のお兄さんがまた来て怒るよ!」
柔らかい態度で仲裁しようとしていたアフィーネへ割り込む形でエニマが入ってきた。
「うちの弟と妹がごめんなさい。いつもこんなんだからさっきみたいに変な人に……」
どうやら羽の人――ハノワリに何かしらの諍いを仲裁してもらっていたようだった。彼の性格からして怒ることはあるまいが。
そこから間もないうちに今度は子供同士で言い争いとは。祭りの雰囲気に呑まれると大変だ。
一方で落ち着いた様子で全く三人へ興味を示していない者もいる。
テーブルの一角に腰掛けているヤエは度数の高いトウモロコシの酒をくいと飲み干し、仮面の裏で涼しい顔をしていた。一切小瓶に心当たりはなく、ゆえに興味を示すこともない。
同じように心当たりのない錬金術師のノシュマンは、たまたま一緒になった傭兵の大女、ギネヴィアと話をしつつも、持ち前の好奇心が頭をもたげて、ちらりと小瓶を見た。少し離れているので、あまり詳細は伺えない。
だが一人の女が食いついた。
「あー、それあたしのだよ。ちょっといいかな?」
ひそめていても伝わる色っぽい声。やや高い身長でずかずかとイスラに近寄ったムツラは文句を言われる前に彼女から小瓶をするりと抜き取った。
「あっ、え、そうなんですか?」
「そうだよ。これがないとちょうど探してたところだったの。ありがとうね」
「いえいえ、ところでつかぬところをお伺いしますが、これって何が入ってるんですか?」
ムツラはイスラ、シャロン、ダインの顔をさらりと確認し、ニヤリと笑って答えた。
「媚薬だよ。頭がぶっとんで、めちゃくちゃ気持ち良い」
**
初心そうな少女――イスラを煙に巻くべくいい加減なウソをついたムツラは、小瓶を手で弄びながら、露店を冷やかしていた。
ムツラは小瓶の中身を知らない。しかし、それが高価であることは見抜いていた。
瓶の形状が、裏街組合所属の調毒士――ヴァネッサが取り扱うものと酷似しているのだ。おそらくはヴァネッサから流れたものだろう。毒か睡眠薬だとムツラはあたりをつけている。中身を細かく振ってみると、わずかに鱗粉のようなものが漂っている。これは見たことがないから、もしかすると何かが添加されていて、毒性が高まっているのかもしれない。どちらにせよ、ろくなものではない。
だが売れば儲かるのは間違いない。
三人はまさかあんな堂々とウソをついてくる奴が現れるとは思っていなかったのだろう。まんまとタダで飯の種をせしめたムツラは上機嫌で広場をうろついていた。
混んでいてテーブルに空きはない。何かしら夕食になりそうなものを買ったら今日は家に帰ろうと算段をつける。
なにか良いものはないか、と露店を見て回る。ふと目についたのは、美味しそうに焼いたアジを頬張る少年の姿だった。よく見ると可愛らしい顔立ちをしており、女の子と見分けがつかない。広人種の男女の見分けがつかないのは珍しいのも相まって、ムツラはじっとその子――ルイーズの姿を見つめた。
小さな口で身の開かれたアジをせっせと食べている。一口が小さいが、上品に食べていて身をこぼすことはない。
ムツラが近づいてみると、アジを炙った塩っ気の強い匂いが漂っていた。干したアジの開きをどこかの露店が炙っているらしい。
少し辺りを見渡してみると、すぐにその店が見つかった。
つい先ほど日の落ちた広場で、樹法による明かりに照らされて白い煙がたなびいている。
露店では小さな女の子と若い鬼人種の男が切り盛りしていた。
リア・エイリコとシェックである。
一度列を捌き切ったのか、一段落している様子だ。今は一人が並んでいるきりで、よく見るとそれはムツラの知った顔であった。
「こんばんは。今日は仕事ないのかしら」
「あ、あの時の」
露店に並び、リアから紙袋に包まれた大瓶を受け取っていたのはムツラがよく行く酒場のバーテンダー、アラワクだった。
アラワクは髪をかきあげ、少し面倒そうに眉をひそめる。
「まあ今日は非番なので」
「お酒?」
「好きなんですよ」
「へー、仕事だからやってるってだけじゃないんだ」
「好きだから仕事にしてるんです」
いいなあ、とムツラがこぼした。
それからアラワクは大瓶をたいそう大切な様子で抱え込み、ムツラへおざなりに別れの挨拶を告げて広場から去っていった。
ムツラは匂いのことを思い出す。
お腹が減ってきた。
周囲の他の露店も一応見てみるが、サンドイッチやドーナツなどの軽食を売っているノエルの店と数種類のパンを売っているエミリーの店はどうにも今のムツラの気分には合わない。
今は味の濃いものを酒で流し込みたい気分だ。
「まだやってるよね?」
列のない店の前で、ムツラはリアへ話しかけた。小動物のようにぴょこんと顔を上げたリアは、快活な笑みをムツラへ向ける。
「すみません、今焼いてるところでして、少し待ってもらいますけどいいですか?」
「全然構わない」
ムツラは暇を持て余して、手の中で小瓶を転がした。これだけでも今日は大当たりの日だ。きっと家に帰って食べる干物も美味しいに違いない、と心を躍らせる。
だがそれは長く続かなかった。
「おい、あんたちょっといいか」
ずんずんとムツラの方へ近づいてくる男の影がいた。服装は全体的に黒いが、よく見ると聖職者の法衣である。
ムツラは逃げるタイミングをのがして、男――ジャン・ジルベルトが近づいてくるのを平気そうに取り繕うことしかできなかった。
「なんだい?」
「手に持ってるものを見せてみろ」
「なんのことか分からないね」
色っぽい声音でずいとムツラは近づいた。その隙に手から服の隙間へすべりこませる。
だがそれではジャン・ジルベルトは騙せない。
「今のはなんだよ」
ジャンは少し熱気で湿ったムツラの腕を掴む。ぽろりと小瓶がこぼれた。
「どこでこれを?」
「さっき拾っただけだよ」
ムツラはとっさに自分の持ち物ではないとアピールした。ジャンはおそらくこれがヴァネッサの取り扱っているものだと感づいている。へたに関与が疑われる方がまずい。
ほとんど嘘はいっていない。大丈夫なはずだとムツラは自分に言い聞かせた。
「中に何が入ってるのか分かってるのか?」
「さあ。すぐ届けるつもりだったさ」
そうか、とジャンは頷いた。
「じゃあこれは俺が衛兵に届ける。いいな?」
「そうかい」
ムツラは内心で嘆息した。せっかくの儲け話がふいになってしまった。もったいない。別に自分が損したわけでもないが、なんとなく負けた気がした。
だが実際には、捕まらなかっただけラッキーかもしれない。
ジャンが小瓶を手に広場の雑踏へ姿を消すあいだ、ムツラは背中を眺めながら干物が焼けるのを待っていた。
**
ジャンは小瓶をすぐに小さな布に包むと、服の裏へしまって隠した。
彼も小瓶をみたとき、すぐに毒であると気づいたのだ。ヴァネッサの取り扱う小瓶の外見は分かりやすい。
ジャン自身は薬を扱う経験がないが、裏町の会合で耳にしたことはあった。同じく盗賊であるノワあたりから聞いたとジャンは記憶している。
そんなものをこの広場で使われたら、面倒になるのが目に見えている。別にジャン自身は正しいことをしようと思って取り上げたわけではない。
聖職者としての表の顔、盗賊としての裏の顔。双方でこの薬が起こす問題の扱いが面倒になる。それを事前に防いだにすぎなかった。
「今のはなんです?」
だがそんなジャンの思惑を知ってか知らずか、一人の女が声をかけてきた。聞き覚えのある声。ジャンが逃げることの出来ないささやき。胸をじりじりと痛めつけるような清冽な態度。
聖職者、アルトレーゼが後ろに立っていた。
まるで何もかもが見透かされているかのような、清らかな瞳。疑うところを知らないような態度の中に、すべてを知った上でこちらの出方を見ている蛇のような無機質さを嗅ぎ取ってしまう。本当は違うのだろう。だがジャンには真意が読み取れない。
「いや、なんでもない。祭りには要らないものですよ」
聖職者のときの礼儀正しい態度を纏ったジャンは、無表情でアルトレーゼを見返す。彼女の横にはラフな格好をした軍人、ライル・クロイツァーが立っていた。どうやらさっきまで二人で話をしていたらしい。アルトレーゼの剣を持っているところを見るに、剣術か何かについて話をしていたんだろう、とジャンは推測する。
「そうですか。ならいいんですけど」
アルトレーゼはジャンに対して疑う様子を見せず、頷いた。
ジャンは自分がアルトレーゼに信用されているということに仄暗い喜びをわずかに覚えつつ、小瓶を服の中へ強く押し込めた。
「そろそろ花火ですよ」
ライルが川の方へ顔を向ける。空はもうすっかり暗い。
ジャンもつられて空を見上げる。するとほぼ同時にシュウウ、と火の上がる音とまっすぐ空へのぼる光があがった。
それから一拍置いて、腹に響く音がとどろく。
花火だ。
色とりどりの炎が夜の闇を鮮やかに彩った。暗くなった空を、海のように青い火が線を引いていく。その先で秋口の麦畑のように鮮やかな黄金色の花が舞い散っていく。
それからも次々に様々な火が、空の闇をキャンバスにして彩った。
川の方では火薬に熟知したウィク・イグナイターが作った花火が打ち上げられているのだ。
広場では空を見上げる人ばかりになった。川からは火薬の匂いの残滓が漂ってくる。
その中で、端の方のテーブルに座った二人組――チノとヴェックマンだけは、異質な空気の中で佇んでいる。
チノはまだマシだ。浴びるように飲んだ酒でふらふらしており、花火の音など気にもしていない。
もうひとりの男は、酒を飲んでだいぶ気分が落ち込んでいるようだった。
「兄貴はすげえんだよ」
情報屋の男ヴェックマンはもつれた口を動かす。
「優しくて、頭もいいんだ」
頭を垂れて、テーブルについた肘で支える。突っ伏しそうになるのを堪え、青い瞳をぎゅっと瞑る。過去の情景が脳裏へ蘇る。
「たまに、本当にたまに貰えるお菓子は、絶対に大きい方を俺にくれたんだ……それからクソ親父に殴られないように酒にちょっとづつ水を足したりしてたよ。バレて殴られるときに、俺は何もしてやれなかった」
「良い兄さんだったんだね」
チノはイカ串の根本をかじって、ヴェックマンの顔をぼんやりと眺める。
土気色をしたヴェックマンはチノに話しているのか、ただ吐露したいだけなのか判別がつかない。すっかり過去へと没入しており、花火の音も遠ざかっている。
「兄貴は昔から楽しいことが好きでさ……夜に二人で花火を見たこともあったなあ。バレてクソ親父が俺たちの背中を瓶でぶん殴ってくるのに、また花火があるって時、兄貴は性懲りもなく家を出てったよ。本当に楽しいことが好きだったんだ……本当に」
「で、そいつはどこ行ったんだい」
冗談めかしてチノは尋ねる。
「しらねえよ」
吐き捨てて、なんでも知っているはずの情報屋はグラスを煽った。中のビールが空になる。
いなくなった兄の過去を語るヴェックマンに、空で鮮やかに咲く花火の影が落ちていた。
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp