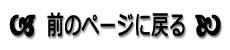●大聖堂の撒いた夢
【登場人物】
・ボルブ・ボルドリック・ボロボレイト
・フクマル
・シャロン
・レビィア・トピアス
・ドロイ・トピアス
・アルトレーゼ
・ジャン・ジルベルト
・ララ
・エミリー
・カイル
・ノエル
・ウリエラ
・ヘンリー・オーグスト
・キキ・テリヤ・ニートカ
・スカーレット
・ルミア・バリシス
・ジークヴァルト・クラウス・ディッペル
・エニマ
・マロン
・メシュ・メシュ(NPC)
・アフィーネ(NPC)
・ヴォル(NPC)
精緻の限りを尽くされた大聖堂の内に、人種も年齢も違う大勢の人々が集まっていた。
すでに聖堂内に入っていた人たちの顔には落胆や呆れ、ホッとした態度と様々な感情が浮いており、今から入ってくる人々のほうには野放図な期待が携えられていた。
宝くじだ。
今日は大聖堂が開催した宝くじの結果を発表する日だったのだ。
古くて壊れてしまった教室の補修と学用品の購入に充てる予算不足に悩んだシドリア大聖堂の苦肉の策であったが、“ちび宰相”メシュ・メシュの発案によるこの世俗的極まりないイベントは聖堂の多くの聖職者の予想を超えて大盛況になってしまった。
大理石で設えられた構内には人がひしめき、あちらこちらで声が上がっている。壁の何箇所かに当選番号を書いた紙が貼り付けられており、いずれの場所にも人だかりができていた。
柱のそばで苦笑しながらもくじと発表番号を何度も見比べている中年男性はボルブ・ボルドリック・ボロボレイト。周りには待機中の王国軍人たちが群れており、ボルブの店の羽振りが良くなるのを期待していたようだったが、残念なことにその当ては外れた。馴れ馴れしく肩に手を置く軍人たちを散らしながらボルブは無愛想な顔で髭を撫でた。
その近くでがっくりとうなだれているのは、飲食店を営んでいるフクマル。
長屋住まいの職人シャロンは最近悩んでいる隣人の騒音からおさらばできる見込みが消えて、しょぼんと立ち尽くしていた。
向こうの聖旗の下で目を皿のようにしている兎の獣人種はアリーナの大物食い“鮮血の赤兎”ことレビィア・トピアス。その姿を弟の服飾職人ドロイ・トピアスが冷ややかに眺めている。
聖騎士アルトレーゼは慣れない交通整理にまとめていた髪が振りほどけるほどに四苦八苦し、双子都市の悲喜こもごもがフルコースでシドリア大聖堂に溢れていた。一日限りの夢が盆に入り切らないほどに溢れかえり、泡となって消えていく。
そこから身体をどうにか引っこ抜いて人混みから離れた男が、くせっ毛の頭を掻きながら出てきた。
「もう一枚見たら書いてあったりしないもんかね」
ヴォルだ。
別段今はお金がなくて困っているわけではないが、あるに越したことはない。それに働かずに手に入るならなお良い。足りなくて困ることはあってもありすぎて困ることはないからだ。
そうした思惑を持って宝くじを買ったヴォルだったが、目論見を外したようだった。一人ぼやいて己が身を慰めるほかなかった。
しかしそこに割って入る声がした。
「どれも同じですよ。何度確認したって何も変わりはしません」
素気ないジャン・ジルベルトがヴォルの横へ立っていた。
彼は聖職者だ。普段は聖堂に近寄りもしない人々がこぞって集まっていることにあまり良く思っていないらしく、浮かべる表情はいつもより数倍増しで冷たい。
ヴォルは聖職者とは思えないほどの鋭い雰囲気にぎょっとするが、すぐに気を取り直した。もしかすると話しかけられたのは警戒されてのことかもしれない。安全で信頼できるところをこの聖職者に見せねば、と雑談に乗る。
「でもなー、やっぱり気になるよ。もしかして綴り間違いなのかな、とか」
「何度も確認した上で張り出してますからそんなことはありませんよ。まあ本当に気になると言うなら止めはしませんがね」
冷たく返すジャンにヴォルは苦笑を返すほかなかった。
「そういえば当選した人って公表したりするのか?」
話を変えてやり過ごそうとしたヴォルだったが、上手くいかなかった。
ジャンはため息をついてヴォルを見る。
その態度にヴォルは振る話題を間違えたと悟ったがもう遅い。
「もしそんなことをしたらどうなるか想像がつきませんか?」
「あーえっと……たかられる?」
それもありますね、とジャンは前置きした上で、
「ほかにももっと悲惨なことが待ち構えているでしょう。慣れない店に行ってぼったくりに遭ったり、今まで存在しなかった友人たちが大挙したり、下手すれば寝床に潜り込まれて身ぐるみ剥がされる可能性だってあります。お金は足りなすぎても問題ですが、いきなりポンと渡されて余りすぎても問題になるんですよ」
そう言ってジャンはこんこんとヴォルへのお説教を始めた。聖堂に熱心な信者以外が大勢いるせいで仕事にならないのか、ずいぶん暇そうだ。ヴォルはしばらく逃げられそうにないことを悟り、ジャンのお小言に耳を傾けた。
**
聖職者と用心棒の男が話している間、ひっそりと身を隠して聞き耳を立てている少女がいた。
ララである。
大きな耳をぴんと立てて、二人の会話を聞いていた。当選者を知りたいのだ。少しくらいなら当選金からくすねても問題ないだろう、とララは考えつつ二人の話に一人で相槌を打っていた。
「何をしてるの?」
ララの肩に手が置かれる。びくん、と跳ねたララが大きく後ろを振り返った。髪が乱れる。それを気にする間もなく、相手の姿を視界に捉えた。
アフィーネ、聖職者だった。
「な、あたしは別になにもしてないし!」
「そうかな? なにか盗み聞きしてなかった? 耳がぴこぴこしてたよ」
そう言ってアフィーネはララの頭を指差す。ララはどきりとして咄嗟に手で耳を隠した。
「何か向こうの方に向いてなかった?」
おっとりと話す口調に圧力はないが、的確に自分の行動を探られていることにララは気づいた。大聖堂は普段入りもしないから知らなかったが、聖職者とはかくも清冽で聡明なものなのかと戦慄する。
何とか逃げ切らなければならない。
急に離れれば追いかけられるかもしれない、と考えたララは向こうから離れてもらえばそれでいいと判断する。
アフィーネがララから離れたくなるような話題を出してしまえばいいのだ。
「別に、どこも向いてないよ。ま、聖職者サマには何か見えないことが見えることとかあるんだろーな」
急にふてくされたような態度を取り始めたララにアフィーネがムッとする前に怪訝な顔つきをした。
ララはさらに畳み掛けようと猛然と口を動かす。
「だいたいこんな催し、どうせ胴元が一番儲かるように出来てるんでしょ? ここにいっぱいいるみんなに希望を与えるだけ与えて自分たちだけ大儲けするのって楽しそうだよね」
ここまで言えば流石に相手も引き下がるだろうとララは思った。ちらりと相手の顔を伺う。しかし彼女は全然別の方向を見ていたようだった。
「すみません、これってどの張り紙も同じ内容なんですか?」
「ええそうよ」
仕事着のままここへ駆けつけたような少女――エミリーがアフィーネの前に立っていた。膝に手をついて息を整えている。
どうやら彼女もくじの結果を見に来たらしい。想像以上の人だかりで何が何やらという顔をしており、とにかく事情の分かりそうな聖職者に声をかけてみたというところだろう。
「今は人でいっぱいだからまだ待ってみるのもいいかもね」
「そうですか、ありがとうございます」
そう言うとエミリーはそのままアフィーネの横に立って待ち始めた。ララはもう逃げられる、と判断して人混みのほうへつま先を向けるが、
「あ、そっちの人も結果見に来たんですか?」
完全にエミリーと目があった。ララはぎこちなく自己紹介した後、何となく頷いてしまった。
「まあ落ちてたけどね」
そう言って目を床へ落とす。もうそんなことどうでも良いのだが、エミリーはララ以上に悲しんでくれた。
「こういうのって当たるかどうか分からない時が一番楽しいですよね。当たってたら色々買い物したいなー」
「いいね。休みもらって買い物とかしたら楽しそう」
アフィーネもエミリーの話に乗っかって雑談に興じる。二人に置いてけぼりにされたような気分になった。その方が良いはずなのに、とララは思うがどうにもならない。
「まあでも本当に一等が当たってたら店の開店資金にしちゃいますかね」
「あら、お店?」
「はい、私みての通りパン屋で働いてるんですけど、将来は自分の店が開けたらなーって思ってるんです。今はコツコツ働くしかないんですけど、いつかはバンと自分の店を持ってやるんですよ」
鼻息荒くするその姿にララは少し羨望を覚えた。自分より歳下に見える彼女だったが、その志はずっと高いところにある。
結局ララは二人の会話に入ってしまい、しばらく動けなかった。しかしそれでも良いと思えた。
**
「あー外れてた」
カイルの店やノエルの店で両手いっぱいの食べ物を買い込んでいたウリエラは隣に立つヘンリーのぼやきを聞いても慌てることはなかった。しかしヘンリー・オーグストのほうはそうでもないようだ。
「なんでそんなに落ち着いてるのさっ!」
「まあ当たるほうが珍しいから……」
スローテンポの声はヘンリーを落ち着かせはしない。
なんと言っても彼らは普通に当てる気で買い物をしていたからだ。普段はこんなに大量の食べ物を抱えたりしない。
ウリエラが絶対当たるから大丈夫といって先に買い物をしてしまったのだ。ヘンリーは押しに弱い上に、ウリエラは謎の雰囲気がある。当たると言ったときの彼の顔は本物だった。未来が見えているように感じた。
結局ヘンリーの勘違いだったと分かった今でも超然とした顔にはどことなく当たる人間の器があるような気がする。それが錯覚であることは重々承知の上で、それでも彼の態度にはなにかある気がしてならなかった。
「これ普通に三日分くらいの食費かかってるよ、もっと良い使い道もあっただろうなあ」
「気にしなくていいよ。美味しいから」
「いや、僕は普通に気にするから!」
常人よりの発想をしていないウリエラにとっては別段気にすることでもないかもしれないが、ヘンリーにとっては死活問題だ。
ウリエラは手に持った串を頬張りつつ、宙に視線を彷徨わせる。
「当たってたら買いたいもの、あったなあ」
ウリエラは何か自然に関する重大な考え事でもしているかのような態度で、外れたくじに思いを寄せていた。
ヘンリーはため息をつくしかなかった。
「こんな屋台の食べ物なんて端金だったって思えるくらい貰えただろうね、一等なら」
「もっと美味しいものを買ってた?」
「屋台じゃなくて普通に店に入ってたかな。今まで入ったことない店とか」
そう言いつつヘンリーはウリエラから紙包みを貰い、サンドイッチをもそもそ食べる。
「それに服とか買っただろうな」
キキ・テリヤ・ニートカとかに個人で頼めたら最高だろうな、とヘンリーは言った。ウリエラは胡乱げに頷いて串の肉を飲み込んだ。
「女は買わんのか?」
ぎょっとしてヘンリーは振り返った。後ろに女学生の格好をした少女のような出で立ちのルミア・バリシスが立っていた。
「ルミアさんも宝くじを?」
うむ、と言ったルミアの表情は心なしか陰っている。どうやら外れたらしい。
それでもそこまで深く気落ちしているわけではなさそうだった。それもそのはずで、彼女――いや彼は齢六十を超えたお爺さんだ。貯蓄も十分だし、そもそもきちんとした職についており、しっかり稼いでいる。
ただ見た目が十七歳なだけである。見た目に騙されてはいけない。
小人種ではない、というのがひと目で分かるくらいには成長した姿をしているせいでかなりの人間が騙される。
しかし彼の精神は決して見た目に引っ張られてなどいない。
「女を買うってスカーレットとかの店ってことですか?」
経営者本人も美麗で有名な店だ。ヘンリーは度胸も金もないので入ったことはないが、うわさには聞いたことがある。
「うむ。店はどこでも良い。ようは好みの女を抱けたのにな、ということじゃ」
見た目が少女だと言葉の衝撃もかなり変動する。ヘンリーは中身を知っているはずなのに、それでも彼の言葉に動揺してしまった。
「ル、ルミアさんちょっと素が出てますよっ!」
「おっと、忘れてた忘れてた」
ルミアはスカートの裾を軽くつまんで恭しく二人に向かって礼をする。そういう女性観の貧困さあたりに本当のルミアっぽさが滲んていると思ったが、流石に可哀想なのでヘンリーは黙っていた。
そんなヘンリーの思惑など少しも理解していなさそうなウリエラが顔色一つ変えずに、話を元へ戻す。
「お金があればそういうこともできたかな」
ウリエラの落ち着きっぷりは堂に入っていた。少女の姿の老人に女の話を持ちかけられても動揺することなくただ会話を続ける。
ルミアはウリエラの態度へ特に疑問を抱いている様子はなく、全然気にせず話を続けた。
「おお、いいのお。その勢いでずんと何でもやるのが良い」
「確かにそうだねー、お金さえあればね」
「くじなど当たらなくても金なんて手に入るじゃろう」
そうだね、とウリエラは言った。
「でもたっぷりお金がないとできないこともあるんだけどね」
「例えばなんじゃ?」
「部屋の片付けとか?」
それからウリエラは業者に頼むと物凄く高いということについて話をして、ルミアを呆れさせた。
**
汚い部屋に子どもがひしめいている。
窓から注ぐ日光に照らされて床にはおもちゃが散らばり、地べたに座り込む子どもたちがあちこちで塊になって遊んでいる。
その真ん中でジークヴァルト・クラウス・ディッペルは長い裾を子どもに引っ張られつつ、鷹揚に誘いに乗っている。
部屋の扉が控えめにノックされた。
「おお、どうぞどうぞ」
と言っても風通しを良くするためにドアは最初から開いている。
おずおずと入ってきた少女にジークヴァルトはにこやかな笑みを浮かべて応じた。
「すみません、下の子たちの面倒を見てもらって」
「いやいや、気にせんで良い。これは好きでやってることだから」
そういうジークヴァルトの顔つきは優しかった。
エニマが入ってきたことに気づいた数人がわっと群れる。全員エニマの弟と妹だった。エニマは大きな紙包みを抱えつつも、それぞれの頭をなでる。
「買い物の間だけとか融通を効かせくれるのは本当にありがたいです」
今日、エニマは食材の買いだめをしていた。野菜を買うときにはたまたま知り合ったマロンという女性に良い野菜の見分け方を教えてもらい、かなり得をした。
「まあそれぞれ事情があるだろうし、そういう時こそ頼ってほしいからな」
ジークヴァルトは子どもに髭を突かれつつも、その子を抱き上げる。高い高い、と言う彼につられて子どもが笑った。それを見て周りの子もせがむのであっという間に輪ができる。
「そういえば宝くじはどうだった?」
エニマは首を横に振った。ジークヴァルトは悲しそうに顔を下に向ける。
「でもまあ仕方ないですよね。当たれば少しは家計が楽になったかもしれないけど」
「次は当たればいいな」
そう言って労うジークヴァルトはエニマの家計が逼迫していることを知っている。下の子達が多すぎて、働いても働いても楽にならないのだ。それでも投げ出さずに頑張っているエニマをジークヴァルトは尊敬してくれているらしかった。
袖のなかに手をいれて、ごそごそとまさぐって手を引き抜いた。
そして掴んだものをエニマの手にそっと握らせる。
「これでも食べて元気を出すと良い」
飴玉だった。
「いやいや、大丈夫ですよ。私は」
と続けて固辞しようとしたエニマだったが、半ば強引にジークヴァルトはその飴を差し出した。エニマはさんざん頭を下げてお礼を言う。
「次は当たるといいな」
最後にそう言ったジークヴァルトの顔にはただ優しい表情が浮かんでいた。
エニマは下の子たちの手を引きながら、次の宝くじに想像を巡らせる。もし当たれば、もっと弟や妹に楽な思いをさせられるかもしれない、と思った。そんな夢が巡る中、手を握った下の子たちは何も知らずに楽しそうな笑みを浮かべている。弟や妹にとっては宝くじが当たらなくても、当たってもどうでもいいのだ。まだ理解できていない、というのはあるだろうが、それよりも今が楽しくて仕方がないみたいだった。
エニマはそんな弟と妹たちの様子を眺めて、別に当たらなくても良かったかなと思い直した。
**
当たらなかった者も多少の幸せを掴んだ宝くじだったが、実際に当たったものはどうなったのだろうか。
噂によるとアリーナの賭けに突如現れた者が一点に大きく張った挙げ句とんでもない額を稼ぎ出し、その金を種にさらなる躍進を一日で果たしたのち、最後の最後ですべてすって金は消えたという。
一日限りの夢が、現れては消えたという。
当たった者も夢の中へ吸い込まれたともっぱらの噂だった。
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp