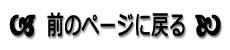●街外れの災難
【登場人物】
・crc_0006:ルイーズ
・crc_0011:ブラックフォックス
・crc_0007:アーベン
「やばいやばい、遅刻だこれ!」
ルイーズは慌ただしい足取りで待ち合わせ場所に向かって走っていた。後ろで一括りにした髪からこぼれ落ちた房が頬や首に垂れた汗で張り付く。
息を切らせて走り、ようやく目的の場所についた。待ち合わせをしていたのは二階建ての、鎧戸で採光の取られた大きめの店だ。
扉を開けると、分厚い熱気が顔に吹きつけた。昼間にも関わらず酒を飲む男たちが大挙してテーブルを占拠しており、周りのことを気にする様子もなく騒いでいる。ルイーズは煙と汗の臭いに顔色一つ変えず、店の中を見わたした。一階には目的の人物がおらず、階段をのぼって上へ行く。
カウンターに近いテーブル席に一人で座っている男が、手を振っていた。
「ごめんなさい」
ルイーズは座る前に軽く頭を下げた。
「いいや、気にしてない。ルイーズさんで合ってる?」
「ルーでいいよ」
そうか、と大した感慨もなく彼は頷いた。
男はアーベンという名前の調毒士だった。彼がルイーズをここへ呼んだ。
「今日は来てくれてありがとう。話はもう聞いてると思うんだけど、護衛がほしいんだ。ある程度戦える人間が欲しい」
「聞いてるよ」
ルイーズは最近、知人にこの仕事を紹介されたばかりだった。穀倉地帯の外で活動をしている時に出会った男の一人がこの仕事を教えてくれたのだ。街はずれで受けられる仕事は公に募集されていないことが多いから、知り合いの伝手は大きかった。
「ルーさんは数十日この都市を離れることになっても問題ないかい?」
「ここじゃなくて、さらに外へ出るということ?」
城外とはいえ、ここを称して『都市を離れる』とは言わないだろうとルイーズは考えて、アーベンの目を見た。彼は穏やかにうなずいた。
「ここから離れた遺跡に調査に行きたいんだ。私については知り合いから訊いた?」
「ううん、そこまでは」
「私は調毒士なんだが、普段は調剤をしているわけじゃない。どちらかというと考古学者みたいなことをしているんだ」
「誰かの依頼で?」
「いや、趣味さ。調査と研究の成果を売ることはあるけど、ほとんどは私事だ。やりたいからやってるんだよ」
パトロンのいない研究ほど気楽なものもないだろう、とルイーズは思ったが口には出さなかった。アーベンはさらに説明を続ける。
「それが最近誰かに邪魔をされている」
「というと?」
「ちょっと市場に買い物へ出るとき、酒場の便所を借りるとき、川面に浮かぶ明かりを頼りに家路につくとき、いずれも私が襲われた時の状況だ」
「いつも一人?」
「襲われる時は決まって一人のときだ。襲ってくるのも単独犯で、人が集まりそうになると逃げられる。まだ怪我をしたことはないが、いつ命を奪われてもおかしくない」
「不思議な状況……」
人気のない場所で一人のときに狙われるということは、なるべく人に知られたくないということだろう。官憲の目を厭わず犯罪に手を染める連中が大勢いる地域で、人目につかないように人を殺すという選択肢を取るのは、捕まりたくないという以上の意味を持つはずだ。それに人が集まりそうになると逃げるということは、アーベンを殺すよりも捕まらないことのほうが優先順位が高いということでもある。
「ルーさんはどう思う?」
アーベンはテーブルに肘をついて、ルイーズの目を真剣な眼差しで見つめた。その瞳には試すように挑戦的な態度が見え隠れしていた。理知的な風貌には似つかわしくない野蛮な気配に、ルイーズは面接であることを思い出した。
ルイーズは今、アーベンに試されているのだ。
落ち着いた素振りを取り、さも経験豊富な野伏であるかのように装って、考えをまとめた。
「たぶん命を狙われてるってよりは、脅されてると取るべきじゃないかな? いつでも殺せるぞってアピールをすれば一人で遺跡には行かなくなるでしょ? それが狙いな気がする」
恐る恐るアーベンの表情を伺う。
「私と同じ見解だな。まあいいか」
アーベンの目元に寄っていた皺は消えていて、鋭さを帯びた目つきからは力がすっかり抜けていた。ルイーズも自然と力が入っていた握りこぶしを緩めて、深く息を吐いた。
「じゃあ雇ってくれる? おいら今すぐに入り用があるんだけど」
アーベンはルイーズの変わり身の早さに目を丸くしつつも、軽く手を上に上げて、まだだとでも言うように首を横に振った。
「今日はもう一人呼んでるんだ。そっちも雇うつもりだけど、二人の相性があまりにも悪かったり因縁の相手だったりしたら困る。顔を合わせて、少し話でもしてほしい。調査は明日にでも行くつもりだから、前金だけなら明日朝イチに渡せるかな」
「それは聞いてないんだけど?」
「いま言った。朝イチじゃ不都合かな?」
「もう一人の護衛と調査が明日なことも!」
「じゃあ、今回は縁がなかったってことで」
「いや、それも困るって!」
ルイーズが手をぶんぶん回して抗議しようとした時、アーベンが突然立ち上がってテーブルの向こう側に手を振った。振り返ってみると、黒ずくめで腰に刀を佩いた獣人の女が立っていた。
「そいつが敵ですか?」
「仲間だよ、気にしないで」
手を振り回すルイーズが、彼女には敵に見えたのだろう。アーベンは空いていた椅子に座るよう彼女に促して、混乱するルイーズに説明をする。
「彼女はブラックフォックスって名前の傭兵だよ。巷じゃすごい強いって評判なんだよ。私も会うのは初めてだけど、やっぱり何か強そうだ。左手を使わないってのは本当なのかな」
「ええ。戦う時は右手しか使いませんね。仕事で支障がありますか?」
「いいや、どう戦おうが、守ってくれさえすれば十分だ」
本名には到底思えない名前の彼女は、アーベンの不躾な言葉にも不快感を示すことなく、淡々と答えた。アーベンの態度が違う気がして、ルイーズは不満げに鼻を鳴らした。
アーベンは先ほどの説明を繰り返した。その間も彼はブラックフォックス相手に興味津々といった態度を取っている。ルイーズは思わず嘆息した。一人だけムキになるのはバカみたいだ。
「ブラックフォックスさんは数十日間ここを離れるとしても問題ない?」
「私は構いませんよ。こちらの方も護衛ですか?」
「おいら? もちろん。ルイーズでもルーでも好きに呼んで。よろしくね」
ええ、とブラックフォックスは特に感情を見せることもなく相槌を打った。
「二人とも変な因縁がなくて良かった。じゃあ、明日。日が上りきる前に鰐口門の前で集合ってことでいいかな?」
「私は構いません」
「おいらも」
アーベンは満足に頷いてから、席を立とうと腰を上げた。それから思い出したように座り直して、ブラックフォックスへ申し訳無さそうな顔を浮かべる。
「三人組なのに女性はブラックフォックスさんだけで大変だろうけどなるべく気を遣うつもりでいるから、安心してね」
ルイーズはアーベンの顔をそっと伺ってから、ため息をつく。ブラックフォックスは二人の顔を交互に見遣って、少しだけ呆けたような表情を浮かべた。
「ま、そういうことでよろし……んわっ!」
ちょうど三人が微妙な表情で固まっているところに、野蛮な暴力の手が伸びてきた。
最初にルイーズが気づいた。椅子から跳び上がるようにして立ち上がり、飛んできたナイフの先にいるアーベンを突き飛ばす。姿勢を崩して床に倒れ掛かりそうになったところで彼も状況に気づき、隣のテーブルのスープの中に思い切り手をついて転ぶのだけはなんとか避けた。
「おい、何してくれてんだてめえ!」
胸ぐらをつかもうと立ち上がった隣のテーブルの大男の背中に、ちょうど運悪く飛び込んできた矢が突き刺さってテーブルもろともスープが血みどろになった。どさりと倒れ込む大男の影に隠れたアーベンの盾になるようにブラックフォックスが回り込む。
「敵は最低二人いますね。話と違いません!?」
店は逃げる客と立ち向かおうとする客でごった返してまともな視界が取れなくなった。階段に殺到する客の中からあがる悲鳴が混雑に拠るものか敵襲のせいかすら判別がつかない。ルイーズはテーブルの上に靴のまま登った。中腰で警戒しつつ、今まさにナイフを投げようと構えた人間がいることを確認する。
「便所の向こう! 顔隠してるやつ見える!?」
「そっちは私がやる」
言い切る前にブラックフォックスは壁伝いに走り跳びながら、敵へ接近した。ルイーズもアーベンを外へ逃がそうと振り返ったところで、彼の姿が既にないことに気づく。
見わたすと、ちょうど鎧戸の向こうへ飛び降りるところだった。
弓矢を持った人間は部屋の中に見当たらない。つまり、外から狙っている可能性もある。その状況で狭い鎧戸から出るのはあまりにも危険だった。
逃げ遅れた客たちを突き飛ばしたルイーズはそのまま勢い良く駆け出して、何とかアーベンの首根っこを引き留めようとしたが、もう遅い。足を枠にかけて飛び降りた。追ってルイーズも飛び降りると、風を切る鋭い音が耳をかすめた。
矢だ。
もう遅かった。ルイーズに打てる手は何もない。とっさに頭と胸を守って身体を丸めてやり過ごしたが、アーベンの悲鳴は聞こえてこなかった。
アーベン自身が、短剣を振りかざして矢を弾いたのだ。どこから矢が飛んで来るのか予測していたのだ。ルイーズがそれに気づいたのは完全に体勢を崩した後で、もう終わりだと思った時のことだったから隙が生まれていた。
二階から落ちて、綺麗に着地できなかったら足手まといになってしまう。ルイーズは瞬間的に手足をじたばたさせてどうにか体勢を立て直そうとするが、どうにもならない。
目をつぶって衝撃に耐える体勢を整える。痛みを想像して、歯を食いしばった。
激しい衝撃が身体に思い切りのしかかる。しかし想像していた痛みとは程遠い感触だった。
「……っ! 危ないな」
ルイーズの身体を支えていたのは、地面ではなかった。アーベンである。
とっさに腕から飛び退いたルイーズは顔を赤らめて、向かいの建物の陰に走り寄った。普段の仕事なら手をひっつかんでアーベンを引き寄せたが、いまは照れが混じって服をつかむことしかできない。弓矢の死角に入った二人は、そこで呼吸を整える。アーベンは地面に落とした短剣の代わりに、ナイフを一本取り出した。
そして、ルイーズのほうへ向き直る。
「ルーさん、女性だったんですか……?」
アーベンは二階から飛び降りてきたルイーズの意外にも柔らかい感触と微かに漂う甘い香水の匂いで、勘違いに気づいた。
甘い香りのルイーズは、汗で張り付いた髪の毛に表情が隠れて、アーベンからは伺えない。
緊張感と同居できない奇妙な照れが、お互いの間に纏わりついて離れない。まだ、向かいの店では激しい足音が絶えなかった。
Novel.725404
Tweet Follow @twoq_jp