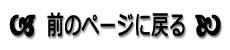●奇妙な魚料理
【登場人物】
・crc_0013:ルシェン
・crc_0017:シェック
・ヴェステルナ
・ルティン
「姐御ー。このさんま、出しちゃってもいいか?」
「ヴェステルナに? いいよ、出しちまえ。悪くなるから。あと姐御はよしてくれ」
白い漆喰の綺麗な昼下がりの酒場、”虎の鰭”亭には客は少ない。扉は開放されているが、通りを歩く人はそれぞれの仕事に忙しい。
人気店ではあるものの、平日の昼下がりにずっと酒場で飲んでいるような者は、あまりまともじゃあないのはどの世界でもそう変わらないものだ。
酒場の板前として働いている鬼人種の青年シェックは、フンスと鼻を鳴らして刺青の入った腕をまくり上げた。カウンターに座ってちびちびとワインを舐めていた黒衣の美女に、にかっと笑いかける。
「お許しが出た。さんまは足が速いからな、どうせ夜まで保たないし。トクしたな、ヴェステルナ」
「あぁ」
黒衣の美女ことヴェステルナは、シェックの手元を興味深げに覗き込む。
「これはおいらのクニの料理で……こうしてまず鱗を落としてワタを取って三枚におろして……包丁で叩くんだ」
「あっ。叩いちゃうのか。潰れちゃったりしないのか」
ルティンの料理を見るようになって目と口ばかり達者になったヴェステルナが口を出すと、シェックは仮面の下でにっと笑った。
「そこは腕さ」
両手に包丁を持って、トントンとリズムよくさんまの身を刻んでいく。
「叩き三年って言われたもんだ」
「三年も修行したのか。見えないな」
「おいら若く見えるから。舐められるんだ」
「すまない」
「そういう意味じゃない……で、ここにネギとジンジャーを刻んで混ぜて……」
「面白そうなもの作ってるな」
ほぼ出来上がったところで、ルティンがひょっこり覗き込んだ。後ろに垂らした耳がぴょこぴょこ言うのを、ヴェステルナはぼんやり眺める。
「ホイ、できたよ」
香草に乗せられたそれは一見ちょっとぐちゃっとしているが、ジンジャーの香りがさんまの臭みを消していた。
ヴェステルナとルティンがそれぞれ手を出す。
「へぇ」
「ほぉ」
潮の香りのするさんまにネギとジンジャーが合うし、香草の香りがそれを引き立たせている。
「これ、塩味のビスケットとかに乗せてもいいんじゃないかな」
「ワインのつまみに良さそうだ」
「オリーブ油とにんにくとかもいいかも」
「お前はすぐそれだな」
と、かしましい二人を、シェックは満足げに頬杖をついて見る。魚料理をしたくて砂鉄掘りから足を洗った彼だ。こういう姿を見るのがぜんたい好きなのだ。
「本当は一味足りないから、塩で代用してるんだ」
「へぇ?」
「なんていうか……こっちの言葉にないけど、大豆をつぶして発酵させたしょっぱい調味料があるんだけど……それがあるともっといいんだよ」
「うまいのか」
ヴェステルナは目をぱちぱちさせた。
黒王女として権勢を振るうこともできる彼女だが、世界には知らないこと、見たこともないものがたくさんあるのだ。それが楽しい。彼女の正体を知るのはここではルティンだけだが、じぃやアリカに文句を言われつつも続けているこの下町通いは、がんじがらめの彼女の唯一の気晴らしになっていた。
「うまいよ。なんて言ったらいいかなぁ。しょっぱいんだけどそれだけじゃなくて……」
「手に入らないのか?」
「姐御、それが材料はなくもないんだけど、タネがいるんですよ」
「エクス商会に注文できないかな……」
皿を前にしてうんうん行っていると、ぬうっと白い髪の青年が戸口に顔を出した。足元に小さな獣を連れている。
「持ってますよ。少しなら」
「わっ! あ、いらっしゃい! ……ん? 持ってるって?」
「ミソですよね? 自分の分ですけど、少しなら持ってます。あ、失礼、私、ルシェンと言います」
「前に何度か来てくれてたよな」
「覚えてらしたんですか」
「客商売だから」
カウンターの椅子を進めるルティンに、シェックが割り込んだ。
「持ってるって? ミソを?」
「えぇ。私も東の方の出身なんで。もしよかったらどうぞ」
ルシェンはふところから密閉される木の容器を取り出して、ぱかんと開けた。ヴェステルナとルティンが覗き込んで、顔をしかめる。
「臭くないか?」
「なんだこれ」
「これこれ!」
シェックは平手を立てる鬼人のお礼の仕草をすると、スプーンでひとかきすくう。ちょっと味見をしてから、さっきと同じようにさんまをさばいてそれを混ぜ込んだ。
「あああ」
「黙ってみてなって」
素早く仕上げたそれを、三人に突き出す。
「あ」「へぇ」「懐かしいです」
三人がそれぞれ感嘆の声を上げる。たしかに、さっきのは一味足りなかった。今は味に深みが増した気がする。
「思ったよりウマイ」
「だろ? あんた……ルシェンだっけ? ありがとうな」
シェックが細身の彼の肩を叩くと、笑った。
「あんた、普段は?」
「薬売りですよ。流れ流れて……。こちらはミケ」
足元の奇妙な獣が、ギェーン、と鳴いた。
「かわった獣だな」
ヴェステルナが椅子を降りてかがみ込んだ。おそるおそる指を出すと、ふんふんと匂いを嗅がれる。
「大丈夫です。賢いですから。その、もしよければ、ミソのぶんで彼に何か出してあげてくれませんか?」
「あぁ、もちろん。あんたもなんか食っていけよ。いいよな、姐御」
「姐御はよせって……。もちろん、こんな面白いものを見せてくれたんだからな。店長もいないし。ヴェス、ワインまだ飲むだろ。開けちゃおう」
ルティンが「なに食べるのかな、その仔」などと言いながら、奥に引っ込む。
「ありがとうございます。あ、そうだ」
ルシェンは丁寧に頭を下げると、鞄から小さな瓶をいくつも取り出した。
「よかったら何か買いませんか? いろいろありますよ。こっちは毛生え薬。これは風邪薬で、これは……あぁ、これは売り物じゃないです」
「商魂たくましいな」
シェックが苦笑して、瓶を一つ取り上げた。
「誰かと仲良くなれる薬はないかな」
ミケをつついていたヴェステルナが、視線を上げずにつぶやく。ルシェンは静かに答えた。
「なくもないですが、あなたの望みは薬ではないでしょう? きっと」
「……そうだな。忘れてくれ」
「おぉい!」
そんな会話に気づきもせず、ルティンが両手いっぱいに食べ物を抱えて戻ってくる。
「その仔、何食べるんだぁ? いろいろあるぞ。魚のきれっぱし、ハムのしっぽ、クズ野菜、骨……」
「なんでも食べますけど」
ルシェンは顔を上げて微笑んだ。
「そんなにたくさんは食べないですね」
昼下がりの酒場”虎の鰭”亭には客は少ない。
だが、こうしてちょっとした宴会が開かれることもある…。
Novel.hirabenereo
Tweet Follow @twoq_jp