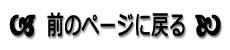●おまけのクリーム
【登場人物】
・crc_0001:ルミア・バリシス
・crc_0010:ウリエラ
・crc_0002:ヘンリー・オーグスト
・アルフレド
・エクス
「騒々しい人たちでしたね」
ヘンリー・オーグストは苦笑して、コーヒーを出してくれた店員のアルフレドに苦笑した。銀髪を揺らしてアルフレドも笑う。
酒場からの居抜き物件で、明るくリフォームされたカフェ・ド・エクスは、再び落ち着きを取り戻していた。開け放たれた扉からは港を行き交う人々が見え、大きすぎるほど大きな窓(この大きさの板ガラスは高価だったろう、と、ヘンリーは考えた)はもうすぐ春になる暖かな日光を取り入れている。磨かれた板張りの床に、天枝の影が落ちていた。
黒髪のヘンリー・オーグストは(彼のお給料にしては)奮発してこの店に来る。黙って座っているだけでも耳に飛び込んでくる古今東西の話は面白いし、あのあこがれの女の子に話しかけた時のために話題を作っておきたいし。もっともその機会は、彼が一歩を踏み出さない限り当面やってこないのだけれど。
彼は人見知りで、あまり積極的にあちこちに話しかけたりしない。そうできれば、人生はもっと面白いのかもしれないが、と、彼は思う。
カフェ・ド・エクスは、貿易商であるエクス商会の玄関口でもある。
商売に関する話が飛び交い、そしてそれ以外にも話の枕にするために、本当とも嘘ともつかない話を騒がしく聞くことができるのが、この店の楽しみだ。
しかし今日は、いささか楽しすぎた。
金髪の美女二人が長々と商会主であるエクスにクレームをつけていたのだ。なんでも、彼女らの注文していた品物が盗まれたとかなんとかで。
二人に絡まれていた商会主のエクスは、金髪をがりがりとかいて盛大に溜息をついた。
あんな二人になら絡まれてみたいものだが、当事者はそうは行かないだろうな、と、商売もやっているヘンリーはまた苦笑する。くだんの二人が一緒くたに「あんな二人」と呼ばれていることを知れば彼女らは猛然と反論するだろうが、彼はそんなこと知る由もない。
「来ると華やかになるんですけどね、あのお二人は」
「何の話だったんですか?」
「さぁ……僕はお店のほうばかりで、商会のほうは……」
言いながら、アルフレドはヘンリーに「お騒がせしました」と言ってクリームを出してくれる。
「コーヒーに落とすと、なめらかでコクがありますよ。今朝入ったばかりのとれたてです。どうぞ」
「わぁ、い、いいんですか?」
「えぇ」
唇の前で人差し指を立てるアルフレドだったが、目ざとい客にはどうやら無意味だったらしい。
「おぉ、タダか?」
「いいですねー」
ヘンリーの両脇から、他の客がずずっと距離を詰めて、彼は目をぱちぱちした。
「ルミアさん、ウリエラさん」
アルフレドが天を仰ぐ。
「いいでしょ。私にもちょうだいよ」
「僕も、彼に劣らず経済的に挑戦されているんですよー」
一人は少女だ。
黒髪に白い肌の小柄な女の子だが、その豊かな胸とお尻が年齢をわからなくさせている。ひょっとしたらもっといっているのかもしれない。ヘンリーは年頃の女の子にぐうっと近づかれて(対象が自分ではなくクリームであるとわかっていても)どぎまぎとなった。
もう一人はヘンリーより背の高い青年で、美しい長い白髪と整った顔立ち。紫色の澄んだ瞳は、今は朝採れのクリームに注がれている。ふわふわした羽のようなマントが、ヘンリーにはすこし邪魔くさい。
アルフレドはむぅ、と一声うめいて、二人のカップにもクリームをそれぞれぼとりと落とした。
「愛想がないわねぇ」
「モテませんよぉ」
「気が合うね」
「じゃあ、お近づきの印に」
少女と青年がヘンリーの胸の前でかちんとカップを打ち合う。
「ここは、酒場じゃないです」
アルフレドが口をとがらせた。
「似たようなもんでしょ……あぁ、わし……じゃない、私は、ルミア。ルミア・バシリス」
「僕はウリエラって言います。錬金術をやってまして。まぁ、あんまり儲からないんですけど」
二人が自己紹介し、そして視線を同時にヘンリーに向けた。ヘンリーは、どうやら自分の名前を効かれていることにようやく気づく。
「ヘンリー・オーグストです。あの、普段は指輪とか作ってます。僕も錬金術やってるんで、金属が出来たりできなかったりするんで……」
「へぇ!」
ウリエラがにこっと笑って、ヘンリーの前においてあったクッキーをつまんだ。
「ご同業ですねぇー。彫金をなさるなんて、器用なんですね。今度何か作ってもらおうかなぁ」
「あ、私も私も。せっかくかわいい女の子じゃもん。いろいろ付けてみたい」
「せっかく?」
「失礼」
この人達、タダで作らせる気かな……、とヘンリーが青くなっているところに、話し声を聞きつけた商会主のエクスがやってくる。小柄な彼女は小首をかしげてアルフレドをつついた。
「どうしたの?」
「いえ、その……」
「クリームを頂いたんです」
「僕も僕も」
「私も」
「あの、ちょっと騒がしかったので、おまけに、と」
アルフレドがしどろもどろになると、エクスはまばたきして彼の背中を叩いた。
「ならお客さんみんなに配ってらっしゃい。エクス商会は気前よく! 誠心誠意!」
「はい」
クリームのカップとスプーンを持ってテーブルを回りに行くアルフレドの後ろ姿を眺めながら、エクスはもう一度小首をかしげた。
「まったく、あの二人が来るといつもこう!」
「あの」
ヘンリーは尋ねる。
「何のお話だったんですか?」
小柄な商会主は年若く、少女と言って差し支えない。ひょっとしたら自分よりも幼いのではないか。こんな子が、今は双子都市ソーンの港で大成功をおさめつつある。好きな子に話しかけることもできない自分とは大違いだ。ヘンリーは彼女から、何か秘訣でももらえないかと思い、彼女を引き止めることにした。
「ん? さっきのです?」
「そうそう、大騒ぎだったじゃない」
「見ていて楽しかったですけどねぇ」
ルミアとウリエラも首を突っ込むと、エクスはカウンターの向こうに回って、エルフレドは使わないスツールを引っ張った。愚痴りたい気分だったのだろう。
「泥棒に入られたんですよ」
「エクス商会が?」
「そう。港の倉庫を借りてて、そこに入荷して審査待ちの品物を入れておいたんだけど……」
「鍵は?」
「もちろんかけてましたよ! 最新式のばね七つ!」
「そりゃすごい」
ヘンリーは思わず身を乗り出した。細工物を作る彼は、鍵職人さんにも知り合いがいる。
「すごいの?」
きょとんとするルミアにくどくど仕組みの説明をしかけて、ヘンリーはそれを飲み込んだ。ちょっとオタクっぽく映るかなと思ったのだ。
「すごいんです」
「そっか」
「何が盗まれたんですかぁ?」
「ほとんどは樹法具。レゴスメントから持ち込んだもので」
「抜け荷?」
「正規品ですよ。まぁ……ちょこーっとどうかなーってのも混ざってたりするかもしれないけど……。その鍵があっさり破られて、しかも現金にほとんど手をつけずに、樹法具がいくつか消えているっていう……。なーんか引っかかるんですよね……あの二人は追っ払いましたけど」
「裏街の仕業です?」
「いやぁ……大きな声じゃ言えませんが、ウチも裏街にはお金払ってるんで……裏街に文句付けたら、知らないって」
”裏街”とは、ソーンの夜を牛耳る犯罪者たちの組織だ。できればお近づきになりたくない連中が集まっている組合で、少なくともヘンリーはよく知らないし、知りたいとも思わない。
「モグリか」
ルミアがすうっと目を細める。このトランジスタグラマーは、ときどき少女とは思えない顔を見せた。
「でも一回泥棒に入られたくらいで傾きはしないでしょぉ? 僕、この店なくなると困るんですよねぇ」
「あはは。大丈夫ですよ。全部が盗まれたわけじゃないし、船が沈んだわけじゃなし」
ひらひらとエクスが手を振る。
「エクスさんが船に乗るといつも船が傾く、って、船長が文句言ってましたよ」
「そんなことないよぉ!!」
クリームを配り終えて戻ってきたアルフレドが、のこったクリームをカウンターの後ろの陶器の箱に収めながら意地悪く言った。あれも樹法具だ。中が低温に保たれるらしい。かなり高価なもので、しっかりした鎖で壁につながっている。ああいうのをまとめて盗んだのなら、ひと財産だろう。
「上で番頭さんが数字合わないって呼んでました」
「またぁ?! めんどくさいなぁ……。船乗りたぁい」
「はいはい」
「それじゃ、ごゆっくり」
エクスがさっきの二人も顔負けに文句を垂れながら去っていき、あとには客の三人が残された。
「大変だなぁ。犯人、見つかるといいですね」
ヘンリーが言うと、ルミアは目を細めてヘンリーとウリエラに言った。
「知ってる? モグリの盗賊に何をしても、裏街の連中は何も言わないの」
ルミアの目から剣呑な光が漏れて、平和主義者であるところのウリエラとヘンリーはそそくさと席を立ち上がった。
Novel.hirabenereo
Tweet Follow @twoq_jp